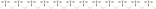Sick City
第一章・天岩屋戸
私が意識を取り戻したのは、仮面の神を倒した次の日だった。血液を大量に失った為に意識を失ったものの、外傷は特に無く、輸血と点滴で体力が回復した。念の為に翌日も検査入院をさせられたけど、その後は問題無しと診断を受けて無事退院出来た。
「とりあえずこの二日間で調べて分かった事は、イシュタルは自分の神域であるエ・テメン・アン・キに引き蘢っているだろうって事だ」
退院して自宅へと戻る最中の車上で蓮見が現状を説明する。ちなみに73式トラックを運転してるのは叶さんだ。
「この神は人間としての生活の気配が全く無い。神が人間の似姿を得て生き長らえたパターンでは無く、あくまで神のまま眠り、そのまま目覚めたという珍しいパターンのようだ」
「まあ風神っていう例もあるしねぇ……」
「風神?」
「ああうん、何でも無い。話続けて」
蓮見の説明に叶さんがぽそりと呟いたけど、私が聞き返してもそれ以上詳しくは話そうという気は無いみたいだ。
「だとすると、静ちゃんは一緒に神域に連れていかれた可能性が高い。一体何をするつもりなのかは分からないが、黙って見過ごす訳にもいかない。こちらから乗り込んで取り戻すしか無いだろうな」
「えっと、神域ってそんな簡単に行けるもんなの?」
蓮見の提案に対して私が疑問を口にすると、今度は後部座席に私と一緒に座っていた美雪ちゃんが口を開く。
「神と契約している人間が神の導きによって主神の許可の元、こちらの神域にあるゲートを通じてのみ他の神域へと転移が可能です」
「こちらの神域って二つ?」
「いえ、合流してくれたアヌビス神の神域を加えるなら三つになります。ですが主神はカンナカムイだけですので、神域カンナビのゲートを使う以外に方法は無いでしょう」
「全くその通りだな」
美雪ちゃんの説明に対し、今度は荷台に寝そべっていたアヌビスが応じた。
「肝心の鳴神は今何してんの?」
「彼は下準備をしているそうです。人の身で神域へと入るには、それなりの下ごしらえが必要なのです」
「そんな訳で俺達はこれから、楯山神社へと向かう」

73式トラックを楯山神社の駐車場に止め、私達は参道の階段を登っていく。鳥居を抜けて境内に入ると、幾人かの巫女さんと共に何だか忙しそうにしている皐月さんを見付けた。
「あら、あなた達来たのね。そろそろ準備が整うと思うから、私の後に付いて来て。案内するわ」
皐月さんの案内で境内の奥に進むと、注連縄で飾られた大きな岩が姿を見せた。
「この楯山という山に造成されたのが楯山神社なの。その造成時に生まれた切り立った山肌に洞窟が掘られて、このように岩で補強したみたいね。この洞窟の奥に、小さな祠があるのよ」
皐月さんの説明を聞きながら、岩で出来た洞窟の入り口にて立ち止まる。
「この入り口から神域に入るのよ。神域の側に主神がいて、それをこちら側にいる人間が認識する。それであちらへと行く準備が出来る。後はこの入り口の『門』が機能すれば問題無いわ」
その話を聞いていくらか理解出来たものの、同時に疑問も浮かぶ。
「えっと私は大丈夫だと思うし、蓮見と叶さんも大丈夫なんじゃない?認識面についてはもう準備出来てると思うんだけど」
カンナカムイの契約者である叶さんは常にカンナカムイを認識しているだろうし、蓮見はスリスと契約していてリーディングもあるのでおそらく認識可能だろう。私も二人の認識に同調すれば可能だし、既にその問題はクリア出来ている。しかし皐月さんは苦笑いを浮かべて補足する。
「いえ、私と佐伯君も同行する為なのよ。今回は既に守るべき対象の静さんがいないから、総力戦でいこうって伝一郎さんが。その伝一郎さんも来る筈よ。佐伯君が準備が終わったって伝えに行ってるから」
つまり準備は終わっていて、単に爺ちゃん待ちだった訳か。
「それともう一つ。『門』って何?何か特別なの?」
岩で出来た門は確かに何か意味があるみたいだけど、それがどういう役割を持っているのかは分からない。
「私も聞いただけだから詳しくは知らないのだけど、『門』とは瞬間的に違う場所へと移動出来るものらしいの。SFとかで出てくる転移ゲートみたいなものなのかしら。今、その調整をカンナカムイが行っているところよ」
そんなやり取りを終えると、境内に佐伯君と爺ちゃんが姿を見せた。こちらへと二人が歩いて来る。
「今回で終わりになればいいのにな〜。敵地に乗り込むって何かラストっぽいじゃん」
「アホか。おそらく『器の神』とやらを始末しない限り、終わりは来ないぞ」
「マジか。いい加減にして欲しいぜ……」
佐伯君の軽口をきっぱり否定した蓮見に、恨みがましい視線を向ける佐伯君。そんなやり取りを見て爺ちゃんが口を開く。
「終わりが見えているだけ以前よりはマシだろう。静を取り戻して『器の神』を倒せば、問題の殆どは解決だ」
「そんな簡単な事じゃないでしょ……」
佐伯君の恨み節を聞いていても気持ちのいいものじゃないので、さっさと話題を変えよう。
「んで、二人の認識をどうやって確保するの?」
「二人にはそれぞれ、神代より伝わる神器を手にしてもらう」
「何それ」
爺ちゃんの説明に思わず反射的に聞き返してしまう。また訳の分からない単語が出てきた。
「三種の神器くらいは知っているだろう?その内の二つ、『八咫鏡(やたのかがみ)』と『八尺瓊勾玉(やさかにのまがたま)』を用いる事で、通常の人間でも神域にいる神を認識する事が出来るのだ」
八咫鏡とは天照大神が天岩戸に隠れた時、天照大神を映す事で外へと誘き出したとされる神器だ。もう一つの八尺瓊勾玉とは八咫鏡と共に使われたらしいけど、実は役割がよく分かっていない。
「鏡は神域におわす神々を映し出す。勾玉は逆で、向こうからこちらの人間を認識するものだ」
「えっと、鏡はともかく、勾玉ってそんな意味があったんだ」
それは用途がよく分からない訳だ。神が必要としたのであって、我々人間側が必要としたものでは無い訳だから。
「勾玉とは己の魂を意味している。装飾品として身に付ける事で、病気などに対する身代わりとしての意味合いがあったらしいぞ。つまり勾玉の数だけ、代わりの命を予備としてストックしていた訳だな」
一応は人間側にも意味はあったのか。名目だとは思うけど。
「でもさ、三種の神器って失われたか、あったとしても皇室が所有してるんじゃなかったっけ?」
「それは歴史上の品の事だろう。俺が話しているのは神が持つ神器の方だ。こちらは唯一無二の物では無く、結構な数があるらしいぞ。地上の人間との繋がりを保つ為の神器だから、紛失した時に備えて神域にいくらでもあるものらしい。剣だけは別らしいがな。要するに皇室所有の鏡と勾玉は、そもそもいくらでも存在する物の一つに過ぎないと言う訳だな」
「ふむ、なるほど?」
そんなやり取りをしていると、巫女さんの内の二人が桐の箱を持ってきた。蓋を開けると一方の箱には青銅製らしき鏡が、もう一方の箱には瑪瑙(めのう)で作られたらしい勾玉が二つ入っていた。ちなみに瑪瑙とは、馬の脳みそのような縞模様をしているというのが名前の由来だそうだ。中に入っていた勾玉は紅色と緑色の二種類。鏡の方は一枚だけだ。
「皐月と佐伯の二名は勾玉を身に付けろ。鏡は蓮見が持ち、叶が投影するんだ。さすれば門は開かれるだろう」
爺ちゃんに言われた通り、皐月さんと佐伯君がそれぞれ勾玉を手にする。蓮見が手にした鏡に向け、叶さんが意識を集中させる。すると鏡の表面にぼんやりと人のようなものが浮かび上がる。
「ああ駄目。これで限界みたい。はっきりとした姿が投影される訳じゃないのね」
どうやら姿形からしてカンナカムイのようだったけど、薄ぼんやりとしていて顔だちまでは分からなかった。
「いや、そんなもんで充分だろう。向こうがこちらを全員認識出来れば転移出来る。行くぞ」
叶さんにそう告げた爺ちゃんがさっさと石の門へと入る。
「うおっ!?」
門の中が一瞬光ったかと思うと、中に入った筈の爺ちゃんの姿が消えていた。それを見た蓮見が後に続く。
「向こう側で全部処理してるみたいだな。地上では単に門という形状があれば機能するのかもな」
そんな事を呟きつつ、門を潜って姿を消した蓮見を追うようにして私達も後に続いた。

「……これは凄い光景だね」
転移した先で目にした光景に息を呑む。巨大な円筒の内壁を大地とした構造体の内部、整然と立ち並ぶ建造物は、鈍い色で照らされた金属製だった。金属を溶かしたダイカストという鋳造物に似ているけど、その強度は遥かに高く、まるで別物のようだった。
「よく来たな。早速だが『門』を使ってエ・テメン・アン・キに乗り込むぞ」
後ろから聞こえた声に振り向くと、巨大な門の側に佇むカンナカムイの姿があった。
「そんな事言われても、具体的にはどうやって?」
随分と簡単に言ってくれるので、思わず懐疑的な言葉が出てしまう。それに対してカンナカムイは鷹揚に頷くだけ。「分かっている。通常ならばいくら主神と言えども、他の神域へ乗り込むのは難しい。しかし幸いな事に、こちらにアヌビスがいる事で簡単になった」
その言葉に皆の視線が低い位置で止まる。
「別に簡単という訳では無いが、それは置いておくとしよう。まず、エ・テメン・アン・キは一般的にこう呼ばれている。『地獄』とな」
「地獄って、あの天国と地獄の地獄?ヘブン・オア・ヘルのヘルの方?」
「そうだ。そして天国とはこう呼ばれてもいる。『バベルの塔』とな」
この話は実に衝撃的だ。バベルの塔はエ・テメン・アン・キとの関連が以前から指摘されていたものだが、天国と地獄という概念と結びつくとは思いもしなかった。
「ここからが重要なのだが、天国と地獄はその信者の圏内における人間の魂を二つに選り分け、エネルギー源として吸収している。天国は教義における善、地獄は悪。では一体誰が、その善悪を判断しているのだ?」
「……えっと、うん誰?」
「私だよ。死を司る神アヌビスが、それら死者の善悪を選り分ける役割を持っていた。正確には私はエジプトにおける善悪を選り分けていたので、天国と地獄についてはシステムの構築に力を貸しただけなのだが」
なんと、そこでアヌビスが関わってくるとは。今も昔も中東という地域は様々な文化が衝突しているんだなあ、などと場違いにも思ってしまった。
「でもさあ、何で人間の魂を善悪に選り分けるとか面倒臭い事してんの?普通に太陽光とか重力だとか、自然エネルギーを使えばいいじゃない」
思わずこぼれた疑問。善とか悪とか胡散臭いし、何より人間をエネルギー源とするなんて気持ちいい話では無い。
「それはバベルの塔の性質による。バベルの塔は当初は各地の神域を高度なネットワークで結ぶ中継基地として構想されたものだった。それを唯一神を名乗る者が奪い、己の一極支配を完成させる為に利用した。まあその是非は今は問うまい。このネットワーク管理という特性により、情報を集約して管理する機能に長けた神域となったのだ。人間の魂という情報も含めてな」
「ああ、なるほど」
ここまでの話でようやく繋がった。人間の魂を情報という括りで考えるならば、それもまたネットワークで流通させる事が可能となる。
「うん?だけど人間の善悪を選り分ける必要って何なの?」
しかしネットワークと善悪が繋がらない。
「これも唯一神の支配体制による弊害だな。己を宇宙で唯一の絶対神であると主張した彼は、その主張に反対した全ての神と戦争を繰り広げたのだ。負けた者や賛同する者を天使と名乗らせ、それでもまだ反抗する者は悪魔だとして旧神域、エ?テメン・アン・キに縛り付けた。しかしこの戦争が終わる気配がまるで無くてな。致し方無しに唯一神は悪魔と停戦した。その条件が権益の半分譲渡だ。ネットワークに集まる人間の魂はそれまでの自然エネルギーと比べても、素晴らしく高効率のエネルギーになった。最終的にはこのエネルギーの権益が、争いの中心となってしまった。そこで唯一神は、悪魔に人間の魂の悪を分け与える事にした」
「えっと、凄く長いお話ありがと。でもその話聞いてるとさあ、これから乗り込むエ・テメン・アン・キって、もしかしたらいっぱい悪魔がいたりするんじゃないのかなあって、そんな事無いよね?よね?」
唯一神とか天使とか悪魔だとか全く持ってどうでもいいんだけど、これからの展開が何となく予想出来てしまって何とも言えない気分になる。
「うむ、その通りだ。エ・テメン・アン・キは地獄だからな。当然、数多くの悪魔達が立てこもっている。その数は数万とも数十万とも、それ以上とも言われている」
「うわ、マジかよ」
この話に一番引いたのはやはり佐伯君だった。そこでカンナカムイが補足をする。
「いや、別に悪魔を一々相手にする必要は無いぞ。こちらの目的は楯山静の奪還だ。敵を倒す事が目的では無いし、ましてや、明確に敵対しているかどうかも分からない悪魔達を刺激する必要もあるまい」
「そうだな。悪魔と出会っても基本は無視しろ。それで見逃してくれるなら良し、しつこく追って来てもとにかく逃げろ。逃げられないと判断したら戦うしか無いが、何万も相手に出来るか。静を見付けてさっさと帰るしか無い」
カンナカムイの言葉に爺ちゃんが頷き、一応の指針が出来る。これで粗方は疑問点が解消されたので、皆が一様に沈黙して微妙な間が出来た。それを頃合いと判断したのか、カンナカムイが皆を見回して口を開いた。
「さて、それでは敵地に乗り込むとしようか。アヌビスが死を司る神である事から、地獄への扉を開く事が出来る。帰還に際してはこの俺がいなくてはこちらへの門を開けないから、俺が生存してなくてはならないのが注意点だ。他に質問は無いな?ではやってくれ」
「分かった」
カンナカムイの言葉に応じて、アヌビスが門へとアクセスを開始する。膨大なエネルギーがアヌビスから門へと流れ込み、門の内側の空間が歪む。
「よし、これで繋がった。あまり長い時間維持出来ないから、さっさと入ってくれ」
アヌビスの言葉を聞いてカンナカムイが飛び込む。それに爺ちゃんが続き、蓮見や美雪ちゃんも入っていく。
「大丈夫なんだろうな?死んだりしないよな?」
「あーはいはい。さっさと行くよー」
入るのを躊躇う佐伯君の背中を押し、強引に門を潜らせる。
「うおい!」
抗議の悲鳴を上げるのを無視して、私も突入したのだった。


第十二話・荒神復活