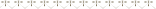Sick City
第三章・地獄結界
群がる下級悪魔達を退けながらバグダッド市内を目指していたのだが、そろそろ市内に入ろうかという所で周辺の様相に絶句した。
到る所で顔を黒いニットのマスクで隠した男達が銃を乱射し、或いは手榴弾を投げるなどといった殺戮、破壊行為を行っていた。その姿を見るにテログループの構成員だろうと思われたが、それにしても数が多い。イラク軍とアメリカ軍がそれを迎え撃っているのだが、突然爆発が巻き起こって次々と粉砕されていく。
これは人間に化けた下級悪魔達による、テロに偽装した破壊行為だ。
市内への入り口付近には倒壊したいくつもの建物の残骸があり、街へと到る境界線なのだと聞いた。
イラク戦争でアメリカ軍によって破壊されたイラク軍の戦車などが転がる中、俺は何とも言えない違和感を感じた。どうやら結界が張られているらしく、この中では悪意が醸成されて人間に悪影響を与えているようだ。
次々に死んでいく、大勢のバグダッド市民達。圧倒的な暴力を前に抵抗らしい抵抗をする暇など無く、命の灯火が消えていくのだ。
結界の手前で車を止めるようアルに指示し、車が停車するとすぐに俺は外に出た。
「この先では人間の思考を弄るノイズが充満している。誰もが冷静さを失い、殺し合いをしてしまう。皆はここで待機していてくれ」
俺の説明を聞いて皆が頷く中で、棗が不服そうな顔をしている。
「いくらなんでも、そう簡単に影響される訳ないじゃん。あたしを誰だと思ってんの?」
どうも棗は普段から自信満々なところがある為か、こちらの言い分を素直に受け取ってくれない。
「忍者娘だろ?」
「違う! ……忍者の修業もしてるけど、あたしは術の方がメインだもん。なんとか言ってやってよ、戸隠〜」
仁科三郎はロブ・クレイグを見張っていた筈だが、状況の変化に伴ってフェニックスによって呼び戻されていた。棗のお守り役では無いのだろうが、桐内家に代々仕えてきた仁科は、棗に対して遠慮が見える。
「お嬢、ここは零二君の言われる通りでしょう。確かに我らならば常人よりは自我を保っていられる時間は長いでしょうが、激しい消耗を強いられる事は想像に難くない」
俺と戦った時の敵対心など今は見えず、こちらの言い分をフォローしてくれる。それでも不服そうな棗だったが、突然、周囲を揺るがす不穏な気配に顔色を変えた。
「うッ!! ……な、何これ」
市内から溢れ出す、強烈な悪意に吐き気を覚えたらしい。車の陰で嘔吐している棗を介抱しながら、エリカがバグダッド市内に目を向ける。
「バグダッド市民を犠牲にして結界内で悪意を醸成すれば、地獄の門を解き放つのが容易になります。早く術者を倒さなくては」
車の屋根の上に座っているレラカムイに声を掛ける。
「……アンタはここで皆を守ってくれ。この先は俺とエリカ、それに飛鳥の三人で行く」
レラカムイは手を上げて、僅かに笑みを見せた。
「判った。こいつらは任せな」
フェニックスもアルも自分の身は自分で守れるだろうが、相手が下級悪魔であれば話は別だ。仁科三郎と棗も合わせて、四人で掛かれば一体くらいは倒せるかも知れないが、どちらにしても彼らには荷が重い。ここは棗と契約しており、教授の護衛も任せているレラカムイに残って貰うべきだろう。
「エリカ、飛鳥。行くぞ」
俺は二人に声を掛けて走り出す。
それを空を飛んで追い掛ける二人だったが、すぐに俺の先を行ってしまう。
「ああもう、あたしに任せて! ――メタモルフォー・ヒエラクス・プース!!」
俺の遅さに苛立った飛鳥が足を『メタモルフォー・ヒエラクス・プース(鷹の脚)』で猛禽類のソレに変化させ、俺の肩の上から脇の下を持ち上げる形で掴み、空へと舞い上がった。
「いてててててッ!!」
鉤爪が脇の下に食い込んで、痛みが走る。
痛みを訴える俺の声に、慌てた飛鳥が声を上げる。
「ごめん! 少し力抜くから、手であたしの足を掴んで」
飛鳥が力を抜くと、痛みが気にならないレベルになった。
腕を伸ばした先を掴むと丁度、飛鳥の膝の辺りだった。
上空からバグダッド市内に侵入した俺達だったが、眼下に拡がるのは阿鼻叫喚の坩堝となった地獄の如き光景。フクロウの眼を持つ飛鳥が、眼下の光景に顔を顰める。
「……ひどい。こんな事をするなんてあいつら、人の命を何だと思ってるのよ」
俺はそれに答えずに、『心眼』で敵の位置を探る。
市内に当初から配備されていた軍隊や警察組織は殆どが壊滅し、一般市民達が逃げ惑う中で強力なエネルギー体を発見する。
「飛鳥、俺をあの建物の上に空から落として一旦離脱してくれ」
いきなりの俺の提案に、飛鳥は怪訝な顔をする。
「何ソレ? 落とすって文字通りの意味?」
どうやら何を言われているのか、よく判らないらしい。俺はどうしたものかと思ったが、ロキが飛鳥の事を軽戦仕様とか言っていたのを思い出した。
「……ジェット戦闘機が訓練で滑走路に降りたと思ったらすぐにスクランブル発進する、タッチ・アンド・ゴーって言うのがあるだろ。判るか?」
そんなあやふやな例え話に、飛鳥の顔がぱっと明るくなる。
「あ〜、ニュースで見た事あるよ。何だっけ、岩国基地だっけ。何となく言ってる意味判ったよ」
やっと意味が通じて安心したが、俺は指差した建物が立派なものに見えたので、気になって横を飛ぶエリカに尋ねる。
「あの建物は何だ?」
エリカは何かを思い出すように考えた後、はっとして口を開く。
「……あれは確か、合衆国大使館ではないかと」
それを聞いて何故大使館なのかと考えたが、もしかしたらという考えが浮かぶ。
「ロブ・クレイグは何処に滞在しているんだ?」
その言葉でエリカも気付いたのか、忌忌しそうな表情で答える。
「……おそらく、大使館でしょう」
大使館らしき五階建ての建物の屋上に、強烈なエネルギーを持つ何者かが立っているのを感じる。
俺の意図を察した飛鳥はスピードを上げ、屋上の人影目掛けて飛んだ。
「――今だッ!!」
人影から少し離れた上空で俺の指示が飛び、飛鳥は俺の身体を離した。
空から落下してくる俺の姿をいち早く察知したロブ・クレイグは、バックジャンプで躱した。
着地した俺は落下のスピードをそのまま利用して、後方に着地したロブ・クレイグに居合抜きを一閃。
しかしロブ・クレイグが両手を振るうと、その手に光と共に一本の白い槍が現れて、俺の斬撃を防いだ。
「何ッ!?」
全てを絶ち斬る『一徹』を防ぐとは、ただの槍では無いという事か。
刀を鞘に収めた俺を、槍を構えたロブ・クレイグが見定めるような目付きで見る。
「……さすがにこう派手なショーを見せれば、気付かれても仕方が無いか」
俺の奇襲が失敗に終わった為か、エリカが俺の横に着地して声を上げる。
「以外と早く正体を現しましたね、ロブ・クレイグ!!」
ロブ・クレイグはエリカの登場に、さして驚く素振りを見せずにそのまま口を開く。
「……こちらも事情があるのでね。今を置いて機会は無いと判断した」
言っている意味がよく判らず、俺が顰め面でロブ・クレイグを見ると、本人は目を細めて説明する。
「何、こちらの事情に過ぎないさ。アスタロスがいよいよバベルの塔を呼び寄せるつもりの様なのでね。このまま素直に呼び出されるのは困るのだ」
それを聞いて何か矛盾を感じる。
まるで、アスタロスとは意見が違うとでも言っているかのように聞こえるのだ。
それに、以前に聞いた話も気になる。
「……確か、バベルの塔は天使達が接収しているとか聞いたな。このまま呼び出せば、天使もおまけで付いてきそうだ」
俺が疑問を口にすると、ロブ・クレイグは苦笑いを浮かべて答えた。
「その通り。なんとも無謀な試みだが……天使共を排除せねば、バベルの塔を押さえる事は出来ないからな。こちらも手を打たなくてはならんのだよ」
それは一体どんな手段なのか、とも思ったが、それをエリカが看破する。
「バグダッドを血に染め、死者の怨念を増幅させて地獄の門を一気に開き、悪魔の軍勢を呼び出すつもりでしょう」
エリカの言葉にロブ・クレイグは特に顔色を変える事無く、両手の白い槍をくるりと回転させて構えを取る。
「……お前達の存在がアスタロスの裏切りを呼んだ。元々、悪魔など寄せ集めの集団に過ぎないが、それでも今回の件は非常に困るのだ。済まんが、ここでお前達を消させてもらう」
槍の輝きが赤みを帯び、大気に満ちる怨念を吸収していく。禍々しい気を放つ槍が膨張し、長さにしておよそ5メートルもの巨大な大槍が完成する。
「……かつてローマの兵士、ロンギヌスがキリストを刺した槍。その曰く付きの槍は聖遺物として祀られたが、人の妄念など悪意と大差は無い。地獄の怨念を吸収し、この様に強力な武器へと変貌を遂げたのだ」
それは、あまりにも有名な槍だった。
俗に『ロンギヌスの槍』などと呼ばれた、聖遺物。しかし血塗られた歴史そのものであるかの如く、聖と邪を併せ持つその槍は、今や悪魔の滅殺兵器となったのか。確かヴァチカンにて保管されているとされている筈だったが、目の前にあるのだから事実は違ったのだろう。
仕立ての良さそうなスーツを着た欧米人が、巨大な槍を構えている姿はある意味シュールな光景だ。強烈な悪意を発散するその大槍に警戒感を抱いたのか、上空を旋回していた飛鳥が不意打ちを狙う。
「――ドーデカ・クーシポス!!」
空から突然降ってきた12本のブレードを、バックステップで難なく躱したロブ・クレイグ。先制攻撃に失敗した飛鳥が、さらに吸血羽根を射出しながら声を荒げる。クレイグは大槍を真ん中から回転させて、無数の羽根を弾き飛ばす。
「このオヤジ! さっさと正体見せなさいよッ!!」
あくまで人間スタイルを維持するロブ・クレイグに、さらにエリカが追撃する。
「いつまで人間に化けるつもりですか!!」
光の剣筋が間合いを無視して、一気にロブ・クレイグを襲う。それを横に避けたロブ・クレイグは、涼しい顔で答える。
「化ける? 勘違いされては困る。私はロブ・クレイグという人間そのものであり、ロブ・クレイグの意志でカナンの神バールと融合した存在である」
カナンの神バールとは、シリアの古代都市ウガリットにて発見された粘度板に記されている『ウガリット神話』などに、その名が刻まれている。その名はあまり有名では無いが、悪魔の中でナンバー2とされる『ベルセブブ』としてなら有名だろう。ナンバー3とされるアスタロスが本当の名がイシュタルであるように、ベルゼブブの本来の名はバールなのだ。
これらの事から悪魔とは、ユダヤの神ヤハウェに征服され、服従を良しとせずに神域を追われた神々の集合体なのだと判る。
「……人と融合する事で、契約無しで現世に関われる訳か」
どうして融合する必要があるのか、その理由を俺は理解した。その言葉にロブ・クレイグ=バールは、エリカと飛鳥を警戒しながらもこちらを見た。
「理解が早いな。力無き者が力を得ようと渇望するのは人の業。それに答えずして何が神か。我らとて、好き好んで悪事に手を染めている訳では無い。何かを成すならば、犠牲も厭わないというだけの事」
クレイグの言い分は理解出来なくも無いが、それは自然の行いとは言い難い。人である事と神である事、それがクレイグの信念であるならば、もっと違う生き方も選べる筈なのだから。そしてそれは、エリカと飛鳥には受け入れ難い。
「ふざけんな! そんな勝手な理屈で人の生き死に決めるんじゃない!!」
「……人はせめて死に際くらいは選びたいもの。人の上に立つ事を選んだ神が人の死まで好きにする。これが間違いであると今の私には判ります。貴方の言い分は到底受け入れられない」
神々の諍いで神域を追放されたセイレーンと、神の先兵として戦場で死んだ勇者の魂を神域に導いて、さらなる戦いに駆り立てたワルキューレ。クレイグの理屈はまさに、二人の辿ってきた苦渋の道を押し付けてきた側の理屈なのだ。
そしてその先にあるのは――自滅。
経済がインフレで膨張し、やがて自滅してしまうのと似たようなもので、力を追い求めればやがてコントロールを失い自滅する。しかしそれが、パワーゲームの中心にいるロブ・クレイグにとってどんな意味を持つのか。
「神の論理は既に崩壊した事は理解している。だが、我らを超える存在がいるのだと、それを知っている」
――超える存在とは何だ。
唐突に出た言葉に、俺はレラカムイの言葉を思い出す。しかし、そんな事を考えている暇など今は無い。
「議論など無意味だ。そちらが三人ならば、こちらも増援を呼ぶとしようか」
クレイグの背後に赤いオーラが立ち上り、まるでヴェルベットのカーテンのように拡がる。ゆらゆらと揺らめくその波間から、二つの膨大なエネルギー体が姿を現す。
やがて実体化した、二体の悪魔。
一人は全身黒い表皮に覆われ、禿頭に無感情な顔立ちをした黒人のような顔立ちをしていた。
「我が名はフルールティ。バール様、よくぞお呼び下さいました」
もう一人は灰色の長衣を身に纏った、長髪の白髪頭に白い顎髭のアラブ系の老人だった。
「――アガリアレプト、ただいま参上仕りまして御座います」
呼び出された悪魔はフルールティとかいうヤツが1200万程度、アガリアレプトと名乗る者が1000万程度。クレイグはアスタロスを上回って大体4000万程度であり、それぞれがかなりの強者だ。二体の悪魔はそれぞれ飛び出し、フルールティはエリカを、アガリアレプトは空へと跳び上がって飛鳥に襲いかかった。
「リヒトドルック・マハト・アン・オルドヌング――アオス・シュトーセン!!」
エリカは六つの光球を射出してフルールティに応戦するが、いきなり跳び上がったフルールティは追跡してきた光球に向けて両手を拡げる。
「クアール・ナシャーマー!!」
両手から吹き出した冷気が、ブリザードとなって光の球を相殺する。
一方のアガリアレプトは、頭上の飛鳥に肉迫しつつ身に纏った長衣を拡げ、その中から、いきなり無数のイナゴが飛び出て飛鳥に群がる。
「――げ、虫苦手なのよ!!」
嫌悪感に顔を歪ませ、飛鳥は片翼を振り降ろして突風を巻き起こす。風圧によって無数のイナゴが蹴散らされたが、その間隙を縫ってアガリアレプトが目の前に現れた。
「若いのう! カアッ!!」
アガリアレプトは大きく口を開き、何か黄色い煙を吹きかけた。
「うッ!?」
不意打ちを得意とする飛鳥が逆に不意打ちを受けた格好となり、しかも、それが変な息だというのだから対処が遅れたのだろう。見た目年寄りの臭い息を吸い込んでしまった事の嫌悪感は、さらに飛鳥から冷静さを奪う。
「……あれ?」
ぐらりと、飛鳥の身体が傾いてバランスが崩れる。空中での姿勢が保てずに、飛鳥は落下体勢になり、それをアガリアレプトが追撃する。
念動力の衝撃によって、飛鳥は地面に叩き付けられた。
そして俺は、クレイグの繰り出す槍の連撃を躱し続けていた。
「――フンッ! フッ! ハアッ!!」
巨大な槍の攻撃範囲はとても広く、連撃の速度もとてつもなく早い。刀の間合いよりも槍の間合いの方が広いのは当たり前だが、さすがに5メートルの長物は俺も初めてだ。
時折居合で槍の矛先を弾いてクレイグの体勢を崩そうとするが、純粋に腕力で大きく劣る俺の一撃ではびくともしない。『極線』の斬撃は全ての物質を断つ筈だが、ロンギヌスの槍が膨大な怨念を吸収し続けている為、一撃を受けてもすぐに別の怨念が実体を維持してしまう。
どうやらこのバグダッド市内で戦う限り、武器破壊は難しいらしい。
「どうしたサムライ! 近接戦闘はお前の領分だろう!!」
クレイグはさらに連撃を続けながらも、こちらを挑発してくる。しかし俺はそれには乗らず、あくまで相手の隙を伺う事に集中した。
異形の力で遠距離戦も可能だろうに、いきなり接近戦を挑んできたのが俺には不可解に感じられた。大槍そのものが異形の力だと言える訳だが、敢えてこちらの得意分野で戦うには裏があるのでは無いか。
例えば、これがエリカや飛鳥だとすれば、望まなくても遠距離攻撃をされる事もあるだろう。そうなれば接近戦に拘るにしろしないにしろ、どちらにしても消耗を強いられる。
しかし、ハナから接近戦しか出来ない俺を相手にした場合、消耗の激しい遠距離攻撃をしなくても戦える。遠距離攻撃も混ぜれば効果的だろうが、それをしない理由がある筈なのだ。
「それを言うならお前こそどうした。炎でも呪いでも、何でもすればいいだろう」
こちらの挑発に、クレイグは表情を崩さずに槍を引いた。姿勢を低くし、半身の姿勢から、大槍を頭上に掲げて水平に構える。
「……シェオール・ルーハ」
その声と共に、死者の魂がさらに集まる。今までとは違った攻撃が来ると予測し、俺は居合の体勢で足を大きく拡げて腰をさらに落とす。
「――ナークァブ!!」
クレイグの掛け声に反応し、大槍が手から射出される。飛来する大槍を紙一重で躱してバールとの間合いを詰めようとしたその瞬間、後方へ飛んでいった筈の大槍が突然、無数に分裂をしてこちらへ襲い掛かってきた。
「何ッ!?」
地獄の怨念一つ一つを槍に変え、それぞれが恨みの意志によって俺を標的として飛んでくる。それを絶妙な体捌きによって躱し、それでも躱し切れない槍を居合からの連撃で打ち落とす。分裂した為に軽いのが幸いして、何とか全てを躱し、或いは打ち落とす事に成功する。
しかし、躱された槍は再びクレイグの手元に戻り、元の大槍に戻る。俺の迎撃で失われた魂は、周辺に充満する死者の魂によって補充される。どうやらそれが、ロンギヌスの槍の特性のようだ。
「……人の妄念を集めた聖なる遺物は、怨念をも集めるのだ」
だがそれが俺に、ある予感を確信に変えさせた。
「……それはその槍の力だ。ならばお前自身の力は何処に使っている?」
その言葉には、さすがにクレイグも呻く他無かった。僅かに顔を歪ませ、ゆっくりと口を開く。
「……ふむ。さすがに誤魔化し切れないようだ。その鋭さは侮れないが、だからと言って素直に応じる訳にもいくまい」
本音を隠したがるのも判らなくは無い。何故ならば、それが一番重要な狙いだからだろう。
「地獄の門を開けると言ったな。しかし、こんな大規模な殺戮を必要とするからには、それが儀式とかそういったプロセスを整える為のものの筈だ。ならば、実行者は過大な負荷を負うと考えられる。力を使わないのは、既に別の力に労力を必要としているからだ」
だからこそ、クレイグはエリカや飛鳥とは戦わずに、俺と戦う事を選んだのだ。儀式を行いつつも、戦う事が可能な相手は俺だった訳だ。しかしそれを悟った今、素直に応じる訳にはいかない。こうして話をしてるだけでも、クレイグの時間稼ぎに付き合っている事になる。
エリカと飛鳥は、それぞれの敵と激しい戦いを続けている。しかし相手の策なのか、大使館から徐々に離されてしまっている。もし二人がクレイグの思惑に気付いていればすぐに滅殺兵器で片を付けるだろうが、今だ気付かない両者は、通常攻撃で相手の消耗を狙った戦い方を続けてしまっている。
狙いを看破されたクレイグだったが、俺に手があるとは思えなかったらしく余裕を見せる。
「それが判った所でどうにもなるまい。このバグダッドで戦う以上、利はこちらにあるからな」
しかし、こちらに手が無い訳では無い。単純に、その手段をやった事が無いだけだった。
「……ならば、結界破りをするしか無いな」
俺の一言に、クレイグの余裕が消え失せる。
「――何だと?」
おそらく結界を破れば、死者の怨念が一定の空間に充満する事は無くなるだろう。そんな事をしたところでこの場にいないアスタロスは大助かりだろうが、これ以上の殺戮を止めるにはクレイグの思惑をご破算にするしか無い。
俺はワルハラとオリンポスを認識し、『一徹』を通してアクセスを開始する。
同時に二つの神域に介入するのは初めてだし、それが一つでも難しいのだが、それ以外の手段は存在しない。以前、ワルハラの空間制御を用いてラビュリントス破りを成功させた事を思い出す。あの時はさらにエリカの空間攻撃『タオゼントヤーレ・シュぺーア(千年槍)』で、ラビュリントスの独自空間を解除した。
今回は異空間では無く結界だが、祓うべき怨念の量が膨大だ。これをワルハラ、オリンポスの二つの神域に吸引させて浄化を行う。
俺の脳に過大な負荷が掛かり、目や鼻、耳や口元から血が滴る。
その異常を、クレイグが驚愕の目で見る。
「何をしている? いくら何でも、この結界を破るのは不可能だ!!」
今までの余裕は何処へやら、バールは俺の試みを阻もうと大槍を突き出す。
脳の処理能力の殆どを神域とのアクセスに集中しているが、俺の肉体は乖離した自意識とは別に、勝手に反応する。クレイグの連撃を悉く躱し続け、クレイグが儀式に精神を集中しているのと同じ事を俺もやっていた。
突如、闇夜を切り裂くような光が空に二本、出現する。
赤い靄のように、バグダッドを覆っていた結界の妖しい光を貫き、天と大地の狭間に突き立つ二本の柱。
その威容を前に、クレイグは攻撃を中断して目を見開いていた。
「……神域を呼び出しただと? それも二つもか!!」
高次元空間コロニー――その名はワルハラとオリンポス。
神の住まう二つの宮殿に、仮想地獄とも呼べる結界内の亡者の魂が吸収されていく。吸収された魂は残留思念を除去されて無垢なエネルギーへと変換され、自然へと還っていく。さらに地獄の門は存在を維持出来なくなり、下級悪魔も全て退散する。
ワルハラとオリンポスの影響下では、下級悪魔達は存在を許されないのだ。
エリカと飛鳥にとっては、自分の所属する神域が現世に現れた事によって得られる恩恵は計り知れないものがある。何故ならば、多大なエネルギーの消耗を抑えられるだけで無く、神域から絶えずエネルギーの供給を受けるので使っても使ってもエネルギーが尽きない状態になるのだ。
二人の姿はここからは確認出来ないが、『心眼』で二人の戦いはどうやら決着が付きそうな事が判る。
互いに滅殺兵器を使ったのを感じた。
一方、結界を破られたクレイグは以外にもショックを受けたような様子は無く、あくまで冷徹な眼でこちらを見た。
「……一体お前は、何なのだ? 例え神でも、神域を二つ同時に呼び出すなど出来はしない」
クレイグにしてみれば俺のした事は理解の範疇を超えており、その疑問が大きい。しかしそんな事を言われても、俺にも自分が何者なのかなど判る筈も無い。
「ただの人間だよ」
それくらいしか言える事が無いのだが、クレイグはその一言にさらに警戒感を強めた。
「……莫迦な。ただの人間だと言うのであれば、神という存在が馬鹿馬鹿しくなる」
しかし、クレイグ自身答えなど出ないと判ったのか、仕切り直しとでも言うかの如く大槍を再び構える。儀式の為の精神集中を必要としなくなった今、クレイグの全力が明らかになるだろう。
「今度は私の全てで応じよう。行くぞッ!!」
強烈なプレッシャーと膨大なエネルギー。
クレイグの瞳が妖しい光を放ち、明滅する。
途端、視界が歪んだ。
それだけでは終わらず、全身に痺れが奔る。
「ぐッ!?」
視神経より入ってきた何かしらの情報により、脳から肉体へ送られる命令が阻害されている。己の能力が効力を発揮していると確信したクレイグは、ニヤリと笑みを浮かべた。
「ただの人間と言ったな? ならば、魔眼の呪いに抗う事は出来ないだろう」
俺はその声を、辛うじて聞き取った。
魔眼と呼ばれる、魔性の力。
その実体は虹彩の変化、即ち瞳孔の開きを調節して眼球内に入る光の量を調節する機能を利用し、逆に内面より光を発して明滅による情報の発信を可能とする能力だ。
これは眼を閉じていようとも、防ぐ事は出来ない。
何故かと言えば、例え眼を閉じていても、瞼の裏に光を感じる事が出来る為であり、人が太陽の下で活動する生き物である限り、その生理は変わらないからだ。
発信された情報がどんなものなのかは判らないが、クレイグ程の力の持ち主ならば、眼だけで人間の心臓の活動を停止させて、即死させる事も可能な筈だ。
そしてその予感の通り、俺の心臓が止まろうとしている。しかし、ここで俺の自意識は、またも肉体の制御から離れた。
代々の崎守が受け継いできた、魂の伝承。
この手にその実体である『一徹』がある限り、かつての崎守がそうだったように、俺の肉体は大地の記憶に繋がる『一徹』によって勝手に動く。
無理矢理、動きを再開した心臓。
クレイグはぎょっと眼を見開き、その場から一気に飛び退く。その危険察知能力に感心しつつも、俺は静かに口を開いた。
「……俺を止めたければ、この刀を止めなくてはならない」
有り得ない事実を前にして、クレイグは魔眼を中止した。
「……多少は理解した。確かにただの人間だ――但し、その肉体のみはな」
理解が早いな、と素直に感心する。
悪魔と聞けば欲望の権化かと思われるが、このバールには高い教養と知性、思慮深さを感じる。
地獄の怨念を力とする悪魔はその怨念の影響により、破壊や殺戮、あらゆる欲にまみれた存在となる筈だ。しかし、元々の神としての強大な自意識によって、その影響下にありながらも自制心を保ち、神本来の個性を失わずにいるのだから益々侮れない。
俺は目の前の偉大なる敵に、敬意を持った。
「……アスタロスの狙いは、ネットワーク管理神への復帰だと言う。どうしてそれに協力しないんだ?」
悪魔同士の仲違いの様相に、俺は当事者へ疑問をぶつけた。もしそれを知る機会があるとすれば、今この時をおいて他には無いだろう。クレイグ自身も俺に対して一定の評価を持ったのか、案外すんなりと口を開いた。
「……我ら悪魔は、総じて神域を奪われた存在である。衰え、消滅する時にアスタロス――イシュタルの属する神域『エ・テメン・アン・キ』に匿われたのだ」
突然出てきた話は、悪魔誕生の秘密とでも言うべきものだった。この中東地域は、歴史的にあらゆる国が勃興を繰り返し、複雑な事情を持っている。それが神の世界にも当て嵌まるのか。
「だが、他の神の存在を許さないヤハウェ神はそれすら許さず、攻め入ってきたのだ。徹底抗戦の末に追い込まれた我らに、ヤツはとんでもない提案をしてきた……我らに人の怨念を受け持て、と」
キリスト教徒、ユダヤ教徒が聞けば憤慨モノの話だろうが、他の信仰を排斥してきた歴史は覆らない。
俺はどちらの側にも言い分はあるものだろう、と冷静に聞いていた。
例えば人間世界においての戦争でも、敗戦国は戦勝国側の『正義』の生け贄となる。
その最たる例は、アメリカと日本の関係。
戦後の日本が退廃に流れ、常に左翼的イデオロギーを持った団塊世代の活動家を筆頭とする内部勢力とマスメディアに世論誘導をされ、或いは周辺国に戦争責任を捏造されて金や技術を毟り取られる状況は、そもそもはアメリカの『正義』が、日本の歴史認識を阻害しているのが要因である。
太平洋戦争などお互いに責任があるのに、今もってアメリカの政治は、『正義』という自国民への説得材料を捨て切れずにいる。
もしも当時の日本が『悪の枢軸国』では無かったのだとしてしまうと、西欧諸国の植民地政策から現在までの数々の戦争の正当性が怪しくなってしまう。
おそらくは、独裁政権で排他的思想を持った当時のドイツ・イタリアとの三国同盟が、『悪の枢軸』とのレッテルを貼られた大きな要因になってしまったのだろう。
当時の日本がナチスと同じく軍国主義であり、軍部による暴走が戦争の原因だとされているのも全て偽りだ。議会制は機能しており、国民の意志によって戦争に突入したというのが歴史の真実なのだ。
ただ、敗戦濃厚となった時点で一部の軍部強硬派によって停戦交渉への働きかけが遅れ、それが要因となって原爆投下を阻止出来なかった面は否めない。
当時のアメリカの戦略によって、戦争へと突入せざるを得ない状況に立たされた日本の立場は、結局は国際情勢の中でのスケープゴートにされただけの事だ。
国防を人質に取られている現在、アメリカの立場に配慮せざるを得ないのが日本の政治なのだが、それが為に正当性を主張出来ず、そこに付け込んで自分たちは被害者だから永遠に保証をしろ、あわよくば日本の全てをよこせと、間違った主張がまかり通る。
だが、結果を見ればアジアの全ての国々は独立を果たした訳であり、それは西欧世界による植民地化への抵抗が成し遂げられたという事だ。負けたから、被爆したからと自分たちを貶めるのでは無く、今ある結果に一定の評価を持ってもいいと俺は思う。
少なくとも、原爆を落とした国が『正義』など、そんな筈が無いだろう。
だからと言って、今更アメリカを敵視すればいいと言う話では無い。この星に生きる全ての者がお互いに成長し、少しずつでもより良い方向へ進歩して行く。その努力をする責任が、一人ひとりにあるのだと皆が意識する、そんな社会になったらいいと思う。
だが、自己欲を剥き出しにした身勝手な主張一辺倒の戦争責任を、一々鵜呑みにしては社会も文化も滅んでしまう。
戦争に参加した全ての国は、そこに至る過程において、何処か間違いを冒していたのだと何故言えないのか、不思議でならない。まずは、我々日本人の意識が変われば、少しはマシな世の中になるのかも知れない。
間違いを間違いだと正す事すら許されない病んだ世界――矮小化するなら『街』と言い換えても通じる。
それが戦後の世界、『病んだ街』――地球。
病理に蝕まれるコミュニティを放置したままでは、いつか世界は破綻するだろう。まずは日本が真っ先に、破綻の危機を迎えるだろうが。
「苦渋の選択ではあったが、エネルギーの供給が無くては我らは存在を保てない。その決断によって、我らは悪魔と罵られるに相応しい存在へと変容した。力の弱い者は力に溺れたが、それでも高い能力を持った一部の者は自我を保っている。イシュタルもそういった者の一人だ」
ならばバールも同じく、自我を保っている者の一人なのだろう。
それが今では、両者が争っている。
「……ならばイシュタルの目的は、間違いだと思っているのか?」
俺は両者が争うには、何か目的の相違があるのかと疑問に感じた。
クレイグは口元を歪めて首を振る。
「間違いでは無い。イシュタル自身の成り立ちに関わる事なのだから、言える事など何も無い。だがそうなれば、メソポタミアの神では無い者は地獄を追い出されるだろう。地獄は正常化し、元の『エ・テメン・アン・キ』に戻るのだ」
地獄が地獄で無くなる。
それは、悪魔という存在の否定でもある。確かに今の話通り、イシュタルと争うに足る理由だ。しかし、新たな疑問も噴出する。
「……イシュタルはワルキューレに対し、秘宝の力が無くてはバベルの塔の復活は無いと言った。ネットワークの復旧に必要なのか、俺にも判らないがそんな所だろう。今の状態で、イシュタル単独でバベルの塔が動くと思うのか?」
何処かで引っ掛かっていた疑問だった。俺達はアスタロスと戦ったあの時以来、一度もアスタロスと接触をしていない。しかし今の状況だと、イシュタルは単独で目的を果たそうとしている事になる。
「……完全な復活は無理だ。だがネットワーク管理神なのだから、一部の機能は復活させるだろう。問題なのは、バベルの塔を制圧している天使共だ。長らく眠りについていたヤツらが目覚め、再びこの世界に君臨しようとするだろう」
悪魔としては天使の介入は避けたいのか、しかしよく判らない事ばかりだ。
「天使が介入か……何が問題なのか判らないな」
悪魔にとっては敵対勢力だろうが、人間にとっては天使は別に敵では無いだろう。
しかしクレイグは、やれやれと言った風情で首を振った。
「主無き今、天使共はカリスマ独裁者を失った独裁国家みたいなものだ。ならば何をするかと問われれば、おそらくは残りカスに縋るだろう……それは志し半ばで諦めた黙示録の結末――全面戦争だ」
それがどんな結末になるのか、俺でも想像が付いた。
「……イシュタルの試みは天使に阻まれ、地獄からのエネルギー供給を断たれた悪魔は全滅。現世は天使達の力の開放で、荒れに荒れる」
俺の予測にクレイグも同意なのか、首を縦に振った。
「そうだ。ならば私は地獄が無くなる前に全ての悪魔を召喚し、イシュタルがバベルの塔を呼び出した直後を狙い、天使共に不意打ちを仕掛ける。地獄が無くなるならば、天国を制圧してしまえば良い」
何とも無茶苦茶な理屈に驚いた。
――結局、現世が荒れるだけでは無いか。
しかし、その試みはたった今、俺が打ち砕いたのだ。
「地獄の門が消えた今、それは無くなった筈。残るはイシュタルの無謀な試みだけだ」
その言葉に、クレイグは薄っすらと笑みを浮かべた。
「……イシュタルを止めるか。それとも、お前が天使と戦うのか?」
俺はそれには答えず、質問に質問で返す。
「――アンタはどうするんだ?」
お互い腹の探り合いだったが、クレイグは少しだけ間を置いた後にゆっくりと口を開く。
「……さて、こうなっては再び殺戮をしたところで間に合わんだろう。バベルの塔の起動は防げないだろうが、天使共に殺されるのは面白くない。せめてお前を殺し、全体の何割の悪魔を呼び出せるか判らんが、天使共と対決するつもりだ」
どうやら、俺を野放しにしておくつもりは無いらしい。こちらとしても、大量殺戮を平然と行ったクレイグを許すつもりは無い。
「……神による支配など必要無い。悪魔の暗躍をいつまでも許すつもりも無い。イシュタルもアンタも止めてみせる」
俺はそう告げると、腰を落として半身の構えを取った。しかし先程までの戦闘で俺に対する警戒感を強めたのか、クレイグは大槍を頭上に掲げ持った姿勢のまま動かない。
――ならば、攻めさせるまで。
摺り足のまま、じりじりと間合いを詰める。同時にクレイグも、同じく少しずつ間合いを詰めてくる。このまま間合いが詰まれば大槍の攻撃圏に入ってしまうが、ぎりぎりの距離でお互い静止した。
ここからは純粋に、チキンレース的な駆け引きの勝負になる。
相手の眉間辺りに視線を合わせ、クレイグの全身を漠然と眺める。
どちらにしてもクレイグの先手は変わらないのだが、まずどんな攻撃手段を用いてくるのか、それをどう避けてどう攻撃に繋げていくのかと先の展開を読む事が重要になる。
――だが、クレイグは奇策に打って出てきた。
『心眼』の感覚域に、大量のエネルギーが渦巻いているのを感じる。
「まずい!!」
俺はその場から一気に反転運動に入り、クレイグの右から回り込んで側面を取った。遅れて、地面から何百という黒い影で出来た腕が伸びていた。あれはおそらく、僅かに残留する地獄の怨念で生み出したものだろう。
「……ち」
舌打ちしたクレイグは、右側面に回り込んだ俺に目掛けてロンギヌスの槍を突き出す。
今まで己の立ち位置から動かずに迎撃してきたバールは、今回は槍と一緒に身体ごと突っ切る。
その突撃を躱して、さらにクレイグの背中に回り込む。だが地上戦に拘るつもりも無いらしく、あっさりと空中へと飛んで背後から攻撃させない。即座に空中でこちらに振り返り、膨大な亡者の魂をロンギヌスの槍に集め始める。
「……そろそろ決着を付け、その後でイシュタルを処断せねばならん。この私の本気の姿をとくと見よ」
黒い波動を吸収したクレイグの肉体が、劇的な変化を起こす。
見る見る内に膨張した肉体が、スーツの生地を内側から押し破り、黒い表皮に覆われた全身が露となった。頭部は白い外骨格に覆われ、髑髏のような顔に四本の角が後頭部から突き出ている。背に生えた黒い翼をはためかせ、さらに巨大化したロンギヌスの槍を掲げ持つ。
「……闇の滅殺兵器を受けてみろッ! ――ラークィア・コカーブ・オール・ゲシェム!!」
膨大なエネルギーを有したロンギヌスの槍を投げ槍競技の如く、大きく腕を振りかぶってから上空へと投げ放った。
怨念を凝縮されて赤熱した大槍は、軌跡を描きつつ遥か天空を駆け登っていく。凄まじい速度を以て成層圏を突き抜け、夜空に無数の紅い星が輝いた。
それが何を意味しているのかその内判る事になるだろうが、素直にそれを待つ訳にもいかない。とは言っても相手は空に逃げている為、こちらからは手出しが出来ない状況である。
一方のロンギヌスの槍は成層圏を突き抜けた時点で俺の認識外であり、今までの様な予測は出来ない。
『心眼』の認識には『個』『群』『空(くう)』の三段階があり、『個』は自身、『群』は他者、そして『空』こそはこの地球という星全ての認識であり、地球の外に対しては及ぶ所ではないのだ。
だが、何らかの攻撃手段である筈なのだから、十中八九、成層圏外からの超々遠距離射撃、しかも大出力の精密レーザー光線の集中照射による、肉体破壊を狙うものではないかと考えられる。それも広範囲かつ細密、回避も防御も俺には絶対に不可能だ。
何故そこまで予想が可能かと言うと今まさに、天空に新たに輝く無数の星々が数をみるみる内に増やし、さらに紅い輝きを増してきているからだ。
まさに無敵の技と言えるかも知れないが、唯一の欠点は、実際に攻撃が始まるまで時間が掛かるという事になる。
正直、この技が発動されてしまえば俺にはどうする事も出来ない。発動するまで時間が掛かるのであれば、その前に何とかしなくてはならない。
俺は鞘に収めた『一徹』の柄を逆手に握り、目前に立てて掲げ持った。今まで数々の戦いを経験してきたが、全く初めて取った構えを見て、空中のバールは怪訝そうな表情でこちらを注視していた。
「……その構えは情報が無いな。しかし、届かぬ敵にどう対処しようと考えているのか興味深い――その挑戦、受けて立とう」
こちらを侮る事無く、俺の一挙手一投足を冷静に観察していると判るだけに、多少の失望を覚えてしまう。これから俺がやろうとしている事は、相手の隙を作り出す試みであるのだから、なるべく相手には油断をして貰いたい。
だが、バールは油断など全くしていない。
やがて俺の予測通り、遥か天空より膨大な数の精密レーザーが降り注ごうとして、特定の空域が輝きに包まれた。
「どうやら私の勝ちが見えたな」
――今だ!
空からレーザー光線の雨が降り注ぎ、俺の身体を余すところ無く覆い尽くそうとした時、バールは己の勝ちを確信して、とうとう慢心をした。
隙と呼ばれるものの、本当の意味。
それは、心から生ずる。
逆手に握った『一徹』を鞘から抜き、右肩の上に振りかぶって空中のバール目掛けて投擲。レーザーシャワーが俺へと到達する寸前、己に向けて飛んでくる刀をすんなりと躱すバール。
「……悪足掻きか」
しかし、回避する為に注意が俺から逸れ、一瞬だけ刀に眼を向けてしまったのだ。膨大な光量を誇るレーザーシャワーによって、俺の姿はバールの視界に映らない状態になり、勝利を確信したのか光の洪水を見て笑う。
「……さて、ワルキューレとセイレーンの始末もしておくか」
やがて光は集束し、再び大槍へと戻ってバールの右手に納まった。しかし、有る筈の俺の死体がそこに無く、バールは戸惑いの表情を浮かべた。
「……おかしいな。本来は細胞の死滅という結果だけであって、死体が無くなる訳では無いが」
だが、さらなる空中より飛来する気配を感じたのか、バールは慌てて頭上へと大槍を突き出す。
大槍が、縦に構えた鞘にブチ当る。
「その危険察知能力には驚いた」
ギャリギャリと、鞘と槍が当る音が立つ。
バールの目線が俺の眼に合い、絶対の自信を以て放たれた筈の攻撃が無駄に終わったと悟って、悔しげにその眼はギラついていた。
「……馬鹿な。アレを躱したと言うのか」
左の鞘が下から持ち上がり、斜めへ傾く。
大槍に沿って落下した俺はバールの胸を蹴り、反動で身体を引き剥がす。中空に跳び上がった俺を見てバールはギョッと眼を丸くし、大槍のエネルギーを増幅させて、一旦後ろへと退きつつこちら目掛けて伸長させる。
「――ナークァブ!!」
しかし、再び鞘で矛先を防いだ結果、俺の身体を弾き飛ばす形になる。俺は大槍の矛先を、立てて構えた鞘で自身の身体を逸らしつつ、逆手のまま一気に抜刀、バールの額に刀を投擲。
ドスッ!!
「――――うがッ!?」
槍と刀が線状で擦違い、引き剥がされた俺は自由落下し、バールの額から後頭部に、刀身が突き抜けていた。
これぞ天仰理念流居合術・逆手抜き居離(いばなれ)。
居合とは座して抜刀が基本としてあるが、もしも、敵が必殺を期して放った一撃に対処するにはどうすべきか。居合の『居』とは座っている状態を指し、『合』とは接触、即ち抜刀。『居離』とは座った状態から一気に離れ、後退しつつさらに剣から手を離す事を意味する。
相手の必殺に対抗すべく生み出された、対必殺。
それを可能とする最終手段は自らの武器を放棄する事であると、長い歴史の中で得た答えであった。
バールは『点殺の術理』によって頭蓋を貫通させられ、力の源泉たる地獄との繋がりを断たれ、絶命した。
声さえ上げる事も叶わず、エネルギーが霧散して肉体が崩壊する。
大使館の屋上に着地した俺は頭上より落下してきた『一徹』を右手で捉まえ、鞘に収めた。


第六話・魔神騒乱
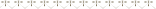
フルールティ
アガリアレプト