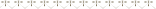Sick City
第一章・遺跡異聞
空一面に拡がる雨雲によって、普段よりも暗い夕方。以前に足を踏み入れた事のある大学の片隅に、教授こと、南一郎教授の研究室がある。
大量の書籍や、資料らしきプリント類が山積みとなって、足の踏み場にすら難儀するような雑然とした室内。俺はエリカと二人で、学校帰りに立ち寄っていた。
「それでは兄は、自分が指輪の継承者だという自覚があったのですね」
エリカは今日になってやっと、南教授の口から兄の事を聞かされた。口髭を弄りながら話す南教授を、俺はエリカの横で黙って見ていた。
「詳しい事は知らんが、きっとそういう事なんだろう。彼は自分の出自を調べ上げ、指輪を年代測定器やX線での構造分析にかけたりしていたと聞く」
南教授の説明に、エリカは哀しみを抑えて答える。
「指輪を起動させるつもりだったのでしょうね……しかし、兄は根っからの学者タイプ。どんな手段を用いても、結局は指輪の力を引き出す事など出来なかった」
そこで南教授の後ろで、待機していたレラカムイが口を挟む。
「……しかし、それで諦めた訳じゃあ無かったって訳か」
レラカムイは南教授が再び悪魔に狙われる可能性を考慮して、ボディガードみたいな事をやっている。レラカムイの言葉に、南教授が頷きを返す。
「うむ。彼は死の直前まで、日本の古代の伝承などを調べていたらしい。それで見つけ出したのが、鎌鍬周辺に伝わる鬼の伝説だ。鬼を殺したと言い伝えられる家柄、それが崎守だった訳だな」
その話は俺に関係するので、敢えて口を挟む。
「……それでホームステイ先がウチになったのか」
偶然にしては出来過ぎだと思っていたが、実はエリカの兄の意見によってウチに決まったらしい。
しかし、どうして崎守に着目したのか。
「彼らしい、突飛な発想だと言えるな。日本は全ての神を受け入れる、不思議な国だと彼はよく語ってくれた。これだけ近代化を成し遂げているのに、未だにイタコや巫女などのシャーマンが現存している。しかも神に祈りを捧げ、実際に力を発揮する。それは日本にまだ神が、いるのかも知れないからなのだと」
実際のところはどうなのか、俺にはよく判らない。
しかし、霊能力や超能力は本当に存在するし、神を信じない俺には聞こえないのだろうが、神を信じているシャーマンならば、この日本に存在する神の声を聴く事もあるのかも知れない。
神を信じないと言うのは、少し語弊があるかも知れない。『神は存在する』が、『神の教える教義を鵜呑みにはしない』と言った方がいいか。例えば歴史上の人物、織田信長や宮本武蔵は、生涯を通して神仏を信じなかったと言われる。
その気持ちは、なんとなく判る。
おそらく、彼らは神仏に依存して『考える事を放棄する』事が我慢ならなかったのだ。自分で考え、自分の思考力によって結論を導き出す。そうでなくては、人間は新たな進化を得る事など出来はしないのだ。
「神を復活させる可能性、もしかしたら崎守ならばと考えたのかも知れん。しかし、自分の妹が神かも知れないなどと、どうして考えたのかな」
南教授の考察は充分に納得のいくものだったが、最後の一言には俺も考えさせられる。しかし、当の本人は違う感想を抱いたらしい。
「……それは、私が少し変わった子供だったからかも知れません。実は幼少の頃に、念動力を使って周囲の大人を驚かせた事があります。尤も、物心付く頃には周りの目を気にして、人前では使わなくなりましたが」
エリカの子供の頃の話には興味をそそられるにしても、それだけで自分の妹が神では無いかとか思う筈が無い。それに俺には、もっと別の疑問の方が重要だった。
「……よくウチの事を調べられたな。一般的に知られている事など、何も無いんだけどな。親類縁者ならともかく」
だが、その疑問はエリカの説明が解決した。
「祖父同士が知り合いでしたからね。兄は頻繁に、崎守家にお話を聞きに伺っていたと聞いた事があります」
こうして一つずつ疑問が解消されていくと、俺達は出会うべくして出会ったのだという結論に到る。どうやらウチの狸爺は、エミール・シュタインメッツと会っていた事実を俺には黙っていたらしい。
レラカムイは腕を組んで、静かに口を開く。
「……この星の全体意識が、お前達の出会いを決定付けたんだ。きっと、何らかの役割を期待されてるのさ」
何だか、気持ちの悪い話だ。
自分で選んだ行動の結果なのに、それは既に決まっていたのだと言う。こういう人間になった時点で、俺の選択は同じ結果しか生まないのか。何だか釈然としない気分を抱えたまま、話題は違う方向にシフトする。
「――それで、バベルの塔の件なんだがね」
こちらの話も重要で、未だにアスタロスの動きが読めない。教授から得た情報を元に、これからどう出るのか、可能な限り予測をしなくてはならない。
「現地のムラサメ商事の動きが少々妙だと、スタッフから聞いているんだ」
ムラサメ商事とは、現地で原油の採掘を行っている日本企業の名だ。
「どう妙なんだ?」
俺の質問に、南教授は難しい顔で答える。
「……それが理解出来ない話でね。採掘権を持っている筈のグローバルエナジーを排除しようと、画策している節があるらしい」
それを聞いて、エリカは目を丸くする。
「そんな事が出来るとは思えませんね……採掘権は国家が保証しています。それを反故にすればどうなるか、まともな経営者なら判る筈です」
こういった話は、単なる金儲けでは済まない。
石油採掘権は国家間の約定を前提とした、まさに国家のプロジェクトとなる事が大半であり、いくら中心的に関わっているからと言って、一企業の都合で好き勝手には出来ない。
日本人としてはあまり馴染の無い話ではあるが、EU連合国のドイツ出身のエリカは、俺なんかよりは意識が高い様だ。何せドイツ自体が、近年エネルギー戦略によって発言力を増してきたロシアから、天然ガスの供給を受けているのだから。それに伴った外交圧力に、EU諸国は晒されていると聞く。
エリカの指摘を聞いて、南教授はさらに厳しい顔をした。
「……ムラサメの動きも妙なんだが、対してグローバルエナジーの方にも不穏な動きがあるらしい」
それを聞いて、エリカは顎に手をやって考え込む。
「……具体的には?」
「ムラサメはどうやらイラク内務省へのリベートを増額しているらしいんだが、最近になって、グローバルエナジーの社外取締役の一人でアメリカ上院議員のロブ・クレイグというヤツが、外交ルートから圧力をかけているとの話なんだよ」
その名を聞いたエリカは何かを納得したのか、手を胸元で叩くように合わせて声を出す。
「ああ、成程。それは充分有り得る話です。ロブ・クレイグはかなりの剛腕で知られていますが、保守派の中でも、特に石油利権に大きく食い込んでいます」
国際情勢の中ではアメリカとEUが衝突する事は度々あるが、そういう事とは違った意味合いで、その人物にはあまりいい印象を持っていないらしい。しかし、そこまで話を聞くと、俺にも別の疑問があった。
「……国同士の話はどうなんだ? 日本政府だって無関係じゃあないだろう」
はっきり言って、日本という国はアメリカの属国みたいなものなのであまり期待はしていないが。何せ首相のすぐ側に、常にアメリカの情報部員が貼り付いているのだから。
「日本は相変わらずさ。しかしムラサメは、官僚共を無視してまで動きを活発化させている。近い内に、ムラサメは出入り禁止になるだろうなあ」
出入り禁止とは要するに、国主導のプロジェクトや公共事業からの締め出しという事だ。石油採掘権交渉において、外務省の担当事務次官の協力が得られなくなると、新規事業の交渉を単独でやらなくてはならなくなる。しかし、それでは国同士の交渉には発展せず、多大な見返りを期待している産油国の要望に応える事は出来ない。
「……ムラサメが、そこまで強引に油田開発を独占しようとするのはどんな理由なのか、そこが問題でしょう」
エリカが導き出した要点に、南教授は額を指で掻くような素振りをしてから答える。
「……これは答えに繋がるかどうか判らんが、ムラサメに買収されていると思わしき連中が、発掘チームの中に潜り込んでいる可能性がある」
「……油田開発と遺跡の発掘に、どんな関係があるんだ?」
教授の説明に、俺は疑問を口にした。しかし南教授は、若干頬を緩めて答える。
「油田のある地域と、遺跡の発掘地点がまさに重なるのさ。油田開発の独占化は、発掘地点の完全な掌握を可能とするだろうさ。何せ警備やら何やら、全て彼らの協力が無くては成り立たなくなるんだ」
そこで話を区切ると、エリカが待ち兼ねたように口を開く。
「ムラサメの狙いは発掘現場と考えて、こちらも行動するべきでしょうね」
それは当然の帰結ではあるが、具体的にどうするのだろう。そんな俺の疑問を感じたのか、エリカは俺を見て笑顔で答える。
「――やはり、現地に行かなくては」
エリカのぶっ飛んだ発言に、皆が絶句した。

急な話だが、俺達はいきなりイラクへと行かなくてはならなくなった。学校はどうするんだとか言いたい事は色々とあったのだが、そこら辺はどういう根回しなのか、既に解決済みであった。
俺とエリカはともかく、他の同行者は南教授とボディガード役のレラカムイ、それにレラカムイの契約者である棗は確定だった。さらに現地での行動を考えてフェニックスとアル、偵察任務に適任との事で戸隠こと仁科三郎も選ばれた。
家で皆が集合し、それぞれの顔合わせをして準備作業。居間で爺さんと一緒に茶を啜っていた叶が、不機嫌そうな顔で皆の準備を眺めていた。
「なんで私だけお留守番なのよう。納得いかな〜い!!」
既に夕飯を食い終わって、料理本を眺めていた御空がケタケタと笑う。
「そんな叶さんを見ていると、当然だな〜って思うなぁ」
俺は庭でライトに照らされたバイクを、フェニックスと共に念入りに点検していた。排気量は250ccだろうか、国産のちょっと古めのオフロードバイクだが、調子は良さそうだ。
「イラクは砂漠の砂嵐で砂が入り込む。砂塵対策は入念にしなくてはならない」
一つ一つチェックをしていくフェニックスの横で、俺はその確認作業を見ている。免許など持っていない俺だが、現地はそんな事はあまり重要では無いらしい。
何故バイクなのかと言えば、エリカやレラカムイは空を飛べるが、俺はそういう訳にいかず、だだっ広いイラクでもし長距離の移動を緊急に強いられた場合には、何か足となるものが必要になるとのフェニックスの判断だった。
中古品らしいがエリカがポケットマネーを出してくれたらしく、どうせ誰も使わないのだからと、イラクから帰ってきても俺が使っていいと言われた。
「……日本に帰ってきたら、免許取りに行こう」
思わず、そんな事を呟いてしまった。
「零二、お友達が尋ねてきてますよ」
そんな時、玄関から婆さんの声が聞こえた。
ちなみに婆さんの名は崎守逸子(いつこ)と言い、今年で65歳になる。控えめな性格であまり表に出たがらないので印象は薄いが、崎守家の台所事情は全て婆さんの腕に掛かっているので、実は陰のフィクサーだったりする。
「判った、今行く」
こんな時間になって来客とは珍しいな、と思いつつ玄関へ行くと、そこには飛鳥が立っていた。
「こら、アンタ携帯切ってるでしょ」
「む、今手が放せなくてな。それでどうしたんだ?」
言われて飛鳥は唸るようにこちらを見る。婆さんは笑顔で奥へと引っ込み、それを見て飛鳥はやっと口を開いた。
「……お婆さんって相変わらず、和服美人だよねえ」
俺は思わず、がくっと膝から崩れそうになった。飛鳥は妹と遊ぶ事があるので、婆さんとも仲良くなってるらしい。
「……で、急用でもあるのか」
「佐伯から聞いた。あたしも行く」
俺は思わず唖然としてしまう。飛鳥の足元に旅行用のトランクを見て、本気だと判る。
龍太郎には、しばらく旅行に行くとしか言っていない。数日前に飛鳥といろいろあったのは事実だが、だからと言っていきなり一緒に戦ってくれとか、そんな事は何一つ言っていないのだ。
「……遊びに行くんじゃないんだ。悪いな」
俺が全く取り合わないような事を言うと、飛鳥は俺の頬を掴んで捻る。
「いてててて!!」
「だからこそ、あたしが必要なんでしょうが」
俺は頬を抑えて飛鳥に反論する。
「日常生活を犠牲にしてまで、お前を巻き込むつもりは無いんだよ」
今まで普通の人間として生活をしていた者を、非日常へと巻き込むのは抵抗がある。普通の生活があるのならば、それをなるべく大事にするべきだ。俺には飛鳥の学校生活を休ませてまで、付き合わせるつもりは無いのだ。
しかし飛鳥の顔からは、諦める気配は全く見られない。
「セイレーンを呼び出した時に判ってたんじゃないの? 動物霊を呼び出して神を誕生させたって事がどういう事か」
「……悪い。よく判ってない」
急に話が変わった為、飛鳥が何を言いたいのかよく判らない。飛鳥は何やら酷くがっかりした様に、肩を落として溜め息を付いた。
「エリカと契約してるのは聞いたけど、あたしの場合は零二が動物霊を認識して神になったから、あんたの認識が切れると現実世界から消えちゃう訳。日本にいるなら兎も角、海外に行ってまであたしを認識出来るの?」
「ああ、そういう事か」
エリカと飛鳥では、俺との関係性に多少の差がある。
『勇者』による認識で定義されたワルキューレは『勇者』の質に左右され、俺とエリカの場合は、俺が『勇者』の条件に合わなくなるとか、或いは契約を一方的に破棄するなどした場合、エリカは現世に留まれなくなる。
対して飛鳥の場合、セイレーンと同化した『九十九鳥の霊』を世界の『死角』において認識を確定した結果、神となった。今まで不確定だった存在を確定させられる存在が、この世にごろごろ存在しているなら兎も角、『九十九鳥の霊』を確定させているのはあくまで俺の認識である為、その認識が不確定となった時点で飛鳥は思念体に戻る。
つまり二人共、過程は違うが俺との関係性が無くなった時点で、エリカはワルハラ、飛鳥はオリンポスという、双方の『神域』にエネルギー体として帰還するのだ。
一度関係が途切れたら、再び存在を確定させるのは難しいだろう。
何故ならば、元々彼女達と俺とでは民族が違うからだ。それぞれの民族の神なのだから、同一民族なら最低でも『同じ民族』という関係性が根っ子として存在する。神は人間達の認識によって存在を確定する為、民族間の共同意識という関係性が一番確実な手段になる。
俺がエリカや飛鳥と関係性を持てたのは、エリカの場合は指輪という触媒があったればこそであるし、飛鳥の場合は『九十九鳥の霊』を呼び出した事による。その関係性が崩れてしまえば、赤の他人になるという事だ。
正確には飛鳥は殆ど日本人だが、あくまでセイレーンは古代ギリシャとアトランティスの神なので、日本人とは無関係だ。
「要するに、あんたの言う日常生活をしたいなら、あんたから目を離せないって訳。だから、出来る限り一緒にいないと。あたしの見てないところであんたに死なれたら、後悔してもしきれない」
「……なんだか、腐れ縁が悪化したみたいだ」
「悪化とか言うな。あたしが一緒だと嫌だって訳?」
そんなやり取りが聞こえたのか、奥からエリカが出てきた。
「あら? 飛鳥さんどうも今晩は。この前の件は聞いています。ロキを倒して貰った事について、お礼を言わせて下さい」
そう言って深々とお辞儀をするエリカを見て、飛鳥は何かを閃いたような明るい顔をした。
「……ん。お礼って事なら、あたしも同行させて貰うわよ」
それはお礼とは言わないだろう、などとは口が裂けても言えなかった。エリカはきょとんとしていたが、特に気にならなかったらしい。
「そうですか。よろしいんじゃないでしょうか」
「……は?」
俺は思わず絶句してしまった。
前々からこいつは天然の気があるとは思っていたが、よく判っていないんじゃないだろうか。しかし、本人は全く気に留めていないらしく、意気揚々とした感じで話を続ける。
「断る理由もありませんし、砂漠ではセイレーンの飛翔能力と索敵能力は有効でしょう。飛鳥さん、よろしくお願いしますね」
なんだか勝手に、話が進んでしまっている。
「おっけおっけ。空はあたしに任せなさい」
昨日の敵は今日の友、とでも言おうか。勝手に結論を出してしまった二人に、俺は儚い抵抗をした。
「……俺は置いてけぼりか」
どうやら置いていかれたのは、飛鳥では無くて俺だった。誰が上手い事云えと、そんな声でも聞こえてきそうだ。

その日の夜、俺達は普通のジャンボジェット機で一般客に混じって日本を発った。途中にインドの空港を経由してからクウェートに到着した頃には、一日半が経過していた。
イラクのバグダッド空港は現在は米軍に接収されており、民間機の離着陸は制限されているらしい。その為、クウェートから陸路でイラク国境を通る必要がある。
日本とは違い、やはり中東は日差しが強く、かなり暑い。
空港で現地スタッフが用意したらしいハマーとか言う大きなジープが二台、それをフェニックスとアルが運転して、バグダッド近郊にあるという遺跡発掘現場へと向かった。アルの運転するハマーに、俺とエリカ、それに飛鳥と南教授も乗っていた。フェニックスの方にはレラカムイと棗、仁科三郎が乗っている。
「アパッチでも用意してくれたら、俺ももっと活躍出来るんだけどなぁ」
そうぼやくアルだったが、米軍では攻撃ヘリに乗っていたと聞いたのを思い出す。前回もそうだったが、自分の見せ場が殆ど無い事に、少なからず不満を持っているらしい。それを聞いたエリカは、やんわりと嗜める。
「そうは言っても、さすがに攻撃ヘリなんて飛ばしたら面倒ですから」
いくら金持ちとは言っても、米軍まで根回しするとなると多大な労力を必要とするだろうし、殆どは通用しないだろう。そもそもドイツ企業のミクロ・ジーメンスに、米軍が協力するなんて事は絶対に無い。では、ドイツ軍なら協力してくれるのかと言うと、そもそもイラクにドイツ軍は駐留していないのでやはり不可能だ。
今回、用意出来たのは車二台だけ、あとは俺に回されたバイクくらいなものだ。
「今回は、あのロブ・クレイグが絡んでるってんだろ? さすがのミクロ・ジーメンスも手を焼く相手だわな」
アルも今回の相手になるかも知れないその人物には、かなりの警戒感を持っているらしい。しかし、そんな話は全く判らない飛鳥は、不思議そうな顔をしている。途中の機内であらかた話は聞いた筈だったが、やはり普通の日本人的な感覚で言えば、アメリカの上院議員がどれ程の影響力を持っているのかは想像が付かないのだ。
「……勢いで付いて来ちゃったけど、何だか話に付いていけないっぽい」
そんな飛鳥に、アルは殊更陽気に笑い掛ける。
「んじゃお嬢さん、俺達はテロ真っ只中の国にいるんだぜ、って言えばどうだい?」
それは飛鳥にとっても、想像の付く範囲の話をしようと言うのだろう。案の定、飛鳥は神であるくせに震え上がった。
「うわ、それならなんとなく。大丈夫なんでしょうね?」
不安げな飛鳥を見て、南教授が口を出す。
「何度か来ているが、ここら辺はまだいい方じゃないか?」
そう言って、教授は外の景色を眺める。
クウェートとイラクの国境地帯からバグダッドに続く真っ直ぐ伸びる幹線道路の横には、ひたすら砂の大地が拡がっている。
夜通し車を走らせて、かなりの距離を稼いだにも関わらず、周囲の景色にあまり変化が感じられない。
途中に何度かガソリンスタンドとかモーテルらしき場所、それから長距離トラックが何台も停まっている空き地に、食い物の屋台みたいな出店が沢山集まったバザールみたいな広場もあったが、殆どは何も無い道が続いていた。目に付く物があるとすれば、破壊された戦車や車の残骸が転がっているくらいだろう。
「どうだろうなぁ。この道路でも、テロは何度も起きてるらしいぜ。まあテロ屋の情報網には俺達は引っ掛かってない筈だから、多分大丈夫だろ。何せこっちも手は打ったからな」
「手を打ったって、何をしたんだ?」
「事前にちょこっと軍を刺激しといた。クレイグがお忍びで来るんで主要幹線道路を封鎖しとけば安全なんじゃねえか、ってな具合でな」
アルの説明は至極あっさりとしていたが、実はかなり大変な話なのではないか。
「……そんな簡単な話じゃないだろ?」
俺の言葉に、アルはニヤリと笑う。
「蛇の道は蛇ってな。軍にいた頃の直属の上官に垂れ込んだだけよ。あいつらも点数稼ぎしたいだろうし」
アルの説明に、南教授が関心した様に口を開く。
「成程なあ。軍の活発な動きに刺激されたテログループは、そっちへ狙いを定めるって訳か」
「そういう事。ついでにドバイの武器密輸ブローカーを通じて、テロ屋にも情報は流したけどな」
「……なかなか策士だな」
軍を動かし、テログループもそれに乗っかる。
アルは活躍出来なくて不満だと言うが、なかなかどうして、根回しの方面では大活躍している。エリカもその話に付け足すような説明を加える。
「それだけでは無く、緊急のお忍びで来た筈のクレイグはかなり動きが制限されます。最悪、彼がテロの標的となりますし。問題があるとすれば、未だ動きが予測出来ないムラサメ商事でしょうね」
「だから、それを調べに来たんだろ? ムラサメは日本企業のクセに情報管理が徹底してやがる。トップは相当やり手だぜ」
アルの言葉に俺はなんとなく、言っている意味合いを理解した。おそらくムラサメ商事に対しても、かなり以前から情報収集を行っていた筈だ。だが今までの所、具体的な成果は上がっていないと言いたいのだろう。
「きっとクレイグも、ムラサメの件でこちらに来るのでしょう。彼の立場ならばエシュロンによる情報が上がってきている筈ですが、ムラサメのガードが堅い。中々情報が上がってこないので痺れを切らした、そんな所では無いかと」
エシュロンとは、アメリカやイギリス、オーストラリアやカナダなどの英語圏の国に導入されているとされる、電子諜報システムの事だ。電話から電子メールまで、ネットワークに繋がる全ての情報網から特定のキーワードを抽出するシステムだとか。このシステムを主導するアメリカにおいては、アメリカ国防総省(ペンタゴン)やアメリカ中央情報局(CIA)のみならず、その情報が必要であるとされた関係各局に情報が引き渡される。場合によっては政府に関係の深い企業にまで引き渡され、経済市場においても他国より有利な立場を得られる。
公式にはその存在は認められていないようだが、己の虎の子を易々と露呈する筈が無いだろう。
「おっと、そろそろ到着だぜ」
アルの言葉に前方を見れば、どうやら油田開発地区への入り口へと来たと判る。鉄条網に覆われた検問所のゲートに、軍の警備が確認出来る。
徐行運転で検問所の前まで来ると、アサルトライフルで武装したイラク軍の兵士にアルが書類を見せる。俺達は教授の伝手で発掘関係者となっているので、あっさりと通行許可が下りた。
「ここの警備はイラク軍なのか」
「テロの標的としては、イラク人よりアメリカ人が優先だろうって判断だろうな。尤も、実際はイラク人だって危ないんだけどな」
俺の一言にアルがそう受け答え、車を走らせる。
中に入るとまず目に付くのは、油田のパイプラインと製油施設らしき大きな設備だった。どうやら中の大半は油田開発の現場で、肝心の発掘現場はもっと中にあるらしい。
何事も無く、中心に向かって車は走る。しばらくしてアルが車を停めると、そこは小高い丘の手前だった。二台の車から全員が降り、丘を見上げる。どうやら今まで寝ていたらしい棗が、軽く伸びをした。
「ん〜、なんか空気がざりざりする〜」
大気中に混じる、砂の感触に慣れないのだろう。時折吹き込む風は確かに黄土色の霧のようで、遠方の視界はあまり良くは無い。女性陣はイスラム女性の慣習に習って、ショールの様な布地を頭から引っ掛けているので多少は砂を防げる。
南教授が近くで作業をしていた現地スタッフに声を掛けると、しばらくして日本人の男が丘の上から降りてきた。
「お久しぶりです教授! いきなりなんでびっくりしましたよ」
「おう、種田クン。元気そうだな」
どうやら教授の知り合いらしいが、おそらくは片腕的な存在なのだろう。その後、皆の自己紹介を済ませて男の素性が判明する。
教授の下で発掘現場を取り仕切っている助教授で、名前は種田安良(やすよし)氏。
最近は油田開発の権益で不穏な空気があり、現地の体制が何度も変更になるなど、作業が中断する事が頻繁に起こっているらしく、教授はそれも含めて関係各所を奔走していた為に、現場から離れていたらしい。
「相変わらず、ムラサメ側の責任者とグローバルエナジー側の責任者とで意見が割れましてねえ。どうしても、ダブルスタンダードに成らざるを得ない状態です」
種田助教授のボヤキに、南教授は苦笑いする。
「その責任者とは、以前と同じかね?」
「いえ、何度も人事異動がありまして。どっちも名前と顔を覚えるだけでも大変ですよ」
どうやら両者の食い違いが原因で、現場は大変混乱しているらしい。南教授は種田助教授を安心させるつもりなのか、俺達を見ながら説明する。
「こちらも個人的な伝手で、新たなスタッフを何とか食い込ませる事に成功したところだ。これから状況は良くなると思いたいがね」
教授の説明に、助教授は改めて俺達の顔を見回す。
「中には随分と若いスタッフも見受けられますが……まあ教授の伝手なら、何か技能を持っているのでしょう。それよりも一度、丘を見てみますか? 以前からあまり作業は進んでいませんが……」
「お願いしようか」
助教授の案内で、俺達は丘の上に登った。傾斜はそれ程きつくはないが、それなりの高さがあるので、上に登るまで多少の時間が掛かった。
「……は〜、こりゃまた大きいねぇ」
目の前の開けた視界に、飛鳥が感嘆の声を上げる。
何十人もの現地スタッフが作業するその現場は、差し渡し10キロはあろうかという広大な規模であった。すり鉢状の中心地点から拡がる基礎部分らしき石垣が、放射状に拡がっている。
「……これは、何かの土台に見えなくもないな」
俺の漏らした感想に、教授は感心したように頷く。
「その通りだ。ここには巨大な円筒状の構造物があったと考えられる。キミらと出会って色々と話を聞いたのが参考になるが、おそらくはワルハラ、オリンポスと同じく、ここで神域となる時空間コロニーを打ち上げたのだろう」
旧約聖書の記述によれば、思い上がった人間が神の住まう天上を目指して、天高くそびえ立つ塔を建てたとされる。しかし、それに危機感を抱いた神は、人間が皆、共通の言語を喋っているのが原因だとして塔を破壊し、種族ごとに言語をバラバラにしたのだと。
アスタロスとの会話で知った内容を併せて考えるに、ネットワーク中枢システムであるバベルの塔が天使達に接収されているらしく、現在は機能していないらしい。それが為に、各地の神域を結ぶネットワークが寸断され、外敵の侵略に対して連携が取れなかった為に、今の衰退があるのだと言う。
棗に貰った菓子を頬張っていたレラカムイが、教授の話を聞いて口を開く。
「現在に伝わっている話ってのは、神代の出来事が断片的に口伝で伝わって、それが当時の文明と同時期の話だと勘違いされているんだよな。言っておくが、シュメール・アッカドの時代よりも、さらに古代の構造物なんだぜ」
その話を教授は特に驚く訳でも無く、静かに聞いている。しかし、案内役の種田助教授は二人の突拍子も無い話に、唖然としていた。
「……教授、一体何の話ですかそれは。そんな学説、今まで聞いた事も無い。いつの間に宗旨替えしたんですか」
彼の言い分は無理も無い事だった。現地で遺跡の発掘に従事しており、年代的な立証など既に済ませている筈だろう。教授はそんな種田氏を諌めるように、手で制した。
「…… 確かに遺跡の年代から、今の話は嘘っぱちにしか聞こえんだろう。だが、目に見えるものが全てだとは限らんよ。例えば、欧州では古代の遺跡を教会が封印していたと聞く。それとは違うだろうが、当時の人がさらなる古代の超文明の痕跡に自分達も倣い、当時の技術による再現を試みた可能性だってあるんじゃないかね」
教授の説明を聞き、種田氏は考え込むような仕草で黙り込んだ。
今の説明はいくらか暴論ではあるが、だからと言って反論も出来ない。種田氏は知らないから仕方がないが、俺としてはすぐ横にエリカがいてレラカムイがいて、さらにセイレーンである飛鳥までいては納得せざるを得ないのだ。
さらに、時代の生き証人とも言えるレラカムイの講釈が続く。
「そもそもメソポタミアってのは、地中海とインド方面、両方から来た連中が合流して出来たんだ。んで、東南アジアには環太平洋文明が存在していた。本当の意味での第一次文明の発祥は、東南アジアと地中海だったんだぜ」
第一世代の神であるレラカムイの話なのだから、それが真実なのだろう。
聞けば第一世代が環太平洋文明、つまり現在はムー文明なのでは無いかと言われているのだが、実際には、まだ日本列島まで人間が分布していない頃の東南アジアで興った文明が発祥だと言う。環太平洋文明と同時期には大西洋にてアトランティス文明が興り、これら二大文明が人類最初の文明との事だ。しかし、その文明は地震と大津波によって海中に没し、逃げ延びた者達もいれば、テクノロジーを駆使して己の存在を神へと昇華した者とに別れた。
それが第一世代の神。
オリエント文明の信仰した神々は第二世代であり、それらの神々は環太平洋文明とアトランティスよりもたらされた技術を継承したオリエントの始祖だそうだ。さらに文化は拡がり、ユダヤにゲルマン、ケルトやスラブ、日本の神道などの神々は第三世代となる。
しかし種田氏は、レラカムイの話を本気にしてはいないだろう。彼から見ればレラカムイはちょっと顔立ちが濃いので日本人か東南アジア系か判断が難しいくらいで、基本的には普通の人間にしか見えない。
「……まあ何と言うか、私には何とも言えませんが。一つ忠告するならば、今の話はここだけの話にしておいた方がいいと思いますよ」
さすがに上司に逆らう訳にもいかず、無難な受け答えを選んだらしい。
俺達がそんな話をしていた一方で、エリカや飛鳥、それに棗の女性陣は現地スタッフの発掘作業を近くで拝見し、フェニックスとアル、仁科三郎の三人は警備の状態を確認して歩いている。どうやら状況の把握と謎解きは俺とレラカムイ、南教授の三人でやってくれという事らしい。
南教授は種田氏の意見に頷きながら、発掘現場の方にいる女性陣三人組を見て口を開く。
「種田クンは彼女達を案内してやってくれ。こっちは私一人でいいから」
「判りました。では、夜になったら酒でも呑みましょう」
種田氏がエリカ達の側に歩いていくのを見て、俺達は今後の方針を固める為に意見調整を始める。まずは、俺達の目的を再確認しなくては始まらない。
「アスタロスとその契約者が教授の記憶から何を引き出したのか判らないが、バベルの塔を掌握して、ネットワーク管理神として再び君臨しようと考えている事は判明している。対して現実世界では、ムラサメ商事とグローバルエナジー社による石油利権の主導権争いの様相に発展しており、発掘作業が難航している」
俺の口から、現状の説明をする。
今更言わなくても判っているのだが、改めて口にする事で、何か気付くかも知れないからだ。
そこでレラカムイが何か気付いたらしく、手を上げて発言する。
「そのムラサメとグローバルなんとかってのは、本当に石油利権だけが目的なのか?」
それは的を射た疑問だった。
実は俺も、その点に何かあるのでは無いかと考えていたからだ。
「偶然にしては出来過ぎているとは思う。たまたま遺跡の発掘現場と同じ場所だった、とするのは苦しいな」
対して、南教授も何か思う所があるようで手を上げる。
「今までの日本の油田開発では、他国を出し抜こうとしても必ず横槍が入った。例えば、サハリン沖の海上プラントにしても当初は日本単独で開発を始めた筈だったんだが、最後にはメジャーが食い込んでいたのさ」
その話は有名で、エネルギー資源の確保の難しさを如実に語る逸話であった。ちなみにメジャーとは別に大リーグの事では無く、国際石油資本の事である。俗に四大メジャーなどと呼ばれているが、その四つとはアメリカ資本のエクソン・モービルとシェブロン、イギリス資本のBP、そしてイギリスとオランダ共同資本のロイヤル・ダッチ・シェルの事である。日本でもモービルとシェルは有名なので知っている者は多いだろうし、車好きな者ならBPも知ってるだろう。
そこに最近、急激に勢力を伸ばしているのがグローバル・エナジーで、こちらは元々は原発開発が本業であったが、さらに火力発電や水力・風力発電なども大々的に手掛け、油田開発では日本のムラサメ商事と組む事で新規開発で躍進したのだ。現在ではこのグローバル・エナジーを入れて、五大メジャーと言われ始めているらしい。
話は戻って件のサハリンプロジェクトの内の一つ、サハリン1は開発当初は日本と旧ソ連だけで開発が進められていたが、途中からアメリカによる横槍が入り、結局はエクソン・モービルの子会社が食い込んできたのだった。もう一つのサハリン2においては途中参加では無いが、やはりロイヤル・ダッチ・シェルが権益の半分を有している。もしもサハリン1でアメリカの横槍を阻止出来ていたら、サハリン2でメジャーに食い込まれる事を阻止出来たかも知れない。
一般の日本人に国家における最重要戦略は何かと質問をした場合、おそらくは軍事か平和外交、もしくは環境問題と答えるだろう。しかし、本当に重要な戦略とはエネルギー戦略に他ならない。何故なら、エネルギーが無くては軍隊は動かないし、企業活動だろうと個人生活だろうと、全てが動かないからだ。
俺個人の考えで言えば、エネルギー戦略と環境問題は同列だが、経済優先の風潮ではそうはなっていない。
ちなみに、日本のエネルギー戦略は100%日本権益による油田開発を確保する事だが、今までのところ99%は負け戦である。数少ない勝ち戦はアラビア石油という日本企業による、サウジアラビアとクウェートとの交渉で手に入れたカフジ油田が有名だ。しかしこれも、40年の利権協定が失効し、採掘権延長の交渉も失敗、代わりに中国に権益を分捕られる始末。
とは言え、地球環境を考えるなら化石燃料からの脱却と、クリーンエネルギーへの転換を早期に実現するべきなので、あまり悲観する事は無いのかも知れない。
「それが今回は対等にやりあっているんだな……どうしてだろう?」
俺の疑問に答えられる者はこの場にいる筈も無く、教授もレラカムイも考え込んで黙ってしまう。結局は、そこら辺がこの謎を解く鍵になるのかも知れない。
「……やはり、そこを調査しなくちゃならないんだろうな。フェニックス! ちょっと来てくれ!!」
俺は調査の方針を決める為に、調査責任者であるフェニックスを呼んだ。アルと仁科三郎に何かを説明しながら周辺を観察していたフェニックスだったが、俺の呼び声を聞いて三人一緒にこっちへ来た。
「ムラサメとグローバルエナジーの背後関係を調査して欲しいんだ」
それを聞いたフェニックスは、顎に手をやりながら仁科三郎の顔を見る。
「サブロウ、キミはムラサメを洗ってくれ」
「了解しました」
フェニックスの簡単な指示を聞いた仁科三郎は、いきなり何処かへと走っていった。
「……あんなんで大丈夫なのか?」
レラカムイが顔をしかめてフェニックスに尋ねる。
「大方の見当は付いていたからな。サブロウがムラサメに潜入する算段は付けてあるのさ」
「じゃあアンタはグローバルエナジーの方か」
俺が問い返すとアルが答える。
「いんや、俺がやるよ? フェニックスの旦那は以外に有名人なんでね。サブロウみたいな隠密行動は無理だが、グローバルエナジーの社員に伝手があるんで探りを入れてみるわ」
アルはどうやら顔が広いようで、彼の持つコネクションを利用するらしい。
アルは片手を上げて、飄々と去って行った。残ったフェニックスは、南教授の顔を見て口を開く。
「もしも連中の狙いが石油利権だけの話では無く、遺跡自体が目的だとするならば、貴方を狙うかも知れない。レラカムイが護衛しているとは言え、備えを怠る訳にもいかないだろう」
どうやらフェニックスは、教授の身辺警護について何らかの処置が必要だと判断しているらしい。それを担当しようと言っているのだ。
「既にアスタロスが教授を拉致ってるんだけどな。もしどちらかに繋がっているとして、今更教授が必要なのか?」
しかし、フェニックスは首を振って否定した。
「仮に関係があるとしてもだ。ムラサメとグローバルエナジーは競合関係なのだから、どちらか一方の陣営は、教授から情報を得ていないのではないか?そう考えると、私の危惧も行き過ぎでは無いだろう」
フェニックスの危惧とは何だろうか、とも一瞬思ったものの、今までの会話で俺にも少しばかり裏が見えてきた。
「もしかしてロブ・クレイグがイラクに入るのも、何か関係しているのかな」
フェニックスは珍しく、ニヤリと笑みを浮かべた。


第六話・魔神騒乱