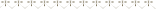Sick City
第四章・霊地祭壇
エリカによって炎は消され、俺の怪我も治癒されていた。結局はエリカに消耗を強いる事にはなったが、それでも直接戦うよりはマシだった筈だ。気絶した忍者男は、本人が使った釣り針をエリカが黒装束に巻き付けて拘束していた。
「さて、これからどうしたものでしょうか。連絡を取るべきでしょうか」
一通りの作業を終えて、エリカがそんな事を言ってくる。俺は少しばかり考えを巡らせ、方針を確認する。
「いや、ここまで来たら、このままで中に突入した方がいいな」
社の裏手に潜伏している筈のフェニックスとは、顔を合わせようと思えばすぐに出来るが、せっかく潜伏しているのを、どこにいるとも判らない敵の姿を確認せずに晒す訳にはいかない。
当然、無線連絡も危険だと考えるべきだ。
「しかし、この神社に気配を殺して隠れているとしても、仲間が倒されるのを前に何も手を打ってこなかったのは不自然ですね」
エリカの言い分は尤もな意見ではあったが、必ずしも中にいるとは限らない。それどころか神社はただのダミーだと、今では理解出来る。
「中にはいるんだろう。近くにいないだけで」
俺の言い方が悪かったのか、エリカはきょとんとした表情で、一瞬何と答えるべきか迷ってしまった様だ。
「……近くにいない?」
「まあ、中を見てみれば判るだろう」
俺はそれだけを言って、無防備に神社の扉を開いた。慌てて俺の側にまで駆け寄ってくるエリカ。それを待ってから中に踏み込み、事前に用意していたペンライトで中を探る。
「これだな」
俺はこじんまりとした八畳間程の広さの部屋の奥に、場違いなものを発見した。鉄の枠で仕切られた、箱形の空間。
「これは……エレベーター?」
その余りの唐突さに、エリカは息を呑む。工事現場にでもありそうな、ケーブルやモーターが剥き出しになった武骨な機械。
「こんなもんがあるって事は、この神社の真下に空間が拡がっているって事だろうな」
富士山の周辺には鍾乳洞などが点在しており、この神社もそういったものの一つを信仰の対象にしている上に、その存在を隠蔽していると考えられる。
「では叶さん達は、この下にいる訳ですか」
「だろうな……行くぞ」
俺は鉄の閂を開けて中に入る。
エリカが入るとそれだけで一杯一杯になってしまう程の狭さ。
脇を見ると昇降用の操作盤があり、緑と赤のボタンが目を引いた。縦に並んだ二つのボタンの内の一つ、下の赤いボタンを押すと、がたんと音を立ててエレベーターが作動した。低いモーター音を鳴らしながら、ゆっくりと降下していくエレベーター。エレベーターは縦穴の壁面に沿って据え付けられたものであり、壁面は水で長年の間に渡って丸く削られた、光沢のある鍾乳石で出来ていた。
一定間隔で備えられた光源によって多少は視界が確保されてはいるものの、降下するにつれて段々と空間は拡がりを見せる。30メートルも降りたところでエレベーターが停止し、剥き出しの岩肌に接地したと知る。
俺達はエレベーターを降りて、辺りを見回した。
「……ここで話をしたら、声が反響して目立ってしまいますね」
そう呟いたエリカの声が反響して、ことさら大きく聞こえてしまう。まだ敵と遭遇していない段階で、声を出すのは止めておいた方がいいだろう。
俺は声を出さずに頷きで以て返し、索敵に集中する。
『心眼』による探知でそのまま前に進み、道らしき空間が存在する事が判る。何も言わずにその空間に進むと、エリカも黙って後を付いてくる。その道らしき空間は高さが約五メートル、幅は三メートル程で僅かに風の流れを感じられた。風を感じると言う事は、この先に地上と繋がる空洞があるという事だ。
灯の無い空洞を、ペンライトの灯を頼りに歩いて進む。とは言っても俺は『心眼』があるので暗闇でも平気だし、エリカも自分の能力として、スターライトスコープと同等の暗視能力があるらしいので大丈夫だろう。
スターライトスコープとはその名の通り、星の明かり程度の明度があれば通常レベルの視力を確保出来ると言われる、軍事用の暗視装置の事だ。ペンライトを点けているのはエリカの暗視能力を発揮させる為で、何の明かりも無い状態ではスターライトスコープと言えども、その能力を発揮出来ないと聞いた事があるからだ。
途中いくつかの分岐点があって横穴がいくつも存在したが、風の流れを感じる道だけを選んで突き進む。
やがて『心眼』の感覚領域に、人の気配を感知する。
先に拡がる大空間、そこに四人の人間がいる。
俺の意志を僅かに反映し、エリカにも何かあるのだと予感を与える。
先を進むと、前方に明かりが見えてきた。俺はペンライトを消して懐にしまい、調息しながら足音を殺してゆっくりと歩く。
やがて辿り着いた場所を視界一杯に収め、鍾乳洞の大空間の真ん中に、一段高くなった祭壇のような形の石段が見えた。上を見上げれば、ぽっかりと開いた開口部から夜空が見え、清涼な空気が入り込んでいる事が判る。
縄で張られた形だけの結界の中、四人の人間が見える。
若い女と少女、ずんぐりとした体形でスーツ姿の髭面の中年男、そして杖を手にし、着物姿の下にステテコを穿いて頭にハンチング帽という、まるで明治か大正時代のような格好をした老人。
その四人が、祭壇の真ん中に置いてある何かを囲んでいた。
四人の中でこちらを向いていた老人が、俺とエリカに気付いて「ほう」と感嘆の声を漏らす。それを聞いてこちらを振り返った叶が、驚きに目を見開いた。
「あらら。仁科くん、やられちゃったみたいね」
それを聞いた棗が、不満げな顔をする。
「え〜! 戸隠負けちゃったのかぁ。不甲斐ないな〜」
次いで老人が、朗らかに笑いながら中年男に声を掛ける。
「おっほっほ――さて教授、彼らはあんたを追ってここまで来た訳だが、何か言ってあげた方がいいんじゃないかね」
教授と呼ばれた髭面の中年男は、頭を掻きながらも申し訳なさそうな顔でこちらを見やった。
「いやね、私はかどわかされた訳では無いんだわ。わはは」
どうやら無事な様で安心はしたが、新たな疑問にエリカが訝しげな顔をする。
「では御自身の意志で、彼らに協力をしていると?」
問い詰めるような口調で迫られ、当の教授は苦笑いのまま受け答える。
「その通り。シュタインメッツさんとの約束を忘れた訳じゃないが、彼女達の用件も非常に興味があったんでね。この壺を見てくれたまえ」
そうして教授の指し示した先には、祭壇の真ん中に鎮座した、縄文土器のような焼き物の壺があった。縄目の紋様が施された赤茶けた壺は、蓋のようなものが被さっており、その境目には何枚もの紙によって封印が施されていた。
「何ですか、その壺。それがこちらの用件を差し置いても、優先する程のものなのですか?」
趣味が日本、とまで言い切るエリカだが、さすがに縄文時代の土器までは判らないらしい。教授はどうしたものかと老人を伺うが、老人が僅かに頷いたので話の先を進める。
「五行会とは修験道の復興を目指しているらしいのだが、忍者に伝わる忍術とやらは修験道がルーツにあるらしい」
いきなり修験道と忍者の関わりを説明され、俺もエリカも訳が判らなかった。
「……忍者は大好物です」
しかしエリカは興味があるらしく、若干、天然気味な事を口走っていた。
「しかし修験道は神道、陰陽道、密教などをミックスした信仰だ。神道とは弥生人がルーツ。それが縄文土器と関係があると誰も思わなかった」
教授の言う通り、日本は先に縄文人が先住していた所に九州・百済系の弥生人が稲作の技術と共に流入してきた。弥生人がルーツの神道ではあるが、日本の文化が縄文と弥生のミックスであるのと同じで、若干は縄文の伝承も加味されていると言われている。
それでも支配者となった弥生人側の都合の良い解釈が前提となっている筈であり、神道ベースと言われる修験道に、縄文土器が絡む要素が何処にあるのかと疑問を持ってしまう。
「しかし……修験道は山岳信仰でもある。実は山岳信仰は縄文の信仰であり、地方豪族の土着の縄文系の一族が、神道を隠れ蓑としてかつての縄文信仰を受け継いだのが、修験道のベースにあると言える。忍者のルーツも武士と同じく、地方豪族なのさ」
それで話は繋がる。
徐々に衰退していったのは、修験道だけでは無い。戦国の世が終わり、太平の世となった頃から、忍者もまた衰退していったのだ。そう考えると、忍者=修験者の図式が成り立つ。
「さて、この土器だが。我ら日本人の中に存在する縄文系の信仰のルーツとは、一体何だろうと思わないかね?」
しかし、そんな話をされても、外国人であるエリカには理解の範囲を超える。返答に困ったエリカが俺の顔を見たので、代わりに俺が引き継ぐ。
「……あれか、アラハバキだとか邪馬台国とか、今ならアイヌとかそういうのか?」
俺も詳しい事は知らないが、アラハバキ一族と言うのが大昔にいて、その一族や卑弥呼が収めた邪馬台国とかも、大きく括れば土着の縄文人と言えるらしい。アイヌ人にしても先住民族であり、やはり縄文人との交流くらいはあった筈で、もしかしたら信仰されてる神に一部共通点があったかも知れない。
「そうだね。断片的だが、そういう形で逸話くらいは残っている。しかし、その実体は未だに謎に包まれている。話は変わって、アラジンの魔法のランプって話は知っているだろう?」
いきなり話が変わり、なんでアラビア圏の話が出てくるのか。そんな俺達の疑問に、教授は得意げな顔で、まるで教え子に講義を聞かせているかのように語る。
「ジンと呼ばれる魔神が、三つの願い事を叶えてくれると言うが、アラジンが騙して富を得る。だがアラブは今やイスラム教、どうしてそんな別種の神が伝承として残っているんだろうか」
言われてみれば少々おかしい。
しかしイスラム教以前にも別の信仰の対象はあった筈で、それが部分的に残った結果なのでは、とも思う。一説によれば、ジンという魔神は、実は天使がモデルであるとも言われている。
「さて、シルクロードと呼ばれる交易の道が、地中海沿岸と中国の間にはあったと言う」
――今度はシルクロードときたか。
「我ら縄文系は環太平洋文化圏、その大元は東南アジアに。そしてアラブの魔神のルーツは天使だと言われているが、そのモデルは……今では僅かにアイヌに伝わるだけの縄文の風の神、そうだ! 雷神と風神の、風神がその正体だ!!」
随分と大きく出たな、と思う。
しかし、ミノタウロスが中国で牛魔王として伝えられている事もシルクロードがあったからとも考えられるし、教授の仮説を否定する事は出来ない。よくよく考えてみれば、現代に伝わる神の内、正確な名称や背景が全く判らないものがある。それらが何故、今では廃れてしまったのかと言えば、それは元となった文化の衰退でもある筈だ。
「この土器は、彼女達が私の研究室に持ってきたものだが、これこそは山岳信仰の名残。燃え盛る炎が山を赤く染め、上昇気流が風を巻き起こし、雨を呼ぶ。その恵みは人と大地へ……この縄目に込められたメッセージには、特に風が強調されている」
そう締め括った教授の顔が、叶に向く。叶は中央に置かれた土器に、両手を突き出してから口を開いた。
「何故、この土器がアラジンの魔法のランプへと変容して伝承されたのか、そんな疑問はどうでもいい。判っているのは、異界から神を呼び出す為の触媒だって事なのよ」
叶に続き、棗も両手を突き出して念を込める。それを見て、エリカが声を張り上げた。
「――ッ! いけない! 神を呼び出せば代償を払わされます!!」
しかし、エリカの忠告は無駄に終わる。
二人の込めた念に土器は震え、紙で出来た封印が弾け飛んで、周囲に風が巻き起こる。荒れ狂う風の中、両手で顔を庇いつつも、教授が嬉々とした声で叫ぶ。
「この富士に穿たれた縦坑こそ、太古から脈々と受け継がれてきた祭壇! そして祭壇にて触媒を用い、『神降ろし』の儀式と成す!!」
土器の蓋が弾け飛び、周囲の風が中へと吸い込まれていく。強大なエネルギーが土器の内側より溢れ、渦を巻きながら中空で一つの形を生み出す。今や暴風となった風圧に押され、俺とエリカは身動きが封じられてしまった。
『――我が風を呼び出したのは、誰ぞ』
そんな声が、何処からか聞こえてくる。野太い男の声に、教授は感嘆の声を上げる。
「……本当に神が現れたのか? ……信じられん」
叶も同じ感想を抱いたらしく、呆然とした表情をしていた。
「は〜、ここまで頑張ってきたけど、夢見てるんじゃないよねぇ」
そんな中で、棗だけは意外に冷静だった。
「お〜、出た出た。えっとどうしよ? お腹空いてない?」
しかし本人にも状況がよく判っていないのか、唐突に場違いな事を言って、懐から棒菓子の包みを取り出す。子供の発想なのか、菓子で気を引こうとでもいうのだろうか。神ともあろう存在がそんな事に構うとは思えない、などと考えるのは間違いだった。
『――しばし待て――基底現実へ認識固定――仮契約により限定解除――』
突然、風が止んだ。
中空より降り立つ、強大な存在。
見れば何かの民族衣装の様な、腰巻きに簡素なズボン、サンダルを履いた半裸姿の年若い男であった。四方に逆立った茶色の髪と、額に巻かれた帯のような布、蒼い染料で全身を彩る刺青が印象的だった。確か刺青は『彫る』もので、『描く』ものは『文身(ぶんしん)』と呼ぶんだったか。
圧倒的なエネルギーを保有するその男は、おもむろに棗の手から棒菓子をもぎ取った。しかし首を捻った後、包装紙に包まれたそれを空にかざして動きを止める。
「……ふんッ!!」
妙に力の入った声を張り上げ、両手を拡げると包装紙が四散し、落下してきた棒菓子を器用に口で受け止めた。さくさくと擬音が聞こえてきそうな素振りで棒菓子を食べ終え、眼を閉じたかと思うとぼそっと呟く。
「……これは、一体何だ」
何か思う所でもあるのか、これが神だとは思えない様な、感慨深げな顔で棗を見る。
「あ、大昔の神様だもんね。うみゃー棒明太おたふくソース味食べたの初めてなんだ」
明太おたふくソース味とは一体、どんな味なんだろう。しかも『うみゃー』って、名古屋かよ。明太子が博多名物で、おたふくソースは大阪、それで『うみゃー』が名古屋とは、いくら何でもツッコミ所が多すぎるだろ、と思ってしまった。
一人納得して、うんうんと頷く棗。男の方も棗に同調しているのか、同じ様にうんうん頷いている。
「この様な珍味と出会えるとは……いいだろう。お前の望みを言ってみろ」
「……珍味なのかよ」
男の感想に、思わずツッコミを入れてしまう俺。妙に人間臭い神だな、などと眺めていると、棗はにんまりと笑顔を浮かべて言い放った。
「よく判んないけど、うみゃー棒一本で一回、言うこと聞いて」
かなりアバウトな願いだった。
そんな具体性に欠ける物言いでいいのかと思ったが、意外な事に、神はすぐさま頷いていた。
「いいだろう。妥当な契約内容だと思うぞ、うむ」
それを傍目で眺めて、俺は呟いていた。
「……随分と安い神だな」
「そ、そうですね」
エリカも引き攣った笑みを浮かべて同意した。
「……実は私も、殆ど中身の無い契約をした、一番安い神だなんて今更言えない」
横でぼそぼそと何かをエリカが呟いていたが、俺の耳には届かなかった。
「それで、今の一本で何を願う?」
早速の要求を出した神に対し、棗は難しい顔をしていた。
「……う〜ん、願い事の前に名前を教えてよ」
しかし、神も難しい顔で頭を捻る。
「う〜む。実は、名前は忘れてしまったのだ」
「は? 名無しさん?」
「名無しと言うか、かつてあった筈の名前は、今はもう人間に忘れられて久しいので意味を持たないのだ。神にとっての名前とは、情報体として世界に存在を確定する為の重要な要素なのだ。それを無くした時点で眠りに付いた訳だ。現在伝わる神話ではアイヌが一番近い。風神のレラカムイと呼んでもらいたい」
風神レラカムイ。
それはアイヌ民族に伝わる神話において、自然信仰を擬人化したかのような曖昧な神格であった。だが、その曖昧な伝承は情報の正確さに欠くとかの原因では無く、本人の性格がかなり大雑把なせいなのでは無いか、と思ってしまった。一方の棗も、難しい事は考えないタイプの様で、至極あっさりとその申し出を受ける。
「うん、じゃあレラっち。あそこの金髪女も神様でと〜っても邪魔だから、追い返しちゃって」
棗はいきなり、妙なあだ名で呼んでいる。レラカムイと呼ばれた風神が、初めてエリカを見る。
「ほう。これはまた若い世代の神だな。見た事の無い一族の様だが、北磁極の光の戦神といったところか? 何にせよ、頼まれたからにはやるだけだ」
横目で一瞬見ただけで、何処のどういった神なのか看破する辺り、相応の力の持ち主だと思える。それはエリカも感じたのか、途端に緊迫した声で俺に語りかけてくる。
「……避けられそうにありませんね――レイジさん!!」
それは転身への合図。
俺はエリカの求めに応じて、指輪に込められたプログラムを起動させる。光に包まれて神の姿へと転身したエリカは、その本当の姿を風神の前にさらけ出した。そんなエリカを見て、教授はまたも驚きの顔でわなわなと震えていた。
「……おお、なんと」
本人の理解の範疇を大きく超える事態に、教授はただひたすら驚いていた。
「神は現れたか……後は若いもんに任せて、年寄りは退散するとしようか」
老人はそう教授に声を掛け、二人は俺達が入ってきた通路の奥へと歩いて去っていった。しかし教授は興味が尽きないらしく、通路の隅っこに座り込んだ。正体が掴めない不思議な老人だったが、今はそんな事に気を取られている場合では無いと判断した。
俺はまず、現時点の戦力分析を試みていた。
今までエネルギーを温存してはいたが、今のエリカの保有エネルギーはだいたい500万前後。対する風神は、エリカのフルパワーと同じ3000万程度と見られる。間違いなく、今まで対決してきた神の中でもアスタロス級の強敵。
今のエリカでは、かなり分が悪い。
完全な状態でやっと五分五分、アスタロス戦ではヒルデブラントを中心に、エリカと俺の援護で何とか勝てた訳で、今回はヒルデブラントがいないので相当な不利を覚悟しなくてはならない。ヒルデブラントについてはドイツの総合電機メーカー、ミクロ・ジーメンスのCEO、フリッツ・シュタインメッツとして、どうしても外せない仕事が入っているとの事で今回は参加出来ないとの事だった。
普通の生活に価値を感じる俺達は、人間としての生活を大事にしようと決めている。なので、ヒルデブラントの事情に口を挟む事は出来ない。だからこそフェニックスとアルが借り出されているのだし、俺達だけで何とか対処しなくてはならない。
そんな事を考えていたら丁度都合よく、上空の開口部の淵にフェニックスの気配を感じた。どうやら本人としては状況はよく判らないが、エリカと対峙する風神が危険な敵だと考えて、持参していたライフルで狙撃体勢を取っているようだ。
しかし風神がまだこちらを攻撃していないので、とりあえず狙撃ポイントを確保しただけに留めているらしい。神を相手に銃弾など無意味ではあるが、使うべきタイミングを間違わなければ、効果的な牽制くらいにはなる。
フェニックスとアルには、事前に俺達が神と闘っている事を説明してあるらしく、神と呼ばれる存在がどれだけの能力を持っているのかも説明済みだろう。目の前の風神が神だと理解しているのならば、不用意な攻撃は控えるだろうし、フェニックスにはその判断力があると俺は見ている。
しかし、俺達の思惑はどうやら筒抜けらしい。
「上に人間が潜んでいるな……そこのお前、何もするんじゃないぞ!!」
「!?」
縦穴の上を見上げたレラカムイが突如、大声を上げる。それを聞いたフェニックスが、硬直したのを俺は感じた。
「――ユプケ・アシ!!」
レラカムイが声を張り上げると、同時にその周囲に暴風が巻き起こり、まるで身体を包み込むかの様に風圧の壁となる。さらに、何処からともなく出現した細長い帯のようなものが、両腕の周りを僅かな隙間を空けて巻き付き、くるくると回転している。僅かに空中に浮いたかと思うと、身体を前傾姿勢にして気合いの入った咆哮を上げる。
「おおおおおおおおおッ!!」
途端、弾かれたかの様にして突撃、数秒遅れて爆音が轟く。
「リヒトドルック・マハト・アン・オルドヌング!!」
圧倒的な爆発力で瞬時に迫るレラカムイに対し、エリカは己の周りに光球を六つ発生させて、後方へと飛びすさる。
「ベエンディグング・フェアフォルグング・プログラムス……アオス・シュトーセン!!」
行く手を阻む光の球に対して全く怯む事無く、レラカムイは一直線に突撃してくる。
「アムニン・オノイエ・ケ・レラ!!」
両腕をそれぞれ振るって光球に拳を浴びせ、眩い光を伴って爆発する。回転する帯が僅かに膨らみ、スクリューの様にさらに高速回転、風圧の壁が爆発力を巻き込んで、外側へと弾いてしまう。
爆発の中を駆け抜け、一気にエリカへと襲い掛かるレラカムイ。僅かに突進スピードの落ちたレラカムイに対して、いくらか余裕の出来たエリカが、ブルドガングを左腕から抜き放って応戦する。
「はあッ!!」
光を伴った斬撃に、レラカムイの左ストレートがブチ当る。
バチン!!
まるで掘削機の様なストレートがブルドガングと激突し、両者はお互いの技の威力で吹き飛ばされる。
「なんの!!」
身体を引き離されながらも、レラカムイは右手を突き出す。突き出された右腕の周りを回転していた帯が、さらに回転力を増してエリカに向かって伸長する。それを左の楯で防いだエリカは、横へと飛びながら眼に力を込める。
ズドン!!
突然の爆発。
念動力による爆発でレラカムイの身体が浮き上がるが、風圧の壁に守られている為か、傷一つ付いていない。
ズドン―――― ズドン―――― ズドン!!
何度も爆発が起こるが、その度に風圧に遮られる。
「ルヤンぺ・アム!!」
イラついたレラカムイは、そのまま空中で両腕を突き出す。巻き起こる風が集束し、二本の竜巻が発生する。射出された竜巻を躱したエリカの足元は、竜巻によってがりがりと削り取られて大きな穴を穿つ。両腕を使った事で大きな隙が生まれ、エリカは咄嗟の判断でレラカムイに肉迫する。
「喰らえッ! リヒトドルック・シュヴェーアト!!」
一際輝きを増したブルドガングが光の軌道を宙に描きながら、レラカムイの肩口へと叩き込まれる。
「甘いッ!」
レラカムイが両腕を突き出した格好のまま、視線をエリカへと向ける。驚いた事に、レラカムイの額に巻かれていた布がフワッと独りでに外れて大きく拡がったかと思うと、エリカのブルドガングを握った右腕全体に覆い被さって拘束してしまった。
「――なッ!?」
莫大なエネルギーを消費しての強烈な打ち込みだったにも関わらず、拘束された右腕はレラカムイの肩口を打つ前に、ぴたりと動きを止めたままびくともしない。
「念動力は、こちらにもあるんでな」
引いた右の拳が、エリカの鳩尾へと叩き込まれる。
「――がッ!?」
ズガガガッ!!
耳障りな掘削音が鳴り響き、エリカの鎧を削りつつ拳が打ち抜かれた。強烈な打撃が腹から背中へと突き抜け、エリカは勢いよく吹っ飛ばされる。鍾乳石で出来た壁に、背中から激しく叩き付けられたエリカの元から、巻き付いていた布が勝手に外れて浮遊し、ぶわっと風に乗ってレラカムイの元へと戻ってくる。そのまま独りでに、レラカムイの額に元通り巻き付いてしまった。
壁に叩き付けられたエリカは立ち上がってブルドガングを構え、削られた腹部の装甲はたちまち修復される。レラカムイに風圧の防御があるなら、エリカには鎧の防御があり、保有エネルギーこそ差があっても、元々の両者の基本性能は互角と言える。
しかし、今の立ち合いを見れば、徐々にエリカが押されているのが判る。不利な状況を打開する為には大技を使うしか無いが、今のエリカに使える大技は限られている。
あるとすれば、アスタロス戦で見せた『プファイラー・デス・ヒンメル(天の柱)』だろうが、アスタロスと同等の力を持つレラカムイに対して通用するかと言えば、それは難しいと考えざるを得ない。そもそも、『プファイラー・デス・ヒンメル』を使えるだけのエネルギーが、今のエリカにあるのだろうか。
前回は、ヒルデブラントの持つグラムの能力でエネルギーを供給して貰っての使用だった訳で、それが無い状態で使えばおそらくは一回こっきり、その後は力尽き兼ねないのだ。だが、滅殺能力のある攻撃手段はブルドガングしか考えられず、長期戦になればじり貧になる事は明白。
風圧に守られているレラカムイに、俺の打撃が通用するとも思えない。格闘の素人だったアスタロスなら兎も角、打撃戦に特化しているレラカムイなら、俺の動きにも簡単に追随出来るだろう。
それでも、他に有効な手段は無い。
ゆっくりと歩いて、エリカとレラカムイの間に入る。
それを見たエリカがすぐに反応する。
「いけませんレイジさん。貴方とレラカムイでは相性が悪過ぎる」
エリカの指摘は間違いでは無いが、だからと言って引き下がるつもりは無い。俺の視線を受けて、レラカムイが笑う。
「ははっ、同族の血が流れる者に拳を向けられるとは……どうやら無自覚な様だから、一つだけお前に関わる重大な事実を明確にしてやろうか」
いきなり、そんな事を言われるとは思わなかった。しかし、こちらの戸惑いを他所に、レラカムイは語り始める。
「――お前は『神殺し』だな」
レラカムイの口から飛び出たその言葉に、俺は眼を見開いて驚く。『神殺し』と言うからには神を殺す者だとでも言いたいのだろうが、その言葉だけでは、何の意図があってそんな事を言ったのかまるで理解出来ない。
後ろのエリカも、その言葉に呆気にとられる。そんな俺達の反応を楽しむかの様に笑みを浮かべ、レラカムイは先を続ける。
「どうして我ら環太平洋圏の神々が、世界から姿を消したのか……その原因の一端には、お前達『神殺し』が深く関わっているのだ。いや、だからと言ってお前達が悪いのでは無い。むしろこちらに非がある」
そこまでを語ると、レラカムイは敵を前にして眼を瞑る、と言う愚行を犯す。しかしそれは、今は戦うつもりは無いとの意思表示だろう。
「――一人の狂った神がいた。いや、『狂わされた』と言い換えるべきか」
まるで昔を懐かしむような感慨を以て、レラカムイの話は続く。
「その神は最強だったが、狂った力は同族である神や人に向けられた。誰もが敵わず、その他の神々は、狂った神をこの地に置き去りにして異界へと引き篭もったのだ。しかし、蹴散らされていた人間の中からある時二人の者が、狂った神の前に立ち塞がったのだ」
そしてレラカムイは、眼を開けて俺の眼を見詰める。そこにあったのは昔馴染みでも見る様な、柔らかい視線だった。
「一人は女。深い慈悲の心を以て、大地の恵みに感謝を述べた。恵みをもたらすこの世の力の源泉へと至り、人が人のまま神を倒す術を見出した。それに応えたのは一人の男。男は深遠よりこの世の記憶を辿り、一振りの剣を己が魂を以て具現化した。剣は狂った神の器を破壊したが、慈悲深き女は狂った神の精神を己が魂に受け入れ、その狂気を慰める事になった」
その話がどんな意味を持つのか、想像するのが怖かった。
己の魂が震えるのが判る。
何か、思い出してはいけない記憶を抉られているような感じがあった。
「判るか? その魂はお前に受け継がれている。そのまま素手で俺に挑もうなどと考えるな。己本来の姿を取り戻すならば、俺も応じよう」
その言葉がきっかけだったのか。
一瞬の閃きが脳を駆け巡り、世界の記憶とも言われるアカシック・レコードへと接続される。代々の崎守が受け継いできたのは主に剣術だったが、どうして剣を手にせずに、剣術を知っているのだ。
それは、意図的に逸らされていた。
俺は祖父から剣術を教わってきたが、今まで一度も、剣を手にした事は無いのだ。
そんな剣術があるものか。
どうして今まで、俺は素手だったのか。
それはいつか、己の剣を己が魂より引き出す為の、伏線に過ぎなかったのだ。
身体が勝手に動く。
『かつての崎守』が、同じく動いたのと同じ所作なのだろう。
反転しつつレラカムイとエリカの両者から、等間隔で壁際へと瞬時に移動。
次に構えを取って眼を閉じた俺を見て、エリカが信じられないものを見たかの様な顔で、呆然と呟いた。
「――うそ」
今まで黙っていた叶と棗も、驚きに眼を見開いていた。
「いつの間に……?」
「……手品?」
動きを止めた俺の左手が、鞘に収められた一振りの刀を手にしていた。反転しつつ移動する中で、この場の全員の『死角』が俺の背後に生まれた。その死角をその時に認識していた者は、世界中広しと言えどただ一人。
それは俺だけ。
「……この世全ての死角に我が魂は有り、死角より出ずるは刀ひとつ。―――銘は『一徹(ひととおし)』也」
俺の口から意識せずに、勝手に言葉が出る。
それもまた、『かつての崎守』の言葉だ。
己の内にある魂を認識する事は己にしか出来ず、それを外に向けて行う。
シュレーディンガーの猫の理論みたいなもので、確定していない筈の形を確定してしまうようなものだった。この手にある刀は、俺が認識している限り必ず存在し続け、決して劣化する事が無く、どんなものよりも硬い。これは、ただ認識によって存在が確定しているだけに過ぎず、俺の魂に刻み込まれた情報が存在の全てなのだ。
居合の構えを取って静かに調息する俺を見て、レラカムイがにやりと笑う。
「それこそが『神殺し』本来の姿だ。本来情報だけの存在であるその刀は、同じく情報のみの存在である神を殺す究極兵器だと言えよう。これで対等。面白くなってきたと言うものだ。なあ?」
同意を求めるかのように振り向いて、棗を見るレラカムイ。しかし、当の棗は驚きから立ち直ってぶうたれていた。
「こんなの聞いてないよう。対等って互角だって事なの?」
聞かれたレラカムイは腕を組んで、途端に難しい顔をする。
「いや、『神殺し』はどんな神であろうと互角だ。何せ存在自体が反則みたいなもんだからな」
訳の判らない言い回しに、棗の顔に疑問符が浮かぶ。
「何それ判んないよ」
「あれは、病んだ地球が生み出した対神兵器だからな……『あんちういるすそふと』ってヤツだよ」
アンチウイルスソフト、その例えならば判りやすい。
神という、自然の摂理から逸脱した存在に対する対抗手段。人が人のまま神を殺す、究極にして一の方法なのだから。
しかし棗には難しい例えだったらしく、理解の及ばないまま、割り切った様に聞き返す。
「いいよ、判んないし。それよりヤバイの? 勝てる?」
あまり緊張感が感じられないが、それを聞いたレラカムイは嬉しそうな顔で応える。
「さあて、勝てるかと言われたら勝つ、としか言えないだろう。ただ、かつての主神を倒したその能力に、純粋な興味があるって事よ」
どうやらこの風神は邪な思惑など無く、ただ興味があると言うだけで俺の力を引き出したらしい。
正直な話、こいつと戦うのは面白いかも知れない。
眼を閉じたままの俺を改めて見て、レラカムイも構えを取る。まるで存在を忘れられたエリカが、控えめに声を掛けてくる。
「……今回、私はお役に立てそうもありませんか……しかし、やはりレイジさんはサムライだったんですね」
どうしてもそこに拘るか。
俺は少し苦笑いを浮かべ、僅かに首を振る。
「……エリカが100%ならば、俺の方こそ必要無かっただろ。今回は俺に任せてみてくれ。きっとなんとかなる」
そう告げてレラカムイと対峙する。
「――行くぞ『神殺し』!!」
暴風を発生させたレラカムイが、空中へと一気に飛び上がる。
俺が空を飛べない事を考えて、自分に有利なフィールドで戦おうというのだろう。高さにして20メートル近い所で浮遊し、おもむろに両腕を胸の前に突き出してクロスさせる。左腕の帯が右腕の帯の隙間に入り込み、二つが一つとなって右腕に巻き付く。その右腕を肩の高さで後ろへと引き絞ると、腕の竜巻の空気密度が上昇し、風圧が倍加した。
「――リクン・プニ・ユプケ・ウェンテ!!」
声と共に突き出された右の拳から、今までよりも大きな竜巻が打ち出され、その中に、2本の帯がぐるぐるとミキサーの刃の様に回転しているのが見える。
だが、その帯の外側は空気の渦。躱すのは容易いが、そのままでは、躱しただけで攻撃に転ずる事は出来ない。
ならば、初手でカウンターを狙うべきだ。
空気の渦に巻き込まれた場合、内側へと巻き込まれてミキサーの餌食になる。だが、その渦の先にレラカムイの姿を捉えるならば、それは一本の道となる。
ギリギリで飛び上がった俺の背後で、竜巻が地面を抉る。次の瞬間、レラカムイは驚きに、思わず声を出していた。
「何だとお!?」
空中のレラカムイに向けて駆け上がる。
足下には、回転する空気の渦。
俺は横に側転宙返りを何度も繰り返しながら、竜巻の上を走っていた。
『心眼』で力の方向性を把握出来るからこそ可能な事だ。
俺にしてみれば単に、その場に留まれば横に滑る雪上の階段みたいなもので、中を回転する帯のおかげで、足の掛かる段差がはっきりとしているのがこちらの有利に働いた。
風圧の上を辿って、突き出された右腕の上に乗っかった俺を見て、ぎょっと眼を丸くするレラカムイ。不安定な立ち位置ではあるものの、居合の体勢に入った俺を見て、レラカムイは咄嗟に額の布地を左手で鷲掴んだ。
「ふッ!!」
刹那の間で鞘から刀を抜き放ち、レラカムイの首筋を狙う。
ガチン!!
驚くべき事に、レラカムイの左手に握られた布がネクタイの様な形状へと変化し、横合いから『一徹』の刀身の腹を打って弾き飛ばしたのだ。
俺の居合に反応するとは、さすがは神。
その動体視力は、尋常なものでは無い。
しかし、それで俺の動きが止まる訳では無い。
弾かれた刀をその慣性のまま鞘へと収め、たったの一動作で元の居合の構えに戻る。さすがに俺を乗せたままでは分が悪いと感じたのか、いきなり右腕に帯を呼び戻して、再び回転力を生み出す。高速回転をされては、右腕に乗っかったままの体勢を維持する事は出来ない。
俺は一気にレラカムイの頭上へと、逆さまに飛び上がる。
「逃がすか!!」
レラカムイは俺を見上げて、左の布を投げ付けてくる。
布は俺の目の前で大きく拡がって視界を遮り、さらに俺を捕縛しようとでも言うのか、覆いかぶさるように迫ってくるのだ。
どうもこの布は特別な素材で作られているというだけでは無く、何らかの力を備えた兵器なのでは無いだろうか。俺は居合の技を仕掛けようとしていただけに、この対応は正直厄介だ。
咄嗟の反応で、刀を鞘ごと布の中心に投げ付ける。自ら武器を捨てるという判断に、レラカムイはぎょっとする。
「何と!!」
刀を包み込んだ布地は、そのままレラカムイの手元へと戻ってしまい、俺はレラカムイの頭上を飛び越して地面に落下、そのまま着地した。だが次の瞬間、レラカムイは当然返ってくるべき感触が手に感じられない事に、戸惑いの表情を浮かべていた。
「……認識を切ると実物も消える、って事か?」
レラカムイの左手に握られた布の中、ある筈の刀が綺麗さっぱり消え去っていたのだ。布に包まれて誰の眼にも映らなくなった刀を認識する事を止め、着地した時に、俺の眼前に誰からも見えない死角が出来ていた事を受けて再び刀を認識し、その場で再び手にしていた。
一方の俺にしても、レラカムイの布に警戒感を持つに到ったところだ。双方が双方の得物をより意識している訳だが、考えてみればレラカムイは秘宝を持っているのだろうか?
俺は引っ掛けてやろうと思い、そのままの姿勢で質問をしてみた。
「その布がお前の秘宝か」
その言葉を聞いて、レラカムイはハッとした顔をする。
「……秘宝の事を知っているとは思わなかったが、考えてみればそちらにも神がいるのだから、知っていてもおかしくは無いか」
否定的な言葉が無い事で、図星なのだと判る。
「お前の言う通り、これぞ我が秘宝。名前はオムケカムイ……俗に『天の羽衣』などと呼ばれるものの原典となったものだ」
天の羽衣の伝承に天女という存在が語られるが、天女は確か仏教だったような気がする。だとすれば今の話はおかしいのでは無いかとも思うが、今までミノタウロスが牛魔王だったり、レラカムイがアラジンのランプの精のモデルだったりという事実があるのだから、今知られている話がどういった事実に繋がっているかなど判る筈も無い。
レラカムイの話に反応したのは、意外にもエリカだった。
「……使用者の意志を反映して、自在に機能を変える金属繊維……まさか貴方は、第一世代の神族では?」
その質問を聞いて、以前聞かされた話を思い出す。
北欧神話やギリシャ神話などに登場する神は、一番新しい第三世代の神であり、それ以前の文明を発祥とする旧世代の神もいるのだと。
レラカムイは、エリカの言葉に呆れ顔で応える。
「何だ? 今頃気付いたか。環太平洋文明とされる地球最古の文明こそ、我らの起源だ。神のシステムの殆どは、我らが構築したものなんだぞ? こんな事も出来る」
レラカムイはおもむろに手を振るう。
一陣の風が吹き抜け、地面に転がっている一つの石ころが宙に舞う。
しかし次の瞬間、今まで石ころだったその物体が、見る見る内に無色透明の煌めきを持った石へと変化を遂げた。何と、ただの石ころがダイヤモンドに変化したのだ。その現象を目の当たりにしたエリカが、呆然と呟く。
「――真正変質。初めてこの眼で見ました」
「何だそれは」
変質能力とやらの話は以前に聞いた覚えがあったが、真正とかいうのは初耳だった。
「ミノタウロスの牛頭変化は、変質能力によるものだと以前にお話しましたが、アレは変質能力の一形態、限定変質。自身の肉体しか変化させる事が出来ない限定変質に対し、真正変質はその他の物質に対しても、自在にその本質まで変化させる事が出来る。言わば、究極の創造の力だと言われています」
前にも同じような説明をされたが、レラカムイの持つ能力はとても希少なものなのだろうか。
「そりゃまた反則技だな……」
「私は第三世代の神族の中でも最も若い部類なので、細分化の進んだ能力の中でも戦闘能力に特化した限定神です。しかし、第一世代の神族はあまり能力分けをしていないのでエネルギー効率が悪い代わりに、殆どの力を備えた万能型なのです。風神とされているのも、単に一番得意としているのが風を起こす力だからと言うだけでしょう」
エリカは妙に感心したような口振りで、そんな説明を付け足した。当のレラカムイはあまり拘っていないのか、軽口でも叩く様な気楽さで答える。
「お前さんの言う様に、一応は多くの能力を保有してはいるが、得手不得手ってのは誰にだってある。さて、それを踏まえた上で次の攻撃をよく見るんだな」
そこで話を区切り、膨大なエネルギーが『オムケカムイ』に流れ込む。
まるでチェッカーフラッグを振り回すかの如く頭上で大きく回転させ、布地が見る見る内に大きく拡がっていく。布地の面積が大きくなるという現象は、やはり真正変質の力の一端なのだろうか。
しかしその程度で使うにしては、余りにも膨大なエネルギーを集束させているような気がする。今まで以上の警戒感を感じつつ、どうすべきかと考えていると、レラカムイが今まで干渉してこなかった叶と棗に向かって声を張り上げた。
「これから、ちょいと大きな力を使う! そこの男を連れてそっちの通路に避難してくれ!!」
今まで、人知を超えた戦いを目の当たりにして行動を起こせなかった二人は、やっと行動の切っ掛けを得た。
「おじさん! 座って見てないで早く逃げようよ」
「離してくれ! 凄い対決じゃないか! まだ見ていたいんだよ!!」
「なんか私達って完全に脇役だわね……」
二人は何とか教授を引っ張って、通路へと退避した。
「――行くぞッ!!」
頭上で振り回した『オムケカムイ』を、勢いよく地面に叩き付ける。その行動の意図が判らずにいると、次の瞬間に、布地が地面に吸い込まれる様にして消え去った。大地に消えた布地はその面積を拡げつつ、俺の足下まで瞬時に移動してきた。
「まずい!!」
嫌な予感がして、その場から一気に飛び上がって大きく退避、大地から現れた布地が、俺を包み込もうと襲い掛かる寸前だった。
「よくぞ避けた! ……だが、これはどうだッ!!」
次の瞬間には布地は俺の頭上を覆い、上から包み込もうと覆い被さってくる。それと同時に、レラカムイが俺に向かって突進してくる。
両手を大きく拡げ、風を巻き起こす。
二段構えの攻めに、俺は寧ろレラカムイとの間合いを詰める選択をした。しかしこちらの刀よりも先に、レラカムイの両腕の竜巻が俺に届く。そこで俺は、繰り出された右の竜巻の上に飛び上がり、軽く蹴りを打って反動を得る。
「何ッ!?」
頭上に飛び上がった俺の行動がまるで予測不能だったのか、レラカムイが驚きの声を上げる。上からは覆いかぶさろうと落下してくる布地があり、それこそ俺の攻撃対象だ。
「ふッ!!」
呼気と共に、一気に鞘から刀を抜き放つ。
両断された布地の間を通り抜け、俺はさらに上空にて逆さま反転、そのまま頭から落下体勢に入る。レラカムイは頭上の俺を見上げ、左腕を突き出した。
「――それを待っていたッ!!」
頭上に突き出された左腕に膨大なエネルギーが集束し、この円形の空洞内全てをカバーする程の巨大な竜巻を発生させる。
「きゃあッ!!」
壁際でエリカが地面に剣を突き刺し、風圧から必死に身を守る。
「しまった――」
空中にいた俺は、突如発生した膨大な気流に巻き込まれてしまう。ぐるぐると竜巻内部で、周回する身体のあちこちが悲鳴を上げる。そんな中で俺の両脇からは、両断された布地が竜巻に乗ってじわじわと迫って来る。
「時空の彼方へと消え去れえッ! ――ニシコトロ・ウトゥル・パイェカイッ!!」
ここに到ってやっと、『オムケカムイ』の真の能力を理解する。
成す術無く両側から挟まれ、俺は布地に全身を包まれてしまった。その瞬間に、今度は肉体を押し潰す様な強烈な圧力を感じ、脳内がシェイクされるような微震動で、様々な感覚が途切れ途切れになる。そして五感は消失し、頼れるのは『心眼』のみという状態まで追い込まれ、気付いた時には、最早自分のいる場所が『何も無い』のだと知った。
――そこは、空間と空間の狭間だった。
この世界は時間と空間と言う拡がりで形作られており、宇宙は暗黒物質ダークマターとか呼ばれる塵で満たされているらしい。
空間を横の拡がりだと捉えるならば、時間は縦方向への拡がりだと言えるが、もし時間を飛び越えて過去や未来へと自在に瞬間移動出来るとすればどうだろう。その瞬間に無限の可能性があるのだから、一つの未来、一つの過去しか存在しないなどと言う事は決して無い。
それが『平行世界』という概念。
だが全ては、観測する者がいて初めて現実として確定する。
この確定というのが大事で、俺が今存在している空間は、俺以外は存在しない亜空間だった。
「……対象を、亜空間に閉じこめる滅殺兵器だった訳か?」
誰もいない事をいい事に、俺は独り言を呟いた。
しかし、それは声として外に伝わる事は無い。
音すら存在しないこの空間において声は意味を持たず、俺自身が喋ったつもりなだけだ。
時間と時間、空間と空間の不確定の狭間。
そんな空間は、いずれ消え去るのだろう。
「もしくは不確定空間がいずれ消え去る事を利用して、対象ごと消し去るのが目的の滅殺兵器か」
どちらにしても、『死』より『消失』と言った方が正しいかも知れない。
酸素など無い空間ではあったが、時間の概念すら曖昧なこの空間において、人の生命活動すら定義が曖昧になる。
『天の羽衣』は、天女が天界へと帰還する為のものだったと伝えられているが、本来の使用目的は、異次元である神域と現実世界を自由に往来する為のアイテムだったのだろう。
しかし、神は己の力のみでそれを可能としている。
ならば『オムケカムイ』は神より下位の存在によって使われていたのか、それとも滅殺兵器として使うべきものを、移動手段として使っただけなのか。
真相は判らないし、実際のところ、今はそんな事はどうでもいい。それよりも早いところ、こんな場所から脱出しなくてはならない。とは言え、三次元の存在である人間に、そんな事が可能なのかと思ってしまう。
そこで思い浮かんだのが、メフィストフェレス戦の時の状況だ。
あの時は俺の認識能力が地獄を認識した事で、俺の存在ごと地獄に移ってしまったらしい。だが、移った事自体は俺の力では無く、エリカと契約した事で常にエリカを認識する事が出来る為に、地獄へと引きずり込まれたエリカに引っ張られる形だった。
――それならば。
「……ここでエリカを認識出来るかどうか、だな」
俺は早速、エリカの存在を探知し始める。
この亜空間、当然の事ながらエリカはいない。
はて、ならばどうやって、地獄にいるエリカを感知出来たのだろうか。
現実世界と地獄は、エネルギーの搾取によって常に繋がっている。メフィストフェレスの力の源であった地獄のエネルギーの出所を感知し、そこから辿ってエリカの存在にまで行き着いたと考えられる。それが判れば、エリカと俺を結ぶワルハラは俺達二人を結びつける。
しかし、この亜空間が現実世界とどう繋がっているのか判らない。俺に判るのは、この亜空間は現実世界の近似値の平行世界との狭間に漂っている、酷く脆い空間だという事だ。
もう一つの可能性が確定する前の、移ろいの中、とでも言おうか。それは時間と時間の間では無く、誰かが観察可能な状態にまで確定する間の、ストップモーションの行間みたいなものだろうか。
もともと確定していない行間にいるのだから、もしかしたら次の瞬間には、俺という存在は空間と空間の間で押し潰されているかも知れないのだ。では、その移ろいの次のコマを認識すればいいのかと言うと、それも違う。それは単に、隣の平行世界へと飛んでしまう事を意味し、俺が元いた世界には戻れないという事になる。さらに俺の移動した平行世界は、全く新しい世界になってしまい、それが確定してしまう。
では、俺が消えてしまった元の世界はどうなっているのだろう。
新しい平行世界になってしまうのか?
それも違う。
ちゃんと消えた事実は残るが、俺はまだこの空間で存在しているので、あちら側はまだ時間が進んでいない。
だから戻る事は、可能性として残っている。
俺が戻る為にはあちら側を認識する必要があり、そのきっかけがあればいい筈だ。
そこで、俺は左手の刀を見た。
見たと言っても視覚も意味の無い場所なので、『見た』つもりなだけだ。
触覚も無いので、手に握っているのかも判らない。
だが『心眼』による認識で、しっかりとこの手に刀があるのだと判る。
そこで気付いた。
この空間は、俺の『心眼』で初めて存在する空間なのだと。
虚無、ニヒル。
ならば、『心眼』で死角を認識する俺が緊急避難的にこの空間にいる、そういう事なのだと。『オムケカムイ』の能力と、レラカムイの最後の言葉で誤解をしていたが、本来ならば俺はとっくに消失している筈だったのだ。
それが理解出来た事に、軽い安堵感を抱く。
つまり俺は、死角を認識する事で『その場所』にこの刀、『一徹』を確定させた。
ならばこちらから、元いた世界を確定してしまえばいい。
それは単純な話だ。
地球のコアにて常に流転する、膨大なエネルギーに蓄積された大地の記憶を共有。
それがアカシック・レコードの正体だ。
地球の質量が丸ごと重力エネルギーを形成し、エネルギーは情報と同じ。
重力は近似の空間を伝播する特性がある。
それはこの空間も例外では無く、やはり地球の質量を感じる事が出来る。ならば、重力エネルギーを辿ってあちら側を認識する事が可能であり、それによってアカシック・レコードとの共有も確定する。
――現実を確定する。
無理矢理引っこ抜かれて、俺の認識へと引っ張り込まれる現実世界、そういう解釈が正しい。
唐突に、中空に俺の姿が出現する。
重力を認識した事で僅かなタイムラグが生じ、現実世界では僅かの時間しか経っていなかった。
どういう経過を経てそうなったのかは判らないが、エリカの放ったブルドガングの一撃を、右の拳で弾き飛ばしたレラカムイが、さらに暴風を纏った左の拳でカウンターを放つ瞬間だった。
「何いッ!?」
「――え?」
驚きに眼を丸くするエリカ。
エリカに拳が届こうという時に、空中から落下してきた俺の斬撃が、レラカムイの左の拳に巻き付いていた金属の布を切断したのだ。しかし、回転する暴風の威力に阻まれたのか、レラカムイ本体には傷を与える事は出来なかった。
二人の間に着地し、背中越しでエリカに声を掛けた。
「――よう」
呆けていた顔が、喜色に染まる。
だが次の瞬間、エリカの口から出た言葉からは僅かに怒りも感じられた。
「……貴方って人は」
左の拳を、半ば程突き出したままのレラカムイに思考が戻る。
「まさか、そんな莫迦な事が……どうやって戻ってきたんだ」
あまりの出来事に、信じられないと呆然とするレラカムイに向かって、俺は静かに眼を閉じ、粛々と語る。
「……神殺しとは、この星が生み出した概念。世界が続く限り、切り離す事は出来ない」
レラカムイは顔に手を当てて、悔しげに口を開く。
「俺の空間変動能力だぞ……相手が神であっても、そう簡単に破れる力じゃあないんだぞ」
レラカムイの言う空間変動能力とやらは初耳で、説明を期待してエリカの眼を見ると、意図を理解したのかエリカは僅かに溜め息をついて説明をする。
「空間変動……レラカムイの風を起こす力は、空間に干渉する事で可能となる力でした。数多いる風の神の中でも、最高の能力を持つ者だけが可能とする古の力です」
そんな事を語るエリカだったが、少し涙目なのは隠せようも無かった。がっくりと膝を地面に付いたレラカムイは呆けたような顔をしていたが、ふと俺を見て、諦めたような顔をした。
「……必勝の滅殺兵器を破られたんじゃあ、次はもう無い。降参だよ、降参」
それを聞いて、通路にいた棗が大声を出す。
「何それ〜!!」
振り返って棗を見ると、叶と教授も一緒だった。レラカムイは薄ら笑いを浮かべて、地面に胡座の格好で座った。
「今のは俺の切り札――最高の技だったのさ。それが通用しないってんじゃあ、俺の負けなんだよ。かと言って、神殺しに殺されるなんてウチの大将とおんなじだ。だったら、ここで白旗上げるのが妥当だと思うぜ?」
いつの間にか、レラカムイの口調が現代風の砕けたものになっている事に気付いた。


第四話・風神伝承
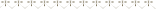
老人