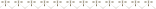Sick City
第三章・悪魔紳士
俺はエリカと共にまず警察署の出入り口まで行き、その間に襲撃が無かった事で外で敵が待ち構えていると考えて、あらかじめ想定していた策を実行すべく、エリカを開け放たれたドアの前に立たせて別行動を取る事にした。
階段で二階に上がり、外の正面がよく見える部屋を探す。
警察署自体は三階建てで、二階には資料室や会議室が大半を占めており、やっと見つけた部屋も何かの会議室らしき部屋だった。
外側一面が窓で外がよく見える。
ガラス窓を開けると僅かに風が吹き込んできた。
まだ暗い中、外を見ると正面の駐車場はいくつかの照明でところどころがよく見えるが、いくつかのパトカーの影が死角を作っている。
だが俺の『心眼』では、特に何かが潜んでいる様な気配は感じなかった。しかし微かに生命反応を感じて空を見上げると、一羽のカラスが何処からか飛んできて街灯の上に止まった。
「……む」
俺にはそのカラスが、とても場違いなものに感じた。
深夜にカラス。
夜行性では無い筈のカラスが、しかもたったの一羽でこの場にいる事の違和感。
そこでハッと一つの関連性に思い至る。
先程、黒犬を『使い魔』だと言ったのは誰でも無い、俺自身では無かったか。何かの本であったか、悪魔の使い魔としてよく知られるのがカラスだった様な気がする。
この部屋からでは距離がある為、『心眼』では保有するエネルギーの大小しか判らないが、もっと接近すればカラスの持つ力が特殊なものであるのが判るかも知れない。
しかしたったそれだけの事で、今ここから飛び出す訳にはいかない。幸いにしてカラスという鳥は夜行性では無いので夜目は利かず、おそらくはこの部屋にいる限りは俺の姿は確認出来ない筈だ。
それでも音を立てれば気付かれてしまうだろうし、そう容易には動けない。
もしエリカを狙う黒幕が自ら現れたとして、ここにいる俺に気付かないとは言いきれない。
視覚に頼らなくても『心眼』によって一定範囲の空間内での物理法則を把握出来る為、俺はガラス窓の下に隠れて目を閉じ、『心眼』による索敵に集中する事にした。
まずは、この警察署の玄関にいるエリカの状態を確認する。
遮蔽物が多い為に判る事はそう多くは無いのだが、エリカの精神状態は脳の活動による『漏れ電流』によって微かに把握出来る。
得体の知れない恐怖感と、俺と離れ離れになった事による孤独感が極度の緊張状態を生み、強いストレスを感じている事が判る。
エリカには、別れ際に本人にしか判らない形で合図を送ると指示をしていた。
しかし合図を送ると言っても、普通の手段では相手に気付かれてしまうだろう。
そこで俺は、ある方法を試すつもりでいた。
やった事は無いし、今までの俺だったらそんな事は考えもしなかっただろう。だが『心眼』を会得し、『個の認識』が明確になった今、特定の対象人物から漏れ出る思考を読むだけで無く、その思考に介入する事も有り得るのだ。
それは俗に、テレパシーと呼ばれている類いのものだ。
ただテレパス能力者はそれ専用に特化されているからこそ、明確な意志を遠く離れた相手に伝達出来るのであって、俺の様なあらゆる現象に対する危険回避能力として開花した能力では用途が違う。
増大した己の自意識が、空間を伝播して電磁波として情報を伝達する訳だが、通常は放射状に発散される意志を、指向性を持たせて先鋭化する為の出力回路が俺には無いと言う事だ。
そして個人によって思考を形作る電磁波の周波数には若干の差があり、それはまるでラジオ放送の様に、特定されていなければただの雑音というだけでは無く、そもそも認知する事さえ不可能なのだ。
俺はエリカと意見を交わし、幸いにして心を通わせる事が出来た。
それがつまりは周波数合わせの作業と同義であり、俺の方でエリカの思考にチャンネルを合わせる事が可能になっている。これがどういう事なのかと言うと、実際は情報を伝達して合図を送るのでは無く、エリカの思考に介入して行動に影響を与える事が出来る、と言う事になる。
とは言ってもあまり複雑な事をさせられる訳では無く、単純にエリカに行動のきっかけを作ってやるだけの話だ。
こういった事を、人はよく『虫の報せ』などと言う。
本人は俺から命令を受けたとは全く思いもよらず、ただなんとなく、『勘』でそうした方がいいと思うだけ。
こうして理屈を説明すると特別な力の様に思うが、実はどんな人間でも少なからずこういった力は持っているのだ。
人の気持ちが人を動かす。
個人から漏れ出る電磁波を受け、その人間の行動が影響を受け、それはお互いに、或いは全ての人間に当てはまるかも知れないのだ。そういった強い思考に特化した能力者、それがテレパス能力者であると言えるだろう。
俺はまず、そろそろ外へ出ても問題は無さそうだという方向性を与えた。すると若干の時間を置いて、エリカはそわそわとし始めた様だった。さすがにテレパス能力者の様に意志を伝えられる訳では無いので、本人の躊躇いを少し軽減させただけの様だが、それでも数分してエリカは思い切って外へと歩いていった。
その時、例のカラスが動きを見せた。
しかし身体を動かしたのでは無く、カラスからマイクロ波による情報の発信が行われた様だった。生憎とカラスから発信された情報のプログラム言語を理解は出来ないので内容は判らない。
プログラム言語という表現は例えであり、おそらくはこれこそ『黒魔術』と呼ばれるものだと思われる。
まず人間の思考に使われるのは、プログラム言語で言えば高級言語、専門用語でBASICなどと呼ばれるものに相当し、低級言語に機械語が存在するのだが、低級言語はコンピュータ寄り、高級言語は人間が理解しやすい方向へ寄ったものである。高級言語は人間が理解しやすいが、コンピュータには直接理解が出来るものでは無く、その為に低級言語へと変換して処理するので処理速度は著しく落ちる。
黒魔術とはより数学的なもので、つまりは宇宙の法則、0と1の数字の羅列である情報エネルギーを人間の言葉として口に出来る様にダイレクトに表現したものだと考えられる。
神や悪魔と呼ばれる連中は、その存在そのものがエネルギーの塊である為か、エネルギーをコントロールする術を持っているのだ。これは人間の武術家が、己の肉体を流れる『気』をコントロールするのと似ている。しかし高次元の存在である彼ら悪魔は、人間よりも多くの力を行使出来るのだ。
カラスがどういった魔術を行使したのかは判らないが、結果はすぐにでも判るだろうと俺は踏んでいた。あのカラスが監視者としての役割を持っているとするならば、十中八九、自分の主に現状を伝えたのだと思う。
そして数秒後、大地を伝わり強大なエネルギーが駐車場のど真ん中に向けて収束するのが感知出来た。それと共に警察署を中心としてかなりの広範囲に渡って濃霧が発生する。あまりにも突然の事で現実として受け入れ難い話ではあるが、これは大地を膨大なエネルギーが流れ続けた結果、地下から水蒸気が発生した為と思われる。
数秒の後、濃霧の中心に得体の知れない強烈な圧迫感が生まれた。
――膨大なエネルギー、強烈な悪意、そして震える大気。
人間よりも遥かに高度な存在の為か、その思考はとても複雑であり、理解出来るのは欲望のみ。
周囲を霧に包まれたエリカは、突然の事に動揺していた。
と言うより、最早精神の限界に達す寸前であり、動揺を通り越し、恐慌する暇も無く、判断する事を放棄していた。これは理解してはならないという、自己防衛本能の現れである。これ以上傍観していては、すぐにでも機会を逸してしまう。
俺は窓枠に手を掛け、外に向かって一気に飛び降りた。敵と思われるエネルギーは既にその構成を変え、物質化へと移りつつある。俺がエリカの目の前に着地したのと、敵が実体化したのとはほぼ同時であった。
「………はっ!?」
いきなり空から俺が降ってきたからか、思考の停滞を引き起していた筈のエリカは我に返って目先の焦点を俺の背中に合わせた。
「覚悟を決めろ!兄さんを殺された理不尽に怒れ!怒りを正しさに変えて揺るぎない己を貫け!これから目の前に現れるのは本物の悪魔だ。プレッシャーに飲み込まれるんじゃないぞ!!」
思考が回復したエリカではあったが、未だに思考がまとまらずにいる状態であり、このまま敵と遭遇してしまえば確実に正気を失う。だが明確な意志を持ち、それを貫く強い動機があれば余計な思考はより少なくなり、より集中力が高まる。
圧倒的なプレッシャーの中で、弱者であるエリカが己を見失わずにいる為には、たった一つでもいいから変わる事の無い気持ちを思い起こさせる事だけだ。そして俺の言葉が、エリカの心の奥底にある肉親への愛情を刺激したのか、はっきりとした思考が甦ってきたようだ。
「……とっても怖い。でも兄さんの為にも私は生きたい。もし私がつまずいたら、今みたいに助け起こして貰えますか?」
霧に視界を遮られ、俺の姿など朧げにしか見えないだろうに、それでもエリカは俺に思いの籠った視線を向ける。
「助けるけど、自分でも頑張るんだぜ?」
頷きを返すエリカを背に、俺は霧の中の悪魔と対峙した。
コツコツと甲高い靴の音と共に、ゆっくりと歩いて近寄ってくるのが判る。
その不気味さに耐えられないのか、少し離れていたエリカが俺の姿を確認出来る位置まで近寄ってきた。そして相手の姿が確認出来ると同時に、その男は手を叩いて不敵な笑みを浮かべた。
「ブラヴォ! 私の絶対支配領域の中、よくぞ意識を保ったものだ」
男である。
何がおかしいのか判らない程、その男はただの人間に見えた。
もし気になるところがあるとするならば、中近東辺りの顔立ちをした、外国人であるという事だろう。黒い生地に白いストライプのラインが入ったスーツに身を包み、目深に被ったコークハットの下には、いかにも紳士然とした毅然とした顔立ちがあった。
「……お前が、化け物共をけしかけた親玉か?」
こいつは、人間の外観をした化け物だ。
内包するエネルギーが桁外れなものであり、俺の『心眼』は今まで以上に敵が強大であると認識していた。俺の言葉を聞いた男は己の顎髭を指で撫で、低く忍び笑いを漏らした。
「くっくっくっ……なかなか面白いボーイだ。世界はかくも広いのかと、驚嘆しているところだよ」
男は右手に持ったステッキで、地面をコツコツと突いて微妙な間を取った。
「わざわざ黒幕自らのご出陣、俺を見抜きに来たと見える。こそこそしてたかと思えば一転して大胆不敵。さぞや名のある悪魔と見受けたがどうだ」
俺にとって敵は強大で、実際のところ勝てる見込みは無いに等しい。情勢が変わるや否や、一転してリスクを背負ってでも前面に出るヤツはとても危険な相手だ。俺の思い切った言葉を聞いて、男はゆったりとした動作でコークハットを取り、深く礼をした。
「深い洞察に敬意を表す。我が名はメフィストフェレス。何、我が名は余りに知られ過ぎているので、隠しても仕方が無いのでね」
悪魔メフィストフェレスと言えば、紀元前にイスラエル王国の王であったとされるソロモン王に使役されたと言われている、悪魔の中でも五指に入る程の、名の通った存在だと言える。
「エリカを付け狙うその目的、どうせ聞いた所で正直に話すとは思えない。だが悪魔は、人間に使役される事でこの世界に干渉する事が許されている様な話を聞いた事がある。これはお前の意志でやってる事なのか?」
悪魔についてそれ程詳しい訳では無いが、実は知り合いにオカルトマニアみたいなヤツがいるので、そういった話は少しばかり噛った事がある。どうしてその様な取り決めがあるのか、その詳細は知らないのだが、推察出来る範囲で言うならおそらくは宗教的な理由になるのではないか。
「ふむ、なかなか良い質問だな。確かに目的を明かす訳にはいかないし、何よりこれから死ぬ者に、何を言ってもあまり意味があるとは思えないね」
俺の質問にメフィストフェレスは興味を持った様だが、しかし即答は避けた。何よりその理由を一番知りたがっている筈のエリカが、悔しげな感情を僅かに覗かせたのは印象的だった。
「……とは言え、私は悪魔の中でも温和な性格でね。何より、人とのコミュニケーションが好きなのだよ」
次に口から出てきた言葉が、メフィストフェレスの性格を物語っている。コミュニケーションが好きなのは判るが、意地の悪さを持った意志のやり取り、つまり、知恵比べ的なものを期待している様な節を感じる。
「何、これはキミを勇者と認めたからこそ是非聞いて貰いたいのだ」
悪魔の口から出た言葉の意図が判らず、俺は新たな疑問を持つ事になった。
「……勇者? それが何の関係があるんだ?」
それを聞いたメフィストフェレスは、話題を逸らした事に成功して喜んでいるのか、それともそんな事は無く、単なる言葉遊びを楽しんでいるのか、意味有り気な笑みを浮かべて話を続ける。
「う〜む、実はここ二千年余り、まるで私の出番が無くて退屈をしていたところでね。久々に私を使役出来る者が現れた訳だが、実はそれ自体はそんなに面白い話では無いんだよ。私としては、契約以外の事については自由にやる主義でね。ここで敢えてキミらに有益な情報を与えたら面白くなりそうだと、まあ、そんな訳なんだが」
何が何だか判らないが、メフィストフェレスは個人的な嗜好を理由に、使役者の意志とはまるで関係の無い行動をしようとしているらしい。圧倒的に不利な俺としては、どんな形であれ、こちらに有利になるのなら話くらいは聞いても問題無いだろう。
俺が黙殺しようとしているのを感じ取ったエリカが、背後から声を掛けてくる。
「よろしいのですか? 何か思惑があるのでは無いでしょうか」
どうも『群の認識』による意志疎通を行った為なのか、俺がエリカの意志や感情を読み取れるのと同じ様に、エリカも多少だが、俺の意志を漠然と感じる様になってしまっているらしい。これは俺がエリカの脳波に同調したままの状態を保っている所為だが、行動を共にしている間は、そのままの状態の方がいいと判断しての事だった。
「話を聞くだけなら別に問題は無いと思うし、もし呪詛みたいな事をやらかすつもりでも、俺には通用しないよ」
俺とエリカの会話はメフィストフェレスにも聞こえているが、それも特に問題にはならない筈だ。
「……キミは指輪を手にしているだろう。ソレを出してみたまえ」
メフィストフェレスの言う指輪とは、俺がエリカに渡した、エリカの兄が持っていた指輪の事だろう。エリカは自分の手に握られた指輪をしげしげと眺め、俺に視線を送ってきた。
「この指輪が目当てなのでしたら、私達の命を保証するのであれば差し上げます」
代々伝わる大事な指輪の筈だが、それも命には代えられないとの判断なのだろう。しかしメフィストフェレスは、首を横に振ってその申し出を拒否した。
「そういう事を言いたいのでは無い。その指輪を彼に渡したまえ」
この段階になっても、メフィストフェレスの意図するところは判らない。エリカは若干悩んだものの、俺に対して絶対の信頼感を持っているのか、手に持った指輪を俺に差し出してきた。
「……いいのかい?」
俺の問いにエリカは頷きを返した。
指輪を受け取った俺を確認し、メフィストフェレスは再び口を開く。
「指輪を嵌めたまえ」
相変わらず意図が判らないが、悩んでいても仕方が無いので言われた通りにする。俺は右手の薬指に指輪を嵌めたが、それで何が変わる訳でも無い。
「うむ、それでいい」
鷹揚に頷くメフィストフェレスに、俺は訳が判らずに問い返す。
「一体、何の意味があるんだ?」
「勇者の証明を果たすのだよ。さすれば、忘れ去られし神は降臨するであろう」
それが、メフィストフェレスの意図するところなのだろうか。
忘れ去られし神、とは一体何の事か。
そして勇者の証明とは?
まるで、ナゾナゾでも出された様な気分だった。
「何が言いたいんだ? 勇者の証明ってのは何の話なんだ」
「単純な話だよ。勇者と認められる事。その一点に尽きる。今までの戦いで充分に証明になっているとは思うんだが、残念な事に指輪を嵌めていなかった」
訳の判らない説明の後、意味深な一言をメフィストフェレスは付け加えた。
「まあ、彼女がどう思うのかによるのだがね」
彼女、とはこの場にいる者で該当するのはエリカしかいないのだが、どういう意味なのか。それとも、何処かでその『彼女』とやらが見ているとでも言うのか。
「これでお前にとって、面白くなるって事なのか?」
俺は相変わらず意味が判らず、しかしメフィストフェレスもまた、相変わらずだった。
「さて、面白くなるかどうかはキミ次第だと思うがね」
そう告げると、手にしたステッキの先をこちらに向けて左半身の構えを取った。
それに合わせて、俺も構えを取る。
しかし、これは自ら構えを取ったのでは無く、取らされた形だ。潜在的な防衛本能がメフィストフェレスを危険な相手と認識して無意識的に構えを取ったのだ。
構えを取らされると言う事は即ち、相手の方が強い、と言う事だ。
「エリカ」
俺の背後に寄り添う様に立つエリカに声を掛ける。すぐに俺の意図を察して、警察署の入り口辺りまで小走りで離れてくれた。
相手に構えを取らされ、その上先手を取られては負ける。
そう判断した俺は、機先を制する為、一気にメフィストフェレスの間合いに踏込んだ。
一瞬で間合いを詰めてくる俺に対して、メフィストフェレスは左手のステッキを突き出しつつ、バックステップで後退する。
その動きはサウスポースタイルのフェンシングといった印象であり、左のステッキで距離を取りつつ、こちらを牽制するかの様に身体を前後に揺する。
近接戦闘に持ち込みたい俺だが、メフィストフェレスはとてつもない速さで突きを繰り出す。
ボボボボボボッ!!
空気の壁を突き破る様な音が辺りに響き渡る。メフィストフェレスの間合いの中、俺はステッキの弾幕を躱し続ける。
「なるほどなるほど!超感覚能力を体術に応用する人間とは初めてだ!!これは面白い!!」
常人を遥かに超える速度と威力持った突きによる弾幕は、普通の人間ならば何十本ものステッキが見えた事だろう。
しかし、『心眼』によってメフィストフェレスが突きを繰り出す時にどこの筋肉を使うのか、僅かな動きによって周辺に起こる些細な影響などが感知出来る為、どんな風に自分の身体を操れば全ての攻撃を躱せるかが判る。
脅威の手数を誇るメフィストフェレスの攻撃を、その場で躱す事は不可能であり、天仰理念流に伝わる特殊な歩法を用いる事によって、不可能が可能となる。
例えば攻撃を避ける際に、相手に正対したままでは自ずと避けられる範囲に限度がある。
それを克服するには足捌きを用い、相手から軸をずらして身体全体で攻撃を避けるべきなのだ。その足捌きの連続移動によって、メフィストフェレスの突きを悉く躱す事が出来る。足を運ぶには、右に避ける時は後ろ足である右足を斜め右に大きく踏み込みつつ重心移動。
こうする事によって相手から軸をずらす事になり、さらに後ろ足となった左足を前方へ進める事によって相手の左側面の死角へと入る事が出来、次の攻撃を封じる事が出来る。左に躱す場合は、前足である左足を斜め左へとスライドさせつつ重心移動をすれば同じ事が可能である。
しかし、メフィストフェレスもかなりの技巧の持ち主であり、こちらが側面へと入身するとそれに合わせて軽くステップを踏んで、足位置を巧みに組み替えて対応してくる。その結果、俺とメフィストフェレスは目紛しく立ち位置を替えつつ、互いの隙を伺う形になっていた。
「……ふんっ!!」
躱し続ける俺を捉える為、メフィストフェレスは掛け声を上げつつステッキを俺の足元へと突き込んできた。しかしその攻撃も既に予測済みであり、俺は反転しつつメフィストフェレスの背後へと周り込み、その首筋に手刀を叩き込んだ。
「破ッ!!」
――ゴキッ!!
頭上へ高く揚げた右手を振り降ろしつつ屈伸、一気に間合いを詰め、メフィストフェレスの右肩口から首筋へと手刀を叩き込みつつ駆け抜ける。
突進スピードと全体重を乗せた一撃はメフィストフェレスの頚椎をへし折り、勢い余ってその身体は地面に叩き付けられて大きくバウンドした。
一撃必殺。
まさに、一瞬で死を招く攻防。
メフィストフェレスの身体は地面に伏したままピクリとも動かず、手に残る感触から、確実に殺した事を実感した。
しかし、相手は名だたる悪魔だ。
果たしてどこまで通用するのか、疑問を感じる。
一瞬で絶命した事は肉体の生命活動を感知しているので判ったが、周囲に影響するエネルギーの意志に揺るぎは感じない。
俺は油断無くメフィストフェレスから距離を取って成り行きを観察していたが、退避していたエリカの目には違う形で見えたようだった。
「レイジさん!」
安堵した表情で駆け寄ってくるエリカだったが、明らかに事態を読み違えている。
「まだだ! こっちへ来るな!!」
俺はエリカに、止まる様に手で制した。
同時に、命を断たれていたメフィストフェレスの肉体から膨大なエネルギーが沸き起こり、突如として周囲の大気に振動が伝播する。
この警察署の近隣一帯に淀むエネルギーが、メフィストフェレスの肉体を即座に回復させてしまったのだ。
「!!!!!」
風圧に煽られて手で顔を庇ったエリカは、驚きの表情を浮かべていた。
「……ふむ。人間に殺されるのは初めての経験だな」
一瞬で動けるまでに回復したのか、スッと立ち上がったメフィストフェレス。
「――化け物め」
俺は呻いたが、実際のところあまりショックは感じていない。
元々、まともにやり合って勝て無いと判っている相手だ。今のはメフィストフェレスが悪魔本来の力を使わずに、こちらの戦い方に合わせていたのと、メフィストフェレス自身の油断が招いたラッキーヒットだったと割り切った方がいい。
「いやいや、たいしたものだ。たったの一発で即死とは。こうして何度も私を殺せば或いは、いつかは本当に殺す事も可能なのかも知れないな」
事も無げにそんな事を言いながら、首を左右に振ったり肩を回したりして身体の調子を確かめている。膨大なエネルギーそのものがメフィストフェレスの正体である以上は、俺の手で触れる事の出来る肉体に宿るエネルギーなど極く一部に過ぎないのだ。エネルギーと質量は比例するものだと言うのに、何処にそんな質量があるのか。
どうすれば勝てる?
人間の持てる技のみで、この化け物を倒す事が出来るのか。
「……ともかく、俺のやるべき事をやるだけの事だ」
俺の考えなくてはいけない事は、エリカを無事に逃す事、そして生きて家に帰る事だ。再び構えを取る俺を見て、メフィストフェレスは不敵な笑みを浮かべる。
「おやおや、姫の眠りは相当に深いと思われる」
――何の事だ?
俺はメフィストフェレスの言葉の意味が判らずに少し考えたが、この場で『姫』に該当する者はエリカしかいない。
「……?」
当のエリカも何の話なのか判らないらしく、怪訝な表情を浮かべているだけだ。
「それでは、少しばかり手品でもお見せしよう」
メフィストフェレスは唐突にそんな事を言うと、右手の指をパチンと鳴らした。
「……!?」
周囲にいくつかエネルギーの揺らぎが発生し、次第に何かを形作る。
――ボッ!!
突如として6つの火の玉が出現し、地上2m程をゆらゆらと浮遊した。
「鬼火、と言うヤツだよ。何、そこの建物の地下には亡者の魂の名残がいくらか見受けられたのでね。魔の力はそうした残留思念をスターターとして、この物質世界に力を具現化する事を得意としているのだよ」
メフィストフェレスの説明通り、俺は『心眼』で火の玉の持つエネルギーにノイズ混じりの劣化した人の意識らしき名残を感知していた。それは警察署の地下の死体安置所に、一時的に保管されていたであろう死者の残留思念だった。
人は生前抱いていた強い思いを、死後においても残す事がある。
普通は時間と共に、自然へと拡散して情報として意味を成さなくなるのだが、稀にエネルギーの拡散の中で情報のみが安定したエネルギーへと転写されて、永く維持される事がある。
例えば、巨大な建築物ならばその固体としての巨大な重さが重力エネルギーを有している訳で、その力はその建物が存在する限りはずっとその場所に存在し続ける。
それが、自縛霊と呼ばれるものの正体だったりする訳だ。
「威力は弱いが、この炎はなかなか粘着質でね。一度引火すればなかなか消えない。これ一つで人間一人を殺すだけの力がある」
そう言ってメフィストフェレスは右の人差し指を立てて、ぐるっと回して見せた。その動きに呼応するかの様に、6つの鬼火は俺の周囲を周回し始めた。
「さあ! ダンスタイムの始まりだ!!」
威勢良く宣告をし、メフィストフェレスは右手の人差し指を頭上に揚げてから一気に振り降ろした。
振り降ろした指が俺をピタリと指すと、6つの鬼火が一斉に俺目掛けて飛んでくる。
鬼火の大きさは直径にしておよそ15cm程であり、それ程大きい訳では無いにも関わらず、凄まじい熱気を放ちながら急接近してくる。
その速度は音速に近いものであり、今この一瞬で最早手遅れな程に接近していた。超高速によって生まれた大気の壁が、熱風を伴って6方向から俺の身体にぶち当たろうという寸前にまでなっていた。
絶体絶命の状況において、再び俺の思考は途絶して反応反射に特化した。
6つの鬼火が滑空する高さよりも低い姿勢、まるで大地に伏せる虎の様な、両手を大地に付けて足を大きく開いた姿勢になりつつ回転し、その回転力を利して6つの鬼火の衝突する爆発地点から一気に脱した。再び思考が正常に戻った時、俺は反転しつつメフィストフェレスの左側面に位置していた。
――ズドン!!
遅れて、鬼火の爆発音が周囲に轟いた。
俺は反転スピードの勢いそのままに、後ろ向きの形でメフィストフェレスの背後を取った。
「!!!!」
遅れて反応したメフィストフェレスは俺を迎撃するつもりなのか、精神を集中して異質なエネルギーの発現を試みる。
「――遅い!!」
背中越しに、俺に視線を向けたメフィストフェレスが驚愕する。腰溜めにした両の掌を、捻り運動を加えつつメフィストフェレスの背筋部分へと一気に叩き込む。
ずしり。
「うがッ!!!!?」
捻転する衝撃はメフィストフェレスの体内を駆け巡り、内蔵諸器官を徹底的に破壊する。そして破壊し尽くしてもなお留まるところを知らない衝撃は、メフィストフェレスの体内だけでは収まり切らず、胸部から外へと放出され、衣服が弾け飛ぶ。
ズバン!!
一瞬の間の後、少し遅れてメフィストフェレスの背広の両胸部分が、まるで見えないドリルが突き抜けたかの様に弾け飛んで四散した。
これぞ天仰理念流絶技・双捻掌。
メフィストフェレスの呼び起こしたエネルギーは、俺の放った捻転エネルギーによって四散し、突っ立ったままで絶命した。
口元から血を流し、うつ伏せに大地に倒れ伏すメフィストフェレス。
二度目の死を与えたものの、未だ一帯をうっすらと覆う異界のエネルギーの存在がある限りは、終わりでは無い。
どこからともなく溢れ出る膨大なエネルギーが、再びメフィストフェレスの肉体を蘇生させ、わずか数秒での復活を果たす。ゆらりと立ち上がったメフィストフェレスの目に意志の光が灯り、おもむろに衣服についた汚れを手ではたく仕草をした。
「……やれやれ、新調したスーツが台無しだ」
油断無く身構えて、メフィストフェレスの動きを警戒する俺とは対照的に、あくまで余裕を垣間見る事が出来るメフィストフェレス。
嫌な予感がする。
正直、今の段階で俺は一杯一杯だ。
確かに直接打撃が当たれば一撃で殺せるのだが、メフィストフェレスはそのたびに復活する。対してメフィストフェレスも一度の攻撃で俺を殺す事が充分に可能であり、俺に復活は無い。
「さて、どうも我が契約者は気が短い様だ」
突然、メフィストフェレスはそんな事を口にした。
「……?」
よく判らないが、どうもメフィストフェレスは契約者とやらとの間にコンタクトがあった様だ。
「確かに。キミとこうして殺りあっているのは単なる私の趣味だがね。時間の浪費と言うもの程、贅沢なものは無いと私は思うんだがねぇ……」
契約者と一体、どんな趣旨のコミュニケーションを取っているのか。
「ふむ、まあ先に結果を出せと言うのも判る話ではある。ボードの上に駒の無いチェスなど無意味ではある」
姿の見えない相手との会話を終えたのか、メフィストフェレスは視線をこちらに合わせて困った様な顔をした。
「悪いが、方針変更の様だ」
そう告げたメフィストフェレスの左手が、横へ伸びる。
膨大なエネルギーが収束し、信じられない事が起こった。
エネルギーとはそもそも物質を構成する原子の中心、原子核の周囲の電子が自由運動をする事で生じている。即ち、エネルギーの発生は同時に物質の存在と同義である。物質からエネルギーが発生するならば、その逆もまた当然ある事であり、目の前で起こっている現象はまさに、無から有が生まれる瞬間であった。
どういう方法で、それが可能になるのかは判らない。
しかし、突如として現れた十数本の短剣が放つ鈍い光が、俺の眼球に映っているのは事実だった。
そして、その切っ先が向けられている先にあるもの。
「――」
目の前で起こった異常な光景を前にして、当のエリカはただただ絶句する他無いと言った様子だった。メフィストフェレスの真意は一体どんなものなのか、ただ一瞬の反応に己を任せるしか無かった。
「……え?」
エリカの紺碧の瞳が、俺を見ていた。
そこに映る、紅い色。
「――ふむ」
対してメフィストフェレスは、俺を見てわずかに驚きを見せた。
全身を走る激痛。
メフィストフェレスの放った数十本の短剣が、エリカ目掛けて放たれる時、俺は咄嗟の判断でエリカの前に立ち塞がり、半身の姿勢で全ての短剣をこの身で受けたのだった。
それでも胸元で交差した両腕で致命的な損傷は免れ、顔を庇った右の掌に1本、心臓や内蔵を庇った左腕に3本、後は左足に5本の短剣が深々と突き刺さっていた。他の数本は寸前で叩き落としてはいたが、さすがに捌き切れずに身体を楯にするしか他に無かったのだ。
しかしこれで、俺の身体は満足に動けない状況に陥ってしまった。
「……ぐッ」
左膝が自然に地面に落ちてしまい、力が入らずに膝ががくがくと震える。突き刺さったままの短剣から流れる血をしばらく眺めていたエリカが我に返り、慌てて俺の身体に手を伸ばした。
「ああ、なんて事に……大丈夫ですか!?」
しかし俺は、震える手でエリカを制した。大気に満ちる膨大なエネルギーが再び収束する。
「神は今もって、生け贄を必要とするのかね! 我ら悪魔と対して変わらん訳だ!!」
メフィストフェレスは大きな声を出し、突き出した右手に力を込める。出現した巨大な炎が、さらに周囲からエネルギーを吸収して炎の中心に凝縮される。
まずい。
このままでは、俺もエリカも助からないだろう。
俺一人ならもしかしたら逃げる事も出来るかも知れない。
しかしエリカには、あの炎から逃れる術は何も無いのだ。
まさに絶体絶命。
まして今の俺は、果たして一人で逃げる事も出来るかどうか怪しい状態だ。
そもそも逃げる事が出来る相手では無いと判断したからこそ、こうして戦ってきたのでは無いのか。結局は始めから勝てる見込みなど万に一つも無く、俺の意志一つである結果が得られるかも知れない、と言うだけの事なのかも知れない。
――相打ち。
俺は既に死ぬべき運命であり、変えられるのはこの場にいる者の死ぬ順番だけであったのだ。俺が逃げればエリカが真っ先に死に、残った俺はメフィストフェレスと戦いその内死ぬだろう。メフィストフェレスを俺が倒せればいいが、それは無い。
俺が先に死ねば、残ったエリカは結局殺される。
では、俺とメフィストフェレスの相打ちは可能なのか。それは今この瞬間のみ、可能かも知れない。
メフィストフェレスの目の前に収束する、炎の塊。
もし今、メフィストフェレスの集中力が途切れたらどうなるだろう。もしメフィストフェレスの肉体が消失した場合、蘇生は可能なのか。
最早、考えている余裕など無かった。
俺は残る力の全てを以て、悲鳴を上げる身体を無理矢理奮い立たせて突撃した。死を受け入れたせいなのか、俺はこの最後の瞬間に一つの進化を得た。脳を構成するニューロンが新たに相互接続し、今まで断片的だった情報が一つの形を成す。
それは、時間を超えた思考とでも言うのか。
今までは途絶していた意識を補うべく、この地球という星が持つ、情報集合体に蓄積された単一の指向性が、肉体の制御を肩代わりしていた。
しかし事ここに至り、俺の意識は肉体から一時離れ、例えるならばコンピュータにおける分散処理で、単純だが膨大な数値演算の処理が独立した回路で行われる様になったのと同じ様な形態へと進化をしたのだ。
肉体が反復によって覚えた単一の動作に関しては、自然界のエネルギーの持つ情報集合体が使用され、認識に関しては俺と言う自意識が特化する。これによって時間の流れから一瞬だけ乖離し、俺の行える一動作において時間の束縛がまさに消失する。
俺はこの瞬間、メフィストフェレスとの距離をゼロに出来る。
「!?」
しかしその試みは、寸前に断たれた。
淡く光を放つ指輪。
金属が持つ微弱な電位はおそらく何かしらの情報が含まれており、何かのきっかけで情報を発信する仕組みを持っていたようだ。一瞬だが身体から力が抜けてしまい、足が進まなかったのだ。
――そして、異変は起こった。
夜空に輝く光のカーテン。
天をあまねく覆い尽くすオーロラが、夜の地上を真昼よりも明るく照らす。強力な電磁波によってこの地上に存在する殆どの電気製品は障害を起こし、電力の供給もストップした事だろう。オーロラと言う現象を引き起した強烈な電磁波は、この指輪が発進した電気信号がトリガーの役割を果たした結果だ。
ますます肥大化する電磁波により、輝きを増し続けるオーロラ。そのオーロラから数多の電磁波がエリカの頭部に降り注ぎ、エリカは悲鳴を上げる暇も無く意識を断たれた。
それどころか一瞬にして、エリカの肉体は膨大な熱量によって破壊され、光を放って消滅してしまったのだ。だが、エリカ自身の意識であるエネルギーはオーロラと一体となり、天上において一つの存在に集約される。俺は強烈な光の中心に、何者かが出現した事を感知した。
果たしてエリカは死んだのか?
天地を貫く光の矢が、メフィストフェレスが生み出した炎の塊を貫き消滅させた。
視界が戻り、俺の目の前には一人の女がいた。
輝きを放つ金色の髪の毛が夜風に棚引く。
白銀の光を放つ鎧を身に纏い、手には西洋式の広刃の剣と円形の楯を携えた姿。こちらを振り向いたその顔を見て、俺は自分の認識が確かな事を確認した。
「――ここに契約は完了しました。貴方の勇気に敬意を表し、勇者と認めます」
一体、何を言っているのか――しかしその声は、確かにエリカと同一であった。


第一話・女神降臨