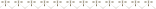Sick City
第一章・異形胎動
「う〜ん、あたし的には一番盛り上がったけどなぁ。」
日曜の夜中二時過ぎ。俺は隣に並んで歩いている女、神足飛鳥と夜道を歩いていた。
白いデニムのブルゾンに黒のUネックのインナー、薄いピンクっぽい紫色のウォッシュカラージーンズと黒いレザースニーカーという活動的な服を着ており、細面で目鼻立ちははっきりとしながらもすっきりとした印象で、髪形は栗色の柔らかそうな長い髪の後ろ半分程をアップした様な形だ。
「あれは下手にいじらなかったのが正解だったな。」
俺達は知り合いの主催しているクラブイベントで遊んできたのだが、なんとか終電で地元の鎌鍬駅まで帰ってきたのだった。
「オリジナルのヴォーカルを殺さなかったのはいいね」
「神足は歌モノが好きだからな」
俺は友達とこうして時々、クラブやライブハウスに行っては夜中に帰ってくるという事があり、帰り道ではこうやって、その日の感想などを言い合ったりしている。
「21時スタートで1時まで遊んでこの時間か〜。誰かに見られたりしたら大変かな」
こちらを流し目で見て、意地の悪そうな笑みを浮かべる。この神足飛鳥と言う女は同級生であり、学校では洋楽同好会と言う同好会で、一緒にバンド活動をしている。
「それより、明日は練習だから気合い入れていかないと。なんて言っても自分の詞を、自分で歌うんだし」
「去年の学祭では、俺の詞で歌ってたからな……やはり自分の言葉を、自分の声で歌った方がいいだろ」
そんなやり取りを交わしながら、神足が加入してきた時の事を思い浮かべる。あれは去年の秋の事で、学祭の準備に大忙しだった時期だ。始めは普段練習に使っている音楽準備室に遊びに来ていただけだったが、一週間もすれば自然と興味から歌わせてみた訳で、神足がなかなかの美声の持ち主である事が判明して、そのまま学祭ライヴで歌わせてみたのだ。
「あたしが入る前は内向的なバンドだったのに、いきなりラブソングに方向性変えさせちゃった訳で。後悔してない?」
「別にそんな事は無いな。歌う本人が一番歌いたい事を歌うのが一番だ。それに、むしろ方向性としては前向きになった訳だし、どうやら周りからのウケはいいみたいだから」
「確かに以前は、あまり目立たなかったもんね。あたしもあんた達がバンドやってんの知らなかったんだよなぁ」
俺達のやってるのはジャンルで言えばサイケデリックなノイズ系のバンド、というのが一番近い。実際にはベーシストがインダストリアル系が好きだったり、ドラムスがエレクトロニカ系だったりして特定のジャンルにぴったりと当てはまる訳では無い。
ロックバンドなんてものは、既に殆どのギターリフは出尽くしてしまっている訳で、なんとかオリジナルでやっていこうとするならば、自然とテクノロジーに頼らなくてはならない時代だ。ただ全てに共通するのは洋楽同好会だけあって、楽曲の全てが英詞だという事だ。
とは言っても、まだ持ち曲は20曲程度しか無い。それでもライブをやる位の曲数があるので、まだ神足が加入していなかった頃から、地元のライブハウスに出演もしているのだ。
そうこうしてる間に脇道に入り、道は坂下から坂を登って山の上の住宅街へと続いている。丁度坂の中間地点近辺には、幸明寺と言う寺の入り口がある。この寺は普通の寺とは大分趣が異なっており、寺の境内はかなり大きくて公園の様になっている。
山の中腹で見晴らしも良く、他の寺が管理している為か深夜になると無人になるので近所の悪ガキの溜まり場になっていたりする。この寺の門前で道が別れており、俺と神足はいつもそこで別れる。
「じゃあまた明日ね。おやすみ〜」
「ああ、じゃあな」
神足の住むマンションはここから歩いて三分程度なので、一人歩きでも問題は無い。明日と言うか既に今日なのだが、明日の部活での曲作りについて考えながら、家路を急ごうと足を踏み出す。
「?」
だがその足は、一歩進んだところで止まる。
何か違和感を感じる。
バツン!!
突如響き渡る轟音。何が起こったのか、俺はそれを確かめるつもりで、寺の門前から中を覗いた。
俺の目に映ったものは、収縮していく残光であった。その光の不自然さに吊られる様に中に入った。
境内に入ると静寂に包まれた、春の終わりの少しひんやりとした空気が出迎えてくれる。いくつもの桜の木は、既に花が散ってからかなり経っており、今は新緑で覆われている。所々に水銀灯が白い灯を灯しており、いくつかの遊具が、暗がりに浮かび上がっている。
こうして眺めると、特に何か変わったところは見受けられない。だが足元に散らばったガラス片を見て、一つの異変を知った。
水銀灯が――破裂しているのだ。
これだけなら、以前から壊れていたのだろうと判断してしまうだろう。だがこの水銀灯は、先程までちゃんと機能していたのだ。水銀灯から熱量を感じるのだ。
先程の閃光、そして爆発。
これらを繋げると、大きなエネルギーによって引き起された爆発の電磁波の干渉を受けて、水銀灯に封入されている水銀蒸気に掛かるアーク放電の電圧が跳ね上がり、過負荷によってガラス管が破裂してしまったのでは無いか、と推測が可能なのだ。
雷などが頻発すると、この手の発光原理の照明器具は著しく寿命が短くなる。
先程の爆発の光量を考えれば、頷ける話である。それにしても自然発生する様な事象が起きている筈も無いので、何か作為的なものを感じずにはいられない。
その場に佇んで周囲を注意深く観察する。きっと何かある筈だ。
「……う」
思わず声を上げそうになった。丁度桜の木の根元に、人がうつ伏せに倒れていた。それだけなら声を上げる程の事でも無い訳だが、俺には事の重大さが判ってしまった。
――死に掛かっているのだ。
「いったい何があったんだ」
俺は急いで駆け寄って、その身体を抱き起こした。その人間は男で、金髪の明らかに欧米人であると判った。じっくりと観察すると、左胸に大きな穴が開いていた。左胸から地面におびただしい量の血液が流れ出ており、既に致命傷を負っていた。
背中から流れた血は多くないので、おそらくは背部から、何か太いモノが貫通したのでは無いかと考えられる。俺はこの男が、最早助からないと確信していた。
「この指輪を頼む――」
俺に気付いた男が最後の力を振り絞って俺の手に何かを握らせる。そして事切れた。
「……どうしろってんだ」
俺は男を地面にそっと横たえ、立ち上がって手に握らされたものを見る。
それは指輪だった。
月光に照らされて質素な輝きを放つ銀色の指輪に興味を引かれ、俺は不味いと思いながらも手に取るのを我慢出来なかった。指輪はオーソドックスな形状をしていたが、表面に刻まれた文字の様なものが印象的であった。それがどんな言語なのか判らなかったし、或いは文字では無いのかも知れないが、俺には何か原始的なシンボルに見えた。
俺は指輪を握ったままで死体を改めて眺め、辺りに漂う鉄分臭さに辟易しつつ、じっくり観察した。まず、男の歳はまだ若く、二十代だろうと思われる。見開かれた目の色は、エメラルドの様な緑がかった青で、髪色はプラチナブロンド。
もし先程の爆発音と閃光が、この男の死に関係があるとして、一体どの様な事態が発生していたのか理解に苦しむ。そうやってしばらく観察を続けていたが、急に周辺の気温が下った様に感じた。
錯覚では無い。
気温が数度変わったくらいの変化では無く、いきなり十数度も低下したらしく、一瞬肌寒さを感じた。しかし今は春、夜とは言え、10度半ばくらいはある訳で、明らかに不自然な現象だった。
それでも、そういった気温の急激な低下を引き起したのは、周囲数十メートルの範囲だったらしく、みるみる内に元の気温を取り戻していく。
それよりも、俺の感覚域は明らかなエネルギー反応を感知していた。ある時から俺には、この世界を形作る大元たるエネルギーの流れを感じる事が出来るようになっていた。
崎守の家に代々伝わる秘伝の剣術、天仰理念流に伝えられる極意『心眼』の境地。五感を超える感覚の眼が、電力や重力、果ては物質を構成する素粒子とその運動エネルギーすら感知するのだ。それは、全ての力を見切る事が可能であるという事。
しかし、そんな俺でもこのようなエネルギーの捉え方は初めての事だった。
常人には感じる事の出来ない感覚。
この世界に満ちるエネルギーが何か意図を以て収束しつつあり、それはやがて強いエネルギーを内包した未知の存在の出現を予感させた。
例えるならば、雷の発生の真逆。
雷の発生する条件と言えば、まず雲に含まれる細かい塵が大気との摩擦を起こして帯電現象を起こし、それがやがて凄まじい程の電圧を有して雲と大地が互いにプラス層とマイナス層という関係を持ち、その間で放電する。それぞれの物質的な干渉によって電気と言うエネルギーが発生する流れ。
しかし今、俺の身の回りで起こっている現象は全くの逆であり、まずエネルギーがあり、それが集まって物質的な干渉を引き起そうとしているのだ。つまり――俺の目前に、何かが出現しようとしている。
それに伴って発生する放電現象。所々でスパークする雷球。雷球の接触によって四散する木々、鉄柵、それに地面。
俺は咄嗟に桜の木の影に隠れて身を守る。そして、視界を埋め尽くす程の閃光。白む視界の中で視覚による判別は難しいが、五感とは違った感覚によって、この世界に新たな生命体が表れた事を知覚した。
突如として周囲のエネルギーの有り様が安定し、静寂が訪れる。しかしその静寂を打ち破る様な、獣の如き咆哮。桜の木より身を晒し、回復した視覚に目前の状況が映る。
そこにいたモノ――それは何かの冗談かと思うしか無い様なモノだった。
隆々たる筋肉を持つ四肢、黒光りする全身。2メートルを軽く超える巨体から沸き上がる蒸気。まるで何かの動物の頭蓋の様な、二本の角を持つ白磁の様な頭部。そこに浮かぶ顔はまるで髑髏。空ろに見える二つの窪みから、赤く光る目が俺を見据える。
「――ッ!!」
下顎から突き出た二つの巨大な牙がゆっくりと動き、大きな口から獣の呻きを漏らし、右腕がゆっくりと持ち上がる。俺は我が身の危険を感じて、咄嗟に後方に飛び退いた。
そこへ振り降ろされる剛腕。何が何だか判らないが、ともかく命を狙われている事だけは判る。俺の胴回り程もある腕をよく見ると、下腕部から指先まで赤黒い外骨格の様なもので覆われており、指先には大きな爪がある事に気付いた。
もし、あのまま避ける事無く身を晒したままであったなら、俺は確実に命を落としていた。それを実感して恐怖を感じる。しかしそんな俺の事など構わず、寧ろそれが引き金となったのか、得体の知れない化け物は瞬時に間合いを詰めて今度は左腕を振り上げていた。
「――速いッ!!」
蹴り上げた大地から、舞い上がる土煙が今頃になって背後に見え、化け物の人間離れした爆発的な瞬発力を感じさせる。俺の視界いっぱいに広がる黒い巨体に圧倒され、俺の思考は完全に止まっていた。
それは、俺の中で時間が一瞬止まっていたかの様な感覚だった。次に感じたのは、まるでスローモーションの様にゆっくりと迫る、月光を反射する巨大な爪。その瞬間、まるでデジャヴの様に別の映像が脳裏に浮かんだ。
記憶の断片。
巨大な爪を濡らす赤い血。
大地に倒れた二つの死体。
俺の右側から襲いかかってくる爪。
ならば化け物の左側面に回り込む様にして、まず左足を斜め前に進め、次いで右足を背後から反転させ、身体をぐるりと回転させつつ移動する。しかし俺の動きよりも早く、化け物の爪は俺の身体に到達していた。
身体全体を衝撃が走る――が、ふと我に返って無傷である事を感じ、今の俺は化け物の爪を完全に回避した事を知った。
「……何だ、今のは」
曖昧とした記憶に疑問を抱いたが、それによって恐怖心はかなり和らいでいた。一方の化け物は攻撃が躱された事で怒りを感じているのか、再び咆哮を辺りに轟かせて両腕を振りかぶった。
そこで初めて、俺は化け物から溢れるエネルギーの有り方を感知した。
視えない泉から、絶えず流れ込む水流。
普通の人間には触れる事の出来ない領域に身を置いている。
そんな者は人ではない。
――神か、悪魔か。
俺の感覚は、今や視覚に頼らずに相手の一挙手一投足を捉える事を可能としていた。昔の剣豪は気配で敵を察知したと言われるが、まさに同じ事である。
此れ即ち『心眼』と言う。
今まで漠然と感じていた感覚が明確となった事によって、俺の中で恐怖は消え、感情は落ち着いて平坦となる。
化け物の両腕が振り降ろされ、俺は目を閉じて明確となった感覚に集中する。振り降ろされる両腕のスピードは常人と比較するならば、およそ倍以上のものだ。もし目に頼るなら、視覚情報が脳へと伝達され、それを処理して理解するまでの僅かの時間が存在する。
だが『心眼』を可能とするのは脳内ネットワーク、つまりシナプスの結合によって専用回路が形作られ、あくまで脳内処理による感覚器官と言える。
判りやすく表現するならば、それはまさしくコンピューターのハードウェアの仕組みに近く、入力用のデバイスから情報をインプットしてCPUで処理するまでには伝送経路が存在する。
しかしCPUのクロック周波数よりも伝送経路、即ち内部バスのバスクロック周波数は速度的に数段劣るものであり、それは人間の脳内ネットワークの電気信号の伝送速度と、脊髄の中枢神経から身体中の神経へと伝わる電気信号の伝送速度の比較も同じ事が言える。
つまり、視覚などに頼るよりも『心眼』によって得られる情報の伝送速度の方が数段早く、今まさに振り降ろされている化け物の両腕の速度は目に頼っていた第一撃目よりも数段遅く感じられるのだ。
『心眼』によって得られるのはそれだけでは無く、その本質は人が見る事の出来ない様々なエネルギーを捉える事にある。
例えば光というものは波長であり、人の目に映る波長には下限もあれば上限もある。だが実際には波長、即ち周波数には人間が捉える事の出来ない領域があるのだ。
この様に、世界に溢れるエネルギーは人間の理解を遥かに上回るものであり、知覚出来ないものを理解しようとしても本質的には不可能と言える。だが脳内において、情報のやり取りに使われるのは電気信号である。と言うよりは、電気こそ情報である。
即ち電気はエネルギーであり、エネルギーは情報でもあるのだ。コンピューターの例えの様に、情報の処理がデバイスに頼らなくなって一つの回路で行われる様になればなるほど、つまり集積化が進んでいけばより効率化に繋がり、今まで処理の追い付かなかった膨大な情報を処理する余裕が生まれるのだ。
化け物の両腕が俺の頭上に迫る。
それを右足を後方へ大きく踏込んで重心を右足へと移す。俺の身体の中心がたったそれだけの動作で大きく後ろへ移った事により、化け物の両腕は空振りに終わる。
それと同時に、俺は自身の両の掌を腰溜めにし、今度は残ったままの左足へと重心を移す。その動作に伴って、両腕を押し出して化け物の両胸に掌を押し当てる。
ズシン。
始点となった右足の爪先から、各間接の捻り運動が重心の移動と連動して掌に伝わる。その衝撃は反作用によって何乗にも膨れ上がって、化け物の両胸から全身へと浸透する。浸透した衝撃は全身で吸収しきれずに背後へと突き抜け、遅れて周囲の空間を伝播する。
バツン!!
大気に伝播した衝撃によって背後で弾けた様な音が響いた。
「――グガッ!?」
化け物の咽喉が震えて、蛙の鳴き声の様な呻きが漏れる。その口から呻き声と共に、鮮血が弾けて化け物の胸元を濡らす。
ぐらりと前へ傾く身体。
俺は即座に後ろへ退き、化け物はうつ伏せに地面に伏した。
これぞ天仰理念流絶技・双捻掌。
我が家は祖父を筆頭として、代々剣術と体術を併せ持った流派『天仰理念流』を伝承している『崎守』の名を持つ一族の末裔であり、体術においては『徹し』と言われる体内で練り上げた衝撃力だけを敵の体内へ伝播させる技法を操る。
敵がどれほどの巨体を持とうとも、衝撃の反作用によって肉体の質量に比例して衝撃力も増大する。それはまるで水面に波紋が広がる様なものであり、内に閉じた肉体内部であればほぼ全身に衝撃は伝わり、それが肉の壁たる筋肉によって再び反射して内部へ還り、反作用を繰り返す。
肉の限界を超え、外側へと弾けるまで。
そしてエネルギーは、エネルギーを打ち消す。
もし霊なるものがこの世に存在するとして、その正体が本質的にエネルギーと同質であると言えるなら、この様な打撃を介して発生した衝撃力=エネルギーによって、霊=エネルギーは霧散するであろう。ただし、霊なるものが肉体に憑依していると仮定するならばだが。
そしてこの化け物こそ本質はエネルギーにあり、エネルギーこそ情報でもあるとするならば、この化け物はエネルギー生命と言い換える事も可能であり、霊もエネルギーに含まれる情報によるものだとするなら、今の衝撃は化け物の本質を攻撃した事になる。
何故この様な考察が必要かと言うと、まさしく目の前で、化け物の肉体が突如として霧散したのだ。化け物が出現した現象は、この世の摂理とは逆のプロセスだったのだ。
エネルギーが先にあり、後から物質化を成した。本来の死とは物質たる肉体の死であり、それによって脳の機能が停止して脳内のエネルギーのやりとりが無くなってエネルギー的にも死を迎える。
だがこの化け物が、エネルギー=情報の塊であったとするならば、エネルギーが殺された事によって肉体を維持出来ずに霧散したと考えられる。本当の所はエネルギーが死ぬ事など無いのだが、エネルギーに含まれていた情報が整合性を失い、情報体としての死があるので『エネルギーの死』と揶揄した。
肉体が霧散したという事は、肉体を情報によって構成していたものの、その情報が失われた事によって元々が塵の集合体だった物質が原子構成を解かれてしまった、とも考えられる。情報を維持出来る程の強度を持ったエネルギーの塊が一体何処から表れたのか、それは判らない。
ただ一つだけ判った事は、明らかにこの世のものでは無いという事だ。この世界は物質、即ち物質の最小構成単位である分子とその運動であるエネルギーによって出来ている。
先に物質が存在し、それによってエネルギーが生まれるのだ。しかしこの化け物の存在はエネルギーが先にあり、そのエネルギーは何処からか滲み出る様に集まって一つの意志を成したのだ。

警察署での事情聴取でかなりの時間を取られ、俺への疑いは一旦取り下げられた。あの後、さすがに死体を放置したままで帰る訳にもいかず、警察に通報をして任意同行を求められたのだ。担当の刑事に化け物の事は伏せつつ、いきなり何者かに襲われたが、顔は見ていないと説明した。
夜の暗がりで顔や姿形などの特徴が殆ど判別が付かなくて当然であるし、被害者の胸にある傷跡に対して、担当刑事の推測が『太い鉄の棒によるもの』とした為に、容疑者に上げられるのは主に建築関係者辺りが妥当だとされたのが最大の理由であった。
ただ水銀灯が破裂していたり、殺傷方法が突飛過ぎてどうやって鉄の棒を貫通させたのか、しかも相当な力を必要とする筈だ、などと刑事達の頭を悩ませていた。俺が未成年者だと知った刑事の一人がパトカーで家まで送ってくれるらしく、廊下の腰掛けに座って待っていた。
そんな俺の前を、若い刑事に連れられた一人の女が通った。プラチナブロンドの長い髪と、エメラルドの様な瞳。おそらくは被害者の家族だろう。ならば身元が判明したと言う事だが、身分を特定出来る物でも所持していたのだろう。
擦れ違い様、何故か俺の目の前で足を止めた女と目が合った。身長はやはり日本人に比べれば高く、服装は胸元から網紐が交差したノースリーブのシャツに、膝上までタイトでその下から二本のプリーツによって幅広になっているスカート、足元はネックストラップ付きのサンダルと比較的綺麗目の格好が女性らしさを演出している。
剥き出しになった肩から腕まで、シミ一つ無い白い肌が印象的であり、顔立ちも完璧なまでに整っており、まるで高い芸術的価値を持った彫刻の様であった。俺は目を合わせたまま動けずに、刑事に促されて通路の奥へ消えていく後ろ姿をただ見送っただけだった。
女の顔に浮かぶ表情は不安や哀しみに染まっており、目元も少し赤く見えたのが印象に残った。
少し経って、奥の部屋から初老の刑事が現れた。
「おう、待たせて悪かったな」
どうやら他の刑事に任せて、俺を送る方を優先した様だ。
「いえ、こちらこそわざわざすんません」
刑事に返事をして立ち上がる。
「まぁお前さんもこれに懲りて、夜中まで遊ぶんじゃないぞ」
「確かに懲りましたよ」
未成年者の夜遊びを刑事が諌めるのは当然なのだが、俺が遅い時間にあの道を通ったからこそ事件が早期に発覚したのであって、なんとなく損をした気になってしまう。
釈然としないモノを感じながら刑事の後ろを歩く。しかし俺は突然足を止め、刑事に話し掛けた。
「……刑事さん、自分の身は自分で守ってくれ」
突然そんな事を言っても、理解出来ないだろう。案の定、刑事は顔を顰めて俺の顔をまじまじと見てきた。
「……何を薮から棒に言いやがんだ――って、おい!」
俺は刑事の言葉が終わるのを待たずに、回れ右をして廊下を逆方向へ向かって一気に駆け出した。
「……ったく、最近の若いヤツの考えてる事ぁわかんねぇなぁ」
刑事の呟きが俺の背中に向かって投げ掛けられたのを感じたが、俺はそれを無視して奥の扉へと急ぐ。先程、若い刑事に連れられた外人の女が入っていったと思われる扉。その扉の先で、今頃は被害者の遺体と対面している筈である。
しかし、俺の『心眼』が捉えている不穏なエネルギーの蠢きは、その扉の先にあると思われる地下から感じていた。警察署で地下と言えば霊安室がある場所だと考えられるので、先程の外人女がいる筈であり、『心眼』でその存在を感じていた。俺が感じているエネルギーは、寺に現れたあの化け物と全く同じ質のものだ。
そしてもし、あの化け物が被害者を殺害した犯人だったとすれば、被害者の親族であるあの女も命を狙われており、今まさに化け物がこの世に現れようとしているのでは無いだろうか。正体不明の化け物に命を狙われる理由など判り様も無い訳だが、俺にこの状況を変えられる力があり、その機会もあるのであれば、見過ごす事は出来ない。
「――間に合えッ!!」
扉を開けるとそこは地下へと続く階段になっており、4m程で地下の床が見える。いちいち階段を一段一段駆け降りるのは面倒なので、一気に飛び降りる。足の裏に軽い衝撃を感じつつ、膝を充分に落としてクッションを作って衝撃を緩和する。
床に手を付けて前方を見ると、地下の通路の両側に扉がいくつか見え、通路の一番奥の突き当たりにも扉があるのが確認出来る。『心眼』に映るエネルギーの流れは、全て突き当たりの扉に集中している。思い切り床を蹴り、一歩の踏み込みのみで奥の扉の前へ到達する。
この間、僅かに3秒。
ドアノブに手を掛けて扉を一気に開け放つ。
「グガァアアッ!!」
俺が中に踏込んだのと、獣の如き咆哮が轟いたのがほぼ同時であった。
「――あ」
俺を襲った時と同じ様に、何処からともなく霊安室に現れた化け物を目前に、あの女が立ち竦んでいた。
窓一つ無い霊安室の真ん中に白いシーツに包まれた遺体らしきものが見え、その横に立っていた女のすぐ目の前に化け物は出現した。俺が立っているのは外の通路に面したドアの辺りで、女は背中を向けているので顔までは確認出来ない。
だが、恐怖によって膝に震えが見られ、動けないでいる女に構う事無く化け物の太い腕が振り上げられる。ビュンと風を切る様な音が鳴る。どすっと鈍い衝撃と、暖かい何かに自分の身体が包まれている事に気付いた女が顔を後ろへ向けた。
「あの、あなたは?」
女は以外に流暢な日本語で、そう訪ねてきた。俺は咄嗟に女の身体を抱え、横に跳んで化け物の一撃を躱した。だが、勢いが付き過ぎて壁に思いっきり体当たりをかました格好になってしまい、鈍い痛みが肩口に走った。
「説明は後回しだ。とにかく逃げるんだよ!」
俺は女の手を取って立ち上がらせ、一歩前に出て女を庇う様にして化け物と対峙する。
「グァアアアアア!!!」
攻撃を躱された化け物は激昂し、両腕を大きく拡げた。3m近い巨躯がその人間の胴回り程もあろうかという二の腕を目一杯拡げると、そのリーチの広さに改めて驚いてしまう。果たして人類の歴史上、此程の巨体を持った敵を相手にした人間が存在するのだろうか。
幸いにして部屋の出入り口はこちらの後ろにあり、女だけでも逃がす事が出来そうだ。しかし、ここで俺が踏み止まって化け物を相手し続けるのは得策では無いだろう。前回は屋外での戦いだった為、こちらの機動力を最大限に生かす事が出来たが、今回の様な屋内での戦いでは限られた空間内でこれだけの攻撃範囲を持った敵に対し、どれだけ有効な手を打てるか疑問だ。
「きゃあッ!!」
化け物の咆哮は周囲の空間をびりびりと震わせ、俺の背に隠れた女は両手で耳を抑えて悲鳴を上げた。それでもすぐに逃げ出さないのを見ると、恐慌に我を忘れている訳では無く、それなりに肝が据わっている様だ。その時、警察署全体に奇妙な空気感が漂っている事に気付いた。
「……?」
まず化け物の持つ、強烈なプレッシャーが起こす大気の振動が、警察署の外に対して伝わっていない。まるで署内だけが、世間から隔離されたかの様な状態に陥っている。それから、署内にいるであろう数十人の警察官達の生命活動が希薄になっている。
わずかに感じるエネルギーから生きている事は判るが、誰一人として動いている者はいない。
――まさか眠っている?
先程まで俺と共にいた年配の刑事も、こちらを追いかけてきていた筈だったが、今は廊下で動かずにいる。『心眼』によって周辺500m程の範囲ならば、例えば人間の体内の各種化学反応や動作によって起こる空気の動きや地面の振動、体重による重力の差など、多岐に渡るエネルギー活動を感知する事が出来る。あくまで『個』を認識する事によって得られる情報なので、それぞれを意識しなければ感知は出来ない。
その情報を受け取っても理解出来るだけの脳の処理能力がなくては意味が無いのだが、俺は現時点で個々の人間の情報をその時々で段階的に上げたり下げたりして『選択と集中』する事が可能になっている。例えば、俺の後ろの女は現時点で敵では無いのだから余計な情報はシャットアウトし、俺の目の前の化け物は明らかに敵なのだから得られる情報の全てを感知している。対して、500m範囲に存在している個々の人間については生命活動と動作についてだけ把握している。
それから範囲内で自然現象的に異常が無いか、例えば火事になったり地震になったり雨が降るなどの環境の変化や、毒ガスだとか放射能汚染などの大量殺傷兵器などの使用なども感知可能な筈だ。この空間を隔離した様な状態をどうやって作り出したのか、一体何者が関わっているのかが判らない。『心眼』で判るのはあくまでこの三次元宇宙の中の『この平行世界』だけであり、もしも全くの外界から関与が可能であるならば、『そこ』にいる者の存在までは感知出来ない。
だが『こちら側』に対して外部から関与があった事は、状況から推測が出来る。こんな現象が『こちら側』で起こる筈は無く、それが可能となるには、三次元空間の法則を超えた力が無くては不可能だと考えられるからだ。その理由は、この建物全体の自重から発生する重力が、本来この世界の内側だけで無く外側に対しても僅かに働いて影響を与え合っているのだが、その外側への働きがねじ曲がっている様に感じるからだ。
「……マズいな」
俺は状況が最悪である事を悟り、思わず呟きを漏らした。
「……グルルルルルル」
化け物は咆哮を上げた後は己の優位を悟っているのか、低い唸り声で威嚇をするだけで動きを見せない。おそらくはこの建物の外へ出る事は出来ない。だからこその余裕だろう。
俺の漏らした呟きは女の耳に入ったらしく、こちらを伺う様にして遠慮がちに尋ねてきた。
「あの、これは」
とは言っても恐怖が未だ強く、たったそれだけしか声にする事が出来なかった様だ。それでも答えを求められている気がしたので、簡潔な説明をしてやる。
「逃げろと言ったけどな、どうも慎重に行動した方がいいみたいだ」
「それはどういう事――」
女が理由を聞こうとした時、突如として化け物が動きを見せた。
「……htjとおsgsjsp」
拡げた両腕はそのままに、何か理解不能な言葉の様なモノを呟き始める。
「……ッ!?」
何か雑音の様な音が脳を直接刺激する。それによって意識が混濁し始め、身体に力が入らずに片膝を床に付かざるを得ない。
化け物の口から漏れる呟きは雑音を生み、その雑音は人間が聞き取る事の出来ない波長を生んでいる。そこに上乗せされている情報が人間の脳に何か命令をしており、結果から推察すれば人間の意識を奪う効力を持っているらしい。
「うっ――」
後ろの女も意識を奪われ、強烈な眩暈のせいか両手両膝を床に付けて四つん這いになっている。意識が朦朧とする中で、俺はある閃きを覚えた。それは何時の話だったか、俺に天仰理念流を叩き込んだ祖父の言葉であった。
己を殺せ――さすれば無明無情、極み一つ、ただそこにあるのみ。
――己を殺す。
口で言うは易し、行うは難し。
だが絶望的状況が既に死を予感させているからか、ある種の開き直りによって、それが意味する所が己の『個』を殺す事であると理解出来た。
そんな事は、今まで不可能だと思っていた。しかし『心眼』に目覚めて『個』を認識する事が可能になった今、逆に己の『個』もまた認識が明快になっている。
『個』というものは、エネルギーに含まれる情報の集合体の事だ。通常、それは脳の化学反応で生まれ、肉体的に維持、この世界に繋ぎ止められている。
しかし肉体的な死を迎え、エネルギーは霧散し、情報もやがて希薄化し、世界に還元される。だが、より強く想う事からエネルギーとしての情報は強化され、残留思念として一つの形を維持する事がある。殆どの情報は失われるが、明快かつ単純化された思考は時に肉体を離れてもなお、存続を可能とする。
それこそ幽体離脱と呼ばれる現象である。脳と言う肉体的なメモリ空間がある以上は意識という情報が離脱して情報が大幅に欠損しても、再び意識が戻れば情報も復元されるというロジックである。
もしも、今だけ必要のある思考だけをシンプルに明確化出来るのならば、このまま意識を失う事こそ寧ろ必要である。
それは情報化の作業だ。
たった一つの事だけを考える。
それは具体的な想いでは無く、もっと漠然とした原理原則。俺という人間が持つ思考をワンパッケージ化し、体現する事である。
――自然であれ。
人間は人間が構成する社会の上に生きているが、しかし本質的には社会それ以前に自然の上に成り立つものだ。それを多くの人は忘れており、社会という一つの『群体』に寄り添ってしまっている。だが本来、人はそれぞれ一つの『個』であり、『個』は自然と向き直る事でより明確化される。
この状況の中、それでも生きていく上でさらに己の『個』を殺すのであれば、それは自然と一体となる事だ。
俺は自然を体現する。
自然は考えない。
だからこそ、もう考える事はやめる。
――そして意識を失った。


第一話・女神降臨