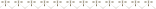Sick City
第二章・能力開花
俯瞰で見る事にしよう。
ここで俺の意識は途絶した筈であり、本来ならばこうして状況を把握出来る立場では無い。だが、それは主観が途切れただけの話であり、客観でモノを語る事は出来る。
呟きによって意識を失った俺達を見下し、化け物は牙の突き出した大きな口をカタカタと鳴らして笑った。そうしてゆっくりと右腕を振り上げ、ややあって俺の身体を横薙ぎにしようと降り降ろす。弧を描いた右腕が俺の身体を直撃しようとした刹那、床に片膝を付いて首を下にして意識を失っていた筈の俺は、瞬時に跳躍していた。
「グガッ!?」
ベリーロール気味に身体を捻りつつ、回転して着地した俺を見て、化け物は一瞬何が起こったのか理解が追い付かずに呆けていた。その時には既に雑音の効力から完全に意識は復帰し、俺は化け物を見据えて啖呵を切った。
「どうしたよ。そんな小細工でどうにかなる相手じゃないって事だよ」
それで状況を理解したのか、化け物は再び咆哮を上げて襲いかかってきた。
「グガァアアアアアアアア!!!!」
最早小細工は通用しないと考えたか、右腕の爪で俺の身体を貫こうと貫手を繰り出してくる。さらに右腕に化け物の内包する強大なエネルギーが集中し、突如として腕全体が白熱化、前方に対して爆発を伴う。
おそらくはこの力こそが、被害者の命を奪ったものだろう。被害者の左胸にあった穴の大きさと化け物の腕の太さは一致しないが、例えば指先一本で触れるだけで人間の身体に穴を開ける事も可能だと思われ、その場合ならば被害者の傷跡に極めて類似した結果になるだろう。
俺の後ろでは女が意識を失って床に倒れており、これなら俺が回避しても女が巻き添えになる様な事は無い。だが腕を中心として爆発力が周囲に発生している為、紙一重で躱すのでは腕一本くらいは吹っ飛ばされ兼ねない。限られた空間の中でこの化け物に決定的な隙があるとするならば、それは足元しか無い。
俺の上半身から上の殆どの空間を爆発力によって封殺しているが、化け物自体の背丈がかなりの高さになる為に、床上90センチ程の空間に関してはまるでガラ空きとなっている。これはあの女が床に倒れている事で、女自身は安全であると判断した時に気付いていた事であった。
俺は迫る爆炎を前屈みに躱し、そのまま前方に倒れつつ回転、背中から床に接地して滑る様に化け物の足元へ滑り込んだ。化け物は自身の攻撃が躱された事を知りつつも、爆発力の放出によって大きな隙を作ってしまった。
後ろの壁が爆発力によって破砕し、まるでバックドラフト現象の様にコンクリート片を巻き込みながら爆炎と爆風が隣の部屋へと突き抜けていく。右足からスライディングの要領で化け物まであと一歩まで間合いを詰め、そこで折り畳んだ左足を起点に立ち上がり、重心を右足へと移す事で攻撃態勢が整った。
半歩間合いを詰めて化け物の右脇腹に右の掌を接触させ、丁度左半身の体勢から左足を踏込んで右半身へ移行、接触した右の掌の上からさらに左の掌を押し当て、衝撃が化け物の肉体に伝播した。
これぞ天仰理念流絶技・滑り合掌。
「グゲッ!?」
化け物はまるで蛙が車に潰された様な声を咽喉の奥から漏らし、一瞬で絶命していた。一つの個性を形作っていた化け物のエネルギーは霧散し、統率を失った肉体は消滅した。
「――ふぅ」
深く吸い込んだ息をゆっくりと吐き出した俺は、命のやり取りをしていた事を改めて実感して僅かに安堵していた。
しかし、安心するにはまだ早い。
未だ警察署は外界から隔離されたままであり、それは今の化け物とは別の存在が介入している可能性を示唆している。
後ろで倒れている女の事もある。
何の理由で化け物に命を狙われているのか知らないが、別の存在がいるとするならまだ命を狙われていると思われる。このままで良い訳が無いので、女を起こしてやる。
「ふっ!」
背中に回って両肩を抑え、一瞬だけ軽く衝撃を浸透させて気付けしてやった。
「――んっ」
意識を取り戻した女が呻き声を上げた。一瞬、何が起きたのか理解が追い付いていない様な呆けた顔をしていたが、すぐに自分の身の上に起こった事に思いが到った様で、ハッとした表情で後ろで膝立ちになっていた俺の顔を見返した。
「……あの、私いったい」
女はそこまで口に出したが、その先を続ける事は出来なかった。俺の背後、部屋の壁面に大きな穴が開いているのが目に映ったからだろう。女の視線の先を俺も同じく見やった。
「……あの化け物の仕業だよ」
その言葉を聞いて自分を襲った敵の姿が思い浮かんだのか、心の奥底から沸き上がる恐怖心を顔に滲ませながらも、そんな自分の感情を押し殺して俺の目を見返して口を開く。
「……アレはいったい何だったんですか?いえ、そんな事より、アレは何処へいったのですか?」
女のその気丈な振る舞いに感心しつつも、求められた説明に応えてやる。
「倒したよ」
過程を説明するのは難しいし、それを理解出来るかどうかも怪しい状態なので、簡潔に結果だけを答える。だが女は納得していないのか、さらに難しい顔をして尋ね返してきた。
「倒した、ってそんな簡単な話では」
しかし、またもや女の言葉は途中で終わってしまう。
――ズズズズズズ。
ゆっくりと地の底から這い上がってくる様にして、建物全体が振動しだした。
「……不味いな」
俺のその呟きを聞いた女は不可解さを感じたらしく、首を傾げた。
「日本が地震の多い国だという事は、充分知ってます」
外国人でありながらこれだけ流暢な日本語を操るのだから、それなりに長期間に渡って日本に滞在しているのだろう。自分は地震には慣れているから別段驚く事では無いと言いたいのだろうが、生憎とこれはただの地震では無い。
現段階においてこの警察署は建物自体の質量から生じる慣性力の働きを捩じ曲げられており、どうも空間ごと外界から隔離されている様な状況である。この地震は実際には隔離された空間自体の振動であり、これを行った者、或いは方法に限界があるのか、もうすぐ隔離が解除される前兆だと考えられる。
「とにかくここから離れよう」
説明しても理解出来る話では無いので外に出ようと勧めるが、女はどうも性格的に真面目な様で、その理由を問う。
「何故ですか?まだ刑事さんとのお話が済んでいませんので、ここから離れるのは遠慮したいのですが」
考えてみれば肉親が殺された訳で、話が済んでいないと言う事は、被害者との別れを済ませていないのかも知れない。しかし、それを考慮している時間は無い。
「……多分、アンタは命を狙われている」
俺の言葉は充分にショッキングなものであり、到底理解出来る話では無いだろう。女の顔は蒼ざめ、震える口でなんとか言葉を発した。
「……何故、私が」
心当たりが無い様だが、実際に命を狙われた以上は、その言葉は虚しく感じる。ここで遠慮をしても状況が変わる訳でも無く、俺は率直な意見を述べる。
「アンタ自身、理由が判らないならどうしようもないな。理由を考えるより、兎に角安全の確保が最優先だ。警察署内であんな化け物が襲ってきた以上は、警察を当てには出来ない。外に出るのがいいと思う」
敵対者が何を仕掛けてくるか判らない以上、いつまでも一つの場所に留まるのは危険だ。女も俺の意見に異論は無い様だが、何か釈然としないのか再び問い返す。
「……一体、貴方はどういう方なのですか?」
その疑問は当然考える事だろうが、それに対する明確な答えを俺は持っていない。
「言える事は、俺が第一発見者だって事くらいかな」
そこまで言って、俺はある事実をすっかり失念していた事を思い出した。ズボンのポケットに手を突っ込み、目的の物を取り出す。
「被害者の遺品だ。年齢的に考えて兄妹なんだろ?一応、アンタに渡しとく」
俺はそう言って彼女の手を取って、あの指輪を彼女の手に握らせた。
「……この指輪は、我が家に代々受け継がれている物です。兄が肌身離さず身に付けていたんです」
やはり被害者とは兄妹だった様だ。その目には涙が滲んでいる様に見えたが、俺は何も言わずに女が落ち着くのを待った。女はしばらく指輪を握り締めて目を瞑っていたが、気を取り直したのか、顔を上げて俺を見た。
「……もう大丈夫です」
その言葉を聞いた俺は、頷きを返してから霊安室の外の廊下に出た。そして女の方を振り返って手招きをしつつ、口を開いた。
「廊下は大丈夫だ」
女は俺の背中越しに、通路の奥の方を覗く様な形で側に来た。
「あの、貴方のお名前を教えて頂けませんか?」
控えめにそんな事を聞いてきたが、考えてみれば普通は名前くらいはお互いに聞くべきだろう。
「崎守零二。零二でいいよ。アンタは?」
「エリカ・シュタインメッツ。エリカと呼んで下さい」
エリカと名乗った女は、そう言って握手を求めてきた。
「――む」
日本人とは違う慣習に少々戸惑いを感じたが、応じるのが礼儀なのだろうから、素直に応じる事にした。呑気な事をしていられない状況下ではあるのだが、人と触れ合う事が安心感を与えたのか、エリカの顔から緊張感が薄れた様に感じた。そんな時、俺の超感覚域に新たなエネルギーの収束が感知された。
「来やがった」
「――え?」
俺の呟きが意味するところを理解出来ず、それでも不穏な空気は感じたのだろう。エリカは警戒感を露にして俺の背中に隠れた。エリカの身長は一般的な日本人女性と比べて高めで、おそらく170センチを少し上回る。それでも俺が182センチあるので、後ろに隠れる意味はある。
だが、今回はそれが裏目に出た。
敵が現れるとして常に前方とは限らず、今回は俺達の背後に、突如として出現したのだ。
「伏せろ!!」
俺は危険を察知して、エリカを床に押し倒した。
「きゃあッ!!」
突然背後に現れた大きな口が、凄まじいスピードを以て襲い掛かってくる。
いきなり押し倒されたエリカからは、その姿形は確認出来なかっただろう。
すぐに立ち上がって体勢を建て直した俺を、床に四つん這いの状態で見上げたエリカだったが、その視界に飛び込んできた光景を見て絶句していた。
「……グルルルルルゥ」
俺達の前方で、唸り声を響かせ立ち塞がったモノ。
「……犬?」
エリカの口から出た言葉通り、そこにいたのは巨大な犬だった。
しかし、ただの犬では無い。
全身は真っ黒な体毛で覆われ、瞳は爛々と紅い輝きを放ち、異様なオーラを全身から発散していた。俺の『心眼』では、犬にしては強大なエネルギーを有している為に外に漏れ出している様が判るが、普通の人間であろうエリカの目には、黒犬の全身を紫電が覆って時折スパークしているのが見えているだろう。
これは少々厄介だ。
と言うのも、黒犬の身体に接触しようものなら、たちまち感電してしまう事が予想されるからだ。
しかし、ここで引き下がる訳にはいかない。
逃げるとしても人間と犬では走力に決定的な差があり、ここで倒すしか生き残る術は無い。それにエリカの命を狙う黒幕がこの黒犬だとは到底考えられず、この先に待ちかまえているであろう本当の敵は、おそらくもっと手強い筈だ。
そう考えるとこの黒犬との対決で、こういったエネルギーによる干渉になんとかして対処しなくてはならない。今までの様に、『徹し』による接触打撃をする余地が無いのだ。
「グルァアア!!」
そんな俺の苦悩など、お構いなしで黒犬が襲い掛かってくる。巨大な顎門は俺の頭を丸ごと噛み砕ける程であり、黒犬の突撃を右斜めへ歩を進めつつ反転する事で、回り込みをしつつ回避する。軸をずらす形で躱したので場所を入れ替える事になり、黒犬と俺の間にエリカがぺたんと座り込んでいる格好になってしまった。
「ひっ!?」
エリカは小さな悲鳴を上げて身を竦ませたが、黒犬は俺の与えるプレッシャーの為に、今更そちらへ攻撃の意志を示すつもりは全く無い様だった。俺はと言うと、黒犬との擦れ違い様に紫電によって左肩に軽い火傷を負ってしまった。
感電による火傷というものは、人間の肉体が持つ電気抵抗の許容範囲を超える電圧によって、肉体が熱を持つ事で起こるものだ。しかし軽い電流なら人間の肉体を損傷する事無く流れる訳で、もし大きな電流を受け流す方法があるならば、損傷無く処理する事が出来るかも知れない。
そこで考えるのは、エネルギーは別のエネルギーへと変換出来るという事実。例えば、火力発電所などは石油を燃焼させて電気を取り出す訳で、火力という熱エネルギーから電気に変換出来る。
他にも風力発電や水力発電などもあり、そちらは風や水の運動エネルギーから電気に変換している訳だ。原子力発電所などは原子核の反応によって電気へ変換出来る訳で、そちらは核力と呼ばれる。
原理的に言えば物質の反応がエネルギーを生み、現在の科学技術は『熱』から電気へ変換する事を可能にしている。だがエネルギー保存の法則を元にして考えるならば、エネルギーとは何も熱や電気だけの話では無く、原子力発電の『核力』もあれば物質の質量が生む『重力』などが存在し、電気エネルギーの『電磁力』と併せて同列のものであり、その全てが相互に変換可能であるとの見方が定説である。
人間は己の体内でカロリーを燃焼してエネルギーとし、化学反応の連続で肉体の運動を可能としている。普通の人間はそれが全てであり、人間の肉体も基本的には己が生み出すエネルギーの上限が、処理の出来るエネルギーである筈で、外部の電気を入力して変換する為の仕組みが無いので感電する訳だ。
だがもし、そういった入力器官と変換器官が存在したらどうなのだろう。そして存在するとして、それはどこの器官なのか。人間が化学反応で電気エネルギーを変換し得る器官とはたった一つ、脳しか有り得ない。
全身を駆け巡る神経や、それこそ肉体全てを構成する細胞自体も微弱な電気が発生しているのだが、それは内部での処理の話であって、例えばマイクロ波を集めている航空管制のレーダー施設などではレーダー直下への人間の出入りというのは危険があるとされており、それはマイクロ波が与える脳への影響というものがあるかららしい。
人間の脳は頭蓋骨によって外部から守られているのだが、それを超える電磁波の影響を受けるのは確かな話であり、霊媒体質など普段見えないものが見えてしまうという現象は、情報体としてのエネルギーを脳が受け取る事によって起こる現象であり、それを考えると脳という器官こそ外部のエネルギーを処理する可能性を持っている器官なのだ。
考えてみれば人間の進化で一番発達した部位とは脳であり、もしこれから先も進化をするとするならば、やはり脳がその可能性を持っていると考えられる。
脳の中で情報を処理しているのはニューロンであり、シナプスが互いに結びつく事によって、それぞれの情報の関連性が構成されてより複雑化する。
『心眼』もニューロンの構成によって処理回路が形成された事によるものであり、例えば霊媒体質の人間の持つ回路がエネルギーの情報を処理する回路であるとして、他にも超能力などは入力回路こそ無いものの、力を形成する専用回路とそれを外部出力する回路だと言え、『心眼』とはあらゆるエネルギーを感知する回路と、それを理解する為のエンコーダーとデコーダーを持ったワンチップの専用超高速回路である。
それが形成される要因は、特定の理屈や肉体の動作をひたすら反復する事によって、余計な考えや動作が次第に省かれてシンプルになり、極めれば一つの行動原則として脳のニューロンが記憶する事で、それ専門に特化するからだ。
だが人間は例え脳であっても、食事によって得られた栄養素を元にしなくては何も出来ない。脳で大量の電気を処理するとしても、例えばブドウ糖など脳の活動に必要な栄養素が一体どれだけ必要になるのか見当も付かない程であり、現実として無理な話なのかも知れない。
しかしこんな話がある。
雷に打たれた人間が、無傷であったと言う話だ。たまたま状況が揃った事で無傷で済んだのだろうが、逆を言えば状況さえ揃えば感電を免れると言う事になる。まさか今の状況でそんな偶然が期待出来るとは思わないが、今の俺自身の力というものが常人の域を超えたものであると言う事が、ある可能性を感じさせる。
『心眼』はエネルギー感知能力であると同時に、それを可能としている要因として肥大化した時間の認識、空間の認識であり、物質の最小構成単位である分子の運動を認識するまでに至り、即ち宇宙の法則の全ての最小を体現する事にある。
それは情報分析能力の極みであり、人という個体が世界から独立した存在では無く、人間もまた世界の一部である事を改めて思い知る事となった。つまり、人間一人が持つ情報というエネルギーは、さらにこの宇宙の情報という名のエネルギーの一部であると言う事である。
対峙する黒犬との間合いはおよそ7メートル程。
その距離は黒犬にとっても俺にとっても、瞬時にして詰める事の出来る間合いであり、決定的な優劣は無い筈であった。しかし、目には見えない違いは確かにあり、それは黒犬の内包する力がこちらを圧倒する程の強大なものである事と、そして俺の『心眼』が認識する時間を測る尺度が、常人より桁外れに微細である事である。
膨大なエネルギーの爆発力を以て黒犬の後ろ脚が床を蹴り、目で捉えて認識する事すら難しい、圧倒的な突進で俺に襲い掛かる。
常人ならそれで終わりだ。
だが俺の脳をコンピューターのCPUに例えるならば、可変クロック速度と言われる技術の様に、必要に応じて認識する時間の尺度を変える事が出来、その他の情報を遮断して、一点に意識を集中する事で周囲の時間の流れが遅く感じる様になるのだ。
今の俺が捉える黒犬の動きは到って緩慢なものであり、まるでスローモーションの様に、その動きの一つ一つを完全に捉える事が出来る。そして身体中を覆う紫電は絶えず発生している訳では無く、規則的な間隔を空けて発生していると判る。
とは言え、その途切れる時の間隔に人間の動きが追い付ける訳では無く、さすがの俺でも電気より早く動ける筈は無い――が、黒犬は別だ。
その圧倒的な爆発力から生まれた突進速度は桁外れなものであり、黒犬の速度と、それでも常人を超える速度を持った俺の突進を合わせれば、電気の発生に割り込む形で接触をする事が出来る。そして俺の脳がこの瞬間に高速化していたのと同時に、肉体に走る神経の伝達速度にも変化が起こる。
周りの時間がゆっくりと進む中、俺の認識に合わせて俺の動きだけは通常の速度で動いている様に見える。己の劇的な変化に対し、あくまで一連の動作を反射で行っているので感情は追い付かない。
しかしほんの一瞬の間だけ、俺の肉体は脳内処理の速度に追随したのだ。俺は右足を斜めに進めつつ左足を右斜め後ろへと引き、黒犬の突進を躱す事に成功していた。黒犬の脇腹が俺の目の前を通り過ぎようとしていた瞬間、右の掌が捻りを加えてその脇腹へと叩き込まれる。
天仰理念流・砂浪(すななみ)。
掌の接触と同時に前屈運動、さらに摺り足による片足半歩ずつの特殊歩法『身滑り』によって、重力エネルギーが運動エネルギーを倍加させ、それによって衝撃が黒犬の体内へと浸透する。しかも真横に壁があった為に、俺の打撃が黒犬の身体を壁面へと押し付ける形になり、本来は空中での接触の為に衝撃が充分に伝わらずに終わっていたものが補われる事となり、圧縮された衝撃が逃げ場を無くして黒犬の内蔵諸器官を徹底的に破壊していた。
「ギャイン!!」
ずしりとした手応えを感じたと同時に、黒犬の身体から紫電が発生する。しかし、遅延している世界の時間は俺に新たな認識を与えていた。黒犬から流れる電気エネルギーが俺の体内へと浸透しつつある中、エネルギーである情報はただ純粋に、この地球と言う星へと還るものであると知った。
人の意識は、やがて自然へ還る。
それは肉体の死によって人の脳が生み出した記憶と言う名の情報が、同時にエネルギーである事で自然の循環へ戻る事を意味しており、この地球と言う星はそういった過去から連綿と続く数多の情報を蓄積して、ある意味情報の集合体を構築するに到っている。
それは、アカシック・レコードと呼ばれているらしい。
自然を体現する理念流においては全ての動作は、自然のエネルギーの利用と還元にある。それによって生まれた突然変異能力『心眼』は、肉体の反射という条件下において自身の意識が空白を生む瞬間に、この地球の情報集合体へと直結して空白の意識を穴埋めしていると言える。
より複雑化する情報の効率的な処理に対し、人間という一個体の性能では対処が出来なくなるのを、一時的に膨大なデータベースである地球の記憶と情報の共有を行う事で、自身の本来の性能を超えた能力を一時的に発揮するのだ。
黒犬から流れ込んできた電気エネルギーは俺の掌から神経を逆流し、脳幹へと瞬時に達する。一時的に電気エネルギーの速度と一致した神経のバスクロック速度は、細胞の水分子が沸騰する前に全ての電流を脳へと運び、シナプスの複雑な連携で生まれた高度な理論回路が高次元との共有化を行う。
それと同時に、黒犬の意識そのものでもあるエネルギーの情報が、俺に黒犬の持つ全ての記憶を認識させた。とは言え、黒犬の存在自体は人間より高次元のものである為に全ての記憶を処理出来ず、結局は至極断片的な記憶だけが残る形になった。
絶命した黒犬から掌を離すと、黒犬は口から血を吐き出した。床へと落下する途中、その身体はまるで霞であったかの様な錯覚を覚えさせる程に、見事に霧散して消え失せた。
「……消えた」
俺の間近でその光景を見ていたエリカは、床に尻餅をついた格好のまま、信じられないものを見た様な顔で呟いた。己の意識を復帰させた俺は、エリカの手を取って立ち上がらせた。
「さっきの化け物も、こうやって消えたんだよ」
俺がそう口にするとエリカの顔は急に蒼ざめ、何かに怯えた様に震えた声を出した。
「――デア・ヒンメル・ウンザー・ファーター……」
その後はドイツ語か何かでブツブツと小声で呟いているので聴き取り難いが、どうやら神に祈りを捧げているらしい。さすがに外人、キリスト教の信者だと言う事だ。祈りを捧げて少しは冷静さを取り戻したのか、今度ははっきりと日本語で語りかけてきた。
「……きっと悪魔の仕業です。この世のものとは到底思えません」
その言葉を聞いた俺は、軽く頷いてみせた。彼女の言い分は、ある程度当たっているのだ。
「どうやらそうみたいだ。尤も、さっきの黒犬は黒魔術とかそういった類いで生み出した、使い魔的なヤツらしい」
そんな事を俺が突然言い出すものだから、エリカは目を丸くしていた。
「日本人は無宗教だと聞いてますけど、貴方は随分と簡単に信じるんですね」
言いたい事は判る。
宗教観の希薄な日本人が、すんなりと悪魔の存在を認めた上、さらに魔術だの使い魔だの言い出したのだ。そんなオカルトな会話をするのは普通の感覚では無いだろう。
「俺は無神論者だけど、神や悪魔の存在は感じている。連中は高次元の存在、エネルギー生命体なんだよ」
おそらく、俺の言葉はエリカの想像を上回っていたのだろう。彼女は複雑な表情をして絶句していた。
「――エネルギー生命体?」
「神の姿なんて誰も見た事は無いだろう?それは存在しているが、目に見えない。同じ様に、パソコンのデータには実体は無い。でも確実に情報が存在しているんだ。エネルギーも、存在はしてても目に見えない。情報もエネルギーも同じものって事なんだ」
俺はそうやって説明をしたが、信心深い人間を相手にどれだけ理解させる事が出来るかは期待していない。エリカと俺の間には認識に決定的な差があるだろうし、実際のところ、俺は宗教には否定的だ。だが、俺が安易に神を否定しなかったのが幸いしたのか、エリカは特に気分を悪くはしなかった様だ。
「神は己の内に感じるものです。しかしポルターガイスト現象などは、今の説明で理解が出来るかも知れません」
エリカも今ここで、宗教議論などをして俺と意見を衝突させたくは無いのだろう。こちらの意見を理解はするが、大事な部分は譲らない頑固さみたいなものがドイツ人にはあるのだろうか。
「今の襲撃で、この場に留まるのはマズいと判ったと思う。しかし、ここを出てもおそらく黒幕が待ち構えている筈だし、どちらにしても危険は覚悟しなくちゃならない」
話題を変えた事で改めて今の状況を認識したのだろうか、エリカは生唾を飲み込んで、緊張した面持ちで静かに俺の話に耳を傾けていた。
「――だから、今度はこちらから仕掛けてやろうと思うんだ」
ぎょっとするエリカ。
だがハナっから否定するつもりも無いらしく、少し考えてから言葉を選ぶ様にして口を開く。
「……私は今でもとても恐ろしくて、何も考えられません。でも状況に流されるままではいけないと言う事と、発想の転換が必要だと言う事は判るつもりです」
さて、言うは易し行うは難し、と言ったところである。
だが何もやらないよりは、やれる事は何でもやった方がいいに決まっている。俺は一つ試したい事があった。
「……もし黒幕がいるなら、立て続けに二度も襲撃を退けた事で警戒していると思う。もし俺が相手の立場なら、少しやり方を変える」
エリカは俺の説明を黙って聞いている。おそらくは自分に状況を変えるだけの力が無いのを判っているので、当面は俺の言葉に従うしか無いと考えての事だろう。
「通常ならば、単体で襲って駄目なら数で攻めようと考える。しかし、建物内でそれは難しい。なら広い空間に誘い込み、そこで仕掛けるのが効果的だ。もし俺達が動かないなら火でも放てばいい訳だし、どちらにしろ俺達は外へ出るしか無い」
そこで疑問を感じたのか、エリカは首を傾げて口を開いた。
「どうやって火を?」
「相手は悪魔だと言ったのはエリカだろ。黒魔術でやるんじゃないか?人間の常識で判断するのは危険だって事だ。このまま普通に外へ出ても敵が待ち構えているなら、いっそ黒幕を引きずり出してやろう」
俺が不敵に笑みを浮かべたのを見て、エリカは複雑な顔をした。不安を感じているのだろうが、どうやってもその不安を払拭出来る訳は無いので話を進める。
「敵は策を労して、裏でこそこそやるのが大好きなヤツだと思う。そんなヤツが一番嫌うのは、不確定要素だ。おそらく俺がいなければ、黒幕の思惑通りに事は終わっていた筈だ。目的はエリカの命だろうが、俺にコケにされたままではプライドが傷付く。まずは俺に狙いを変えてくる筈だ」
あくまで推論の域を出ていない話ではあるのだが、大方の見方はそう的外れなものでは無いと言う確信があった。相手があまり難しい事を考えないヤツなら再び化け物をけしかけてくる筈で、それが途切れている状況を考えると、俺達の出方を伺っている節がある。
「しかし――外に出てきたのが、エリカ一人だったらどうなるか」
エリカはそれを聞いて目を見開く。
「……貴方に救われた身で、今更こんな事言うのは間違っているのかも知れませんけど、私一人ではあっさりと殺されてしまいます。他の方法は無いのでしょうか?」
しっかりと己を主張するが、その表情は既に泣きそうになっていた。
「酷な話だとは思うけど、俺と一緒にいたところで数で来られればどうにもならない。今の状況を最大に生かすには、相手の猜疑心を利用するしか手は無い。敵にしてみればエリカ一人、いつでも片付けられると思うだろう。もしエリカ一人しか姿が見えなければ、当然俺を探すのを優先する。エリカを先に殺してしまうと、俺が逃げてしまうかも知れない」
そこで一旦話を区切り、エリカの反応を見る。
エリカは外見こそ大人びているが、実年齢は俺とそう大差は無い筈であり、まだまだ気持ちは幼さを残している。緑色の瞳が濡れ光っているのを見ると、こちらも罪悪感を感じてしまう。
だがそれでも、現状で俺が今後の結末の鍵を握っている以上は弱さを見せられない。
改めて気持ちを切り替え、話を続ける。
「だがエリカを生かしておけば、俺を誘き寄せる事が出来ると思うだろう。もしかしたら本人が姿を見せれば俺が出てくる事を看破して、わざと姿を晒すかも知れない。俺としては、それに賭けるしか無いと思う」
エリカは恐怖心を抑え込んで俺の目を見る。
何かを強く願うその気持ちはどういったものなのか、俺には知る由も無い。
「……その読みが外れる事もありますよね?」
俺は深く頷いて、本心を包み隠さず話す。
「その時は、諦めて建物の中に逃げ込んでくれ。もしかしたら、すぐに殺さないかも知れない」
話もここまで来れば、結局は俺とエリカの間でどれだけお互いを信用出来るか、と言う事になる。
俺は既に、敵が俺を見逃す筈が無いと思っているので覚悟は出来ているし、命を狙われているエリカに裏があるとは考えられないので疑ったりもしていない。
エリカは今までの事を考えていたのか、ぎゅっと手を握り締めて何かを覚悟したのか、再び俺の目を見て口を開いた。
「……もし読みが当たっても、相手が本当に恐ろしい悪魔だったら人の身で抗う事は出来ないかも知れません。それでも貴方は戦って、勝てると思ってますか?」
それが一番の問題かも知れない。だが敵を知り己を知れば百戦危うからず、と諺にある通り、まずは敵の正体を掴まなくては話にならない。
「勝てる勝てないは考えない。やれる事を精一杯やって、それでも玉砕したなら、それはそれでどうしようも無いじゃないか。だが俺は死にたくは無いし、自分の責任を放棄するのも同じくらいに嫌だ。約束出来るのは、俺は最後までエリカを見捨てないって事だけだ」
だがエリカはまだ多少の不信を持っているのか、食い下がる様に再び問い掛ける。
「……どうして?」
俺はエリカの視線を受け止めて、しかし少々小恥ずかしくなって目を瞑った。
「……これは日本の古い考え方だが、人の死に際を見取った人間は、最後までその死を見届ける義務がある、って考え方がある。キミの兄さんの名誉を守るのは、その死を看取った俺の行動如何だって事だ」
ここで初めてエリカの兄の事を口にした為か、エリカの目から涙が一筋流れ、頬を伝わっていった。
「……兄はここ最近、何か調べ物をしていた様なのです。誰かと頻繁に連絡を取り合っていたみたいですし、きっと何かに巻き込まれたのだと思います。もし、無事に生き延びる事が出来たなら、一緒に兄のしていた事を調べてくれますか?」
これはおそらく、エリカが俺に対する信用を表現したものだと思う。
信用したからこそ、生き延びてその後も同じ目的を共有しようという前向きな意志だ。俺は頷いて同意の意志を示した。
「約束するよ」
エリカは俺の言葉で安心したのか、涙を手で拭って表情を和らげた。
「ありがとう」
俺達は互いに頷いて、しんと静まり返った廊下を歩き出した。


第一話・女神降臨