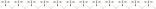Sick City
第一章・崩壊前夜
その日は、余りにも唐突な出来事によって始まった。電話の音によって朝早くに安眠を妨害され、二度寝しようとしたところで爺ちゃんに叩き起こされた。
「う〜、いったい何なの?」
昨日のケツアルコアトルとの戦いで、身体中が筋肉痛になっている。眼を擦って不平を漏らす私の背中を、爺ちゃんが思い切り叩く。
「んぎゃっ!」
バシン、と快音が鳴り響き、遅れてやってきた痛みに悲鳴をあげる。
「さっさと支度をせんか」
何があったのか、急な展開に頭が付いていかない。
「んも〜。そもそも理由が判らないんだけど。まだ学校行くには時間あるし」
だけど爺ちゃんは、それ以上何も言わずに部屋を出て行ってしまった。
「……しょうがないなぁ」
シャワーを浴びて身支度を整え、何だかんだで一時間。まだ朝の六時過ぎだと言うのに、既に居間では朝食が用意されていた。食卓の上座で胡座をかき、ご飯を口に運んでいた爺ちゃんの前に座る。
「朝飯を喰ったら、一緒に楯山神社に行くぞ」
「え? 何で?」
突然そんな事を言われても、何が何だかさっぱり判らない。いまいち理解出来ていないのが顔に表れているのか、私の顔を見て爺ちゃんがやっと説明を始める。
「さっきの電話は楯山神社からでな。静が登校するそうだ」
「……ほんとに?」
何でいきなり登校する気になったのか、余りにも脈絡が無さそうなので素で驚いた。
「判っていると思っていたんだがな。昨日の騒動があったのだから、いつまでも引き篭もっている場合じゃ無い」
「そっか……でも大丈夫なのかな」
どういう心境の変化があったにせよ、いきなり登校してパニックになったりしないだろうか。
「だからこそ、お前が一緒に行くんだ」
「……私に一体どうしろと」
昨日の一件で、気軽に話が出来るような状態じゃ無いのが心の奥底に重しとなっている。そんな事を気にしていると、爺ちゃんはいきなり笑い出してしまう。
「わっはっは。お前があれこれと悩むようなヤツだったとは。似合わんからやめとけ」
失礼な物言いだったけど、爺ちゃんは私の性格をよく知っているから、敢えてそんな事を言うのだろう。確かにいつまでもこのままの状態が続くのは良くないし、悩んだところで解決策は思い付かない。少し気分が軽くなり、自分の顔に自然に笑みが浮かんだのを自覚する。
「ま、折角お膳立てしてくれたんだから、後は出たとこ勝負ってのも悪く無いのかな」
「深く考えたところで、お前の頭じゃ永遠に答えなど出ないからな」
爺ちゃんの余計な一言。
「私、馬鹿じゃないもん」
爺ちゃんと何度こういうやり取りをしたのか。
「お前は馬鹿だ。そういう事にしとけ。後が楽になるぞ」
そして決まってそういうのだ。
何やら含蓄ありそうな物言いだとしても、今の私には判りそうに無かった。

爺ちゃんと二人で楯山神社に歩いて向かう間、神社の石段前で二人の人間がずっと動かずにいるのが感知された。何かを待っているのか、それとも私達を待っているのか。
どうも一人は、あの蓮見みたいだ。もう一人はちょっと判らないけど、何で蓮見があんなところにいるのか。
石段前が見えてくると、やはり蓮見のヤツが立っていて、隣にいる男子学生と何やら話をしているのが見えた。もう一人も何となく、見覚えがあるような気がする。長めのウェーブヘアーを脱色しており、洒落た感じの丸眼鏡を掛けており、学ランの襟章から桐琳の三年だと判る。
こちらに気付いた蓮見が片手を挙げた。
「お、来たな」
「あんた何してんの?」
蓮見はそれには答えず、私の隣の爺ちゃんに向かって挨拶をする。
「どうも初めまして。御空さんの友達の蓮見卓郎と言います」
続いて隣の男子学生も名乗り始める。
「おはようございます。零二と同じクラスの佐伯龍太郎です」
道理で見覚えがあると思ったら、確かこの人は零ちゃんと同じクラスで、洋楽同好会の会長をやってる人だった筈。何でこの二人が一緒にいて、こんなところにいるのか。爺ちゃんは二人の顔をそれぞれ見て、何やら納得したかの様にうんうんと頷いている。
「おう、おはようさん。二人の事は聞いてるよ。状況は判ってるな?」
一体、何の話をしてるのか。私の事などお構いなしに二人も応じる。
「いや〜、さすがに昨日のはヤバかったっすね」
蓮見はケツアルコアトルを撮影していたので、ある程度は何が起こったのか知っている。隣の佐伯君は腕組みをして、難しい顔をしていた。
「……俺達を呼び出すって事は、もう隠す必要が無くなったって事ですか?」
「そうだ。零二はいない。静は出歩かず、敵が現れた。最早、監視する必要は無い」
そこまでが、私の我慢の限界だった。三人の訳の判らない話に割り込む。
「隠すとか監視とか、訳判らないよ。私を除け者にしないで、ちゃんと説明してよ」
蓮見と佐伯君は説明していいのか判断出来ないのか、爺ちゃんの顔を見て黙り込む。それを涼しげな顔でさらっと流し、爺ちゃんが私に向き直る。
「この二人はずっと静を監視しておった。佐伯は零二の側で、蓮見は校内の監視。もう一人、神社側に霧島皐月という娘もいる。三人の家系は桐内や仁科と同じく、楯山の氏子なんだ」
私はあんぐりと口を開けて、ただ呆然と受け止めた。蓮見が珍しく、申し訳無さそうな顔でこちらを見て口を開く。
「ずっと黙ってて悪かったな。喋っちまったら監視の意味が無くなるからさ」
「……別に怒ってる訳じゃ無いけど。それより、静ちゃんを監視する意味が判んない」
私が漏らした疑問を、今度は佐伯君が引き継ぐ。
「楯山が零二の記憶を呼び覚ましてしまったら、楯山が目覚めなくなるって話だ」
「目覚めなくなる?」
次から次へと訳が判らない。爺ちゃんは気難しそうな顔で軽く頷いてから、その後を引き継ぐ。
「まず、我ら崎守の持つ力についてからだ。『心眼』には個人差があり、零二は共感、共有能力に優れる。御空は索敵能力と厄払い、俺は千里眼と予知能力を持つ」
その説明を聞いて少しばかり驚く。自分の事は判るけど、爺ちゃんと零ちゃんの能力は始めて知った。
「共感共有? 予知能力? 何その不思議設定」
「茶化すな。共有とは他者との思考の共有であり、他者と共感する事で可能となる。犬は群れで行動し、リーダーの意志は黙っていても反映されるものだ。それと同じ事で、零二は集団を統合し、導く能力に秀でている」
思わず、零ちゃんが大勢の犬を引き連れている光景が頭に浮かんでしまい、顔がニヤついてしまう。私が妙なタイミングでニヤニヤしてるのが変なのか、爺ちゃんは少しばかり溜め息を付く。
「……はあ、相変わらず緊張感の欠片も無いな。俺の予知能力の方は、自然界の警告に近い。地球の集団意識は全ての動植物の魂の集合体であり、『虫の報せ』という形で示唆を与えてくる」
その説明なら多少は理解出来る。ロジックは全く理解出来ないけど、『虫の報せ』という現象は私自身、何度か経験があった。
「それって私も経験あるんだけど、私にも予知能力があるの?」
「多少はあるだろう。それぞれ能力に個人差があり、それぞれの得意分野について説明しただけだ。共有能力や索敵能力はそれぞれがある程度は備えている」
よく考えてみると、『虫の報せ』は経験あるけど予知って訳じゃ無かった。それに共感共有能力については、全く経験が無い。
「それを踏まえた上で、俺達の役割は分担される。零二は共に戦う仲間を集めている。本人に自覚は無いだろうがな。お前は静の守護者で、俺はお前達の導き手だ」
そんな事を言われても、私にだって自覚なんて無い。成り行きで二人の神を倒したけど、それすらも何か大きな流れの中の些細な出来事の様に思えてしまう。
「……戦う仲間とか守護者とか、私達は一体、何と戦ってるの?」
私の疑問に、爺ちゃんは少しばかり考え込む。
「……うむ、その説明は難しくてな。今まで敵は直接、姿を見せた事が無い。だが敵の『意志』は明らかに存在する。俺達の敵は、その『意志』としか言えないのだ。相手の正体が判らないと言うのは歯痒くもある。一つ言える事は、ゴールが近いという事だけだ」
「ゴール? 何を以て終わりな訳?」
漠然とした話ばかり続く中で、どんな結果が予想出来ると言うのか。随分と当てにならない話だな、と思いながら問い返す。
「静が巫女として、覚醒すれば終わりだ」
「……はあ?」
巫女として、って既に巫女さんをやってる筈だ。それとも、今はまだ見習いみたいなものだから、ちゃんとした巫女さんになるって事なんだろうか。私が面食らってるのを見て説明が足りないと反省したのか、爺ちゃんはさらに説明を加える。
「形式としての話では無いぞ。神に仕える者として、神の声を聴く力に目覚めると言う事だ。その為には、本人がそれを求める強い動機が必要となる。誰かに依存している間は、決してそうはならない」
そこで思い当たる。
静ちゃんが依存している相手は、零ちゃんしか考えられない。幼少の頃に引き裂かれた二人の関係が重くのし掛かり、近くにいるのに遠くの関係。手を伸ばしたいのに許されない、そういったジレンマが、不登校の本当の原因なのかも知れない。
そこまで考えて、ある一つの仮定が生まれた。
私はそれが許せない。
「……零ちゃんを敢えて、静ちゃんから遠ざけていたって訳?」
それを行っていたのは、明らかに爺ちゃんの意志だろう。実際、私に零ちゃんの記憶に関して口止めをしていたのは爺ちゃんなのだから。私が何に対して怒っているのか、爺ちゃんは察していた。
「……お前に損な役回りをさせていたと思っとるよ。言い訳はすまい。だからこそ、二人は元通りになるべきなのだ」
「元に戻るの? 零ちゃんの記憶って」
期待の目で爺ちゃんを見詰める。
それが可能なのなら、是非そうであって欲しい。今まで、静ちゃん一人だけが苦しんでいたみたいだから。
「静は更に苦しむ事になるだろうがな。だがその後は、共感能力の増大した零二ならばきっと、静を『鎮める』事が出来ると信じておるよ」
最早、どうして自分が戦っているのかなんて、どうでもよくなっていた。静ちゃんに立ち直って欲しいと、強く思う。爺ちゃんが何かを言っていたけど、私は適当に聞き流して決意をした。
絶対に、静ちゃんは私が守ると。

神社の境内で待つ事三十分程、いい加減痺れを切らしていたところで静ちゃんは現れた。先に話をしに行った爺ちゃんと、朝からずっと静ちゃんに付いていたらしき皐月さんが、一緒に出てきた。
制服姿の静ちゃんは無感情な様子で、表情からは心情を伺い知る事は出来そうにない。今まで不登校だった静ちゃんをどうやって説き伏せたのか、改めて気になった。私は努めて笑顔で、挨拶から入る事にした。
「おはよう静ちゃん。これから私達が登下校は一緒だから、よろしくね」
「……うん。おはよう」
静ちゃんは目を逸らしたまま、抑揚に欠けた小さな声を搾り出す。色々と聞きたい事は山の様にあったけど、それを聞いたところで応じてくれるとも思えず、何も聞かない事にした。爺ちゃんが皆の顔を見回して口を開く。
「さて、まずは確認しとこうか。昨日の一件で判った事だが、静を狙う敵は強大な力を持っている。今までの様に引き篭もっていて、いきなり寝ているところを襲われでもすれば、対処するのは困難だ」
いきなり核心を突く説明をし始めた事から、静ちゃんにもある程度は今までの経緯を説明してあったらしい。そこに黙っている事の出来ない性格の蓮見が、当然の疑問を口にする。
「翼の生えた巨大な蛇が飛んでたんだぜ?あんなのがまた襲ってくるとして、俺達じゃどうにもならないでしょ」
さらに佐伯君が気難しい顔で付け足す。
「監視役ってんなら何も言うつもりは無いですよ。でも俺達は普通の人間なんですよ。もしそんなのが出てきたら、悪いけど逃げますよ」
そんな二人の態度に嫌気が差したらしく、今まで黙って聞いていた皐月さんが二人を嗜めようとする。
「貴方達、いい加減にしなさい。私達は自分達の出来る事をする、というのが基本な筈でしょう? 出来ない事をしようとは思わないの。スパイ教育を受けてきた蓮見君ですら、昨日の化け物には歯が立たないのだから」
「スパイス教育?」
皐月さんの口から飛び出てきた聞きなれない単語に、私は疑いの眼差しで蓮見を見る。蓮見は苦笑いを浮かべながら答える。
「俺はインド人かよ。すっかりバレてるかと思ってたんだけどな。ちょいと説明するとだな、ウチの親父が防衛省陸上幕僚監部って所で情報調整官っていう仕事をしてるんだよ。それで色々と叩き込まれててな。パパラッチやってたのも半分は趣味だけど、半分は実益だったのさ」
「何かよく判らないけど、蓮見って実は凄いヤツ? 某有名スパイ映画みたいな」
スパイなんて映画の中でしか見た事無いから、実際はどんな仕事をするのか想像が付かない。
「そんな派手なもんじゃないよ。情報を集め、それを関連項目ごとに纏めて意味のある形にする。ぶっちゃけ、やってる事はジャーナリストとそんなに違いは無いんだ。一応は、それなりに戦闘訓練もやってはいるんだけどな」
昨日、駅前まで一緒に走った時にかなり高い運動能力を持っていると思ったけど、改めて考えるとただのカメラオタクにしては、不釣り合いな程のものだと思う。
話が脱線していたのを爺ちゃんが遮る。
「それはそれとして、だ。神社の方は桐内の爺さんに警護を任せてある。とは言え、昨日の化け物の様なものが出てきたらどうにもならん。そこで連携が大事になる。神社には俺が待機し、外出時は御空が対処する。お前達は外で敵と遭遇した場合、御空が対処している間に俺に携帯電話で連絡をしろ」
爺ちゃんの指示を聞いて、佐伯君は顔を僅かに曇らせる。
「……それだったら御空ちゃんが、自分のケータイで連絡すりゃいいんじゃないすか?」
確かにその指摘の通りで、危険を冒してまでそんな程度の役割の為だけに付いてくる必要なんて無い。私もうんうんと頷いて同意する。
「最後まで話を聞け。御空一人で対処するのだから、必ず連絡が出来るとは限らんだろう。それにお前達の役目はそれだけじゃあないぞ。昨日の化け物の一件で判っただろうが、一旦戦いが始まった時に周辺住民を巻き込む可能性がある。お前達はそういった住民を遠ざけるんだ」
私も爺ちゃんの指示に疑問があったので質問する。
「爺ちゃんも『心眼』持ちなんだから、敵が現れたら遠くにいても判るでしょ?」
「俺の感知領域はせいぜい500メートル程度だ。それを超えると色々と邪魔が多くてな。お前程の感知は出来んよ」
そういえば、さっきも得手不得手がどうのとか言っていたっけ。話が一段落したと判断したのか、皐月さんが腕時計で時間を気にしながら声を上げる。
「あら、もうこんな時間。そろそろ行かないと遅刻してしまいますよ」
「折角の静ちゃんの復学なのに、遅刻したら格好付かないもんね。んじゃ行こっか」

私達の登校風景は組み合わせが珍しいらしく、他の登校中の生徒達から注目された。
静ちゃんは学園では影が薄い存在だったからか、それほど注目された訳では無かったけど、蓮見と佐伯君、それに私の三人は一緒に登校などした事が無い。さらにこの三名に関しては学園でも有名人の部類に入るので、そういった意味でも人目を惹く存在だと言える。
「スパイ候補生のクセに、こんなに目立ってていい訳?」
私のイヤミに、蓮見はニヤリと口元を笑みで歪めた。
「木を隠すには森の中、って言うだろ。だいたいジャーナリストの中でも海外特派員なんてやってるヤツらの中には、本職のスパイだっているんだぜ。しかも引退したらテレビに出て、本まで出してたりしてな。下手にコソコソしてる方が不自然だ」
判るような判らないような。
一方のバンドマン、佐伯龍太郎は静ちゃんと同じクラスだからか、何とか会話を成立させようと努力の真っ最中だ。
「だからさ、伝一郎さんに指示されてたからってだけじゃ無くて、零二とはそういった思惑抜きに友達なんだ。そうやって警戒されるのはいいけど、あいつの事は疑わないでくれよ」
一体何の話をしているのか、静ちゃんは相変わらず陰鬱なオーラを全身から発散していた。
「……別に、崎守君とは殆ど喋った事なんて無いから」
それだけを言って黙り込んでしまう。
共通の話題は何か無いかと考えたらそんな話になってしまったのだろうけど、それは薮蛇というものだろう。
会話の糸口がなかなか見出せずに四苦八苦している佐伯君をまんじりとした、眠たげな薄目で眺めていた蓮見が突然、ニヤリと笑みを浮かべる。
何かまた、良からぬ事を考えている。
「話のネタなんて、そこら辺にいくらでも転がってるじゃないか。例えば、実は隠れアキバボーイの龍太郎は、ガチでリアル巫女さんを前に照れがあるんだろう、とか。もっと自分に正直に生きてみたら、きっと世の中楽しくなるぜ」
ケラケラと笑ってからかわれ、意外な一面を暴露された佐伯君が猛烈に抗議を開始する。
「誰がアキバボーイだ! お前に言われたくねえよ!!」
「いやあ、最近のバンドマンは実は隠れオタばっかりだって言うしな。別に恥ずかしがらなくてもいいんじゃね? フィギュア大好きでも、俺は別に軽蔑なんてしないぜ? 俺も『萌え』には理解がある方だ。何なら厳選ベストアングルショットを優先的に回してやってもいい」
「……目の前に、ダメ男が二人もいる」
ついでだから、冷めた視線を二人の男に送る。私の視線にさらに羞恥心を煽られたのか、佐伯君は顔を真っ赤にしてソッポを向く。
「俺が好きなのはブリスターだ! 萌えフィギュアじゃねえよ!!」
「いいから聞けって。ああいう女の子はな、遠慮していても警戒させる一方なんだよ。こっちからガンガン押して、無理矢理扉を押し開けるしか無いんだぜ。判るか?蓮見流交渉術・其の二『獲物は逃すな』だ」
蓮見は静ちゃん本人にも聞こえているのをまるで気にしておらず、遠慮無しに言い放つ。
そもそも最後のは訳判んないし。
私からすれば、静ちゃんは警戒しているというだけじゃなく、前向き志向になれるような希望が欠落しているのが原因なのでは無いかと思う。その原因も判らないのだから、解決策なんてなかなか見つからない。
学園に到着するまでの間、蓮見と佐伯君による果敢なチャレンジは続いたけど、人間関係を構築する気がまるで無さそうな静ちゃんとは、全く噛み合わずに終わった。

久しぶりの静ちゃんの登校に、クラスメイト達がどう反応をしたのか気になっていた折り、ケータイに佐伯君からメールが入った。
『やべえよ。本人帰っちゃったよ』
「……何やってんのよ」
一時限目が終わった直後の休み時間だったので、速攻で佐伯君のクラスまで走る。兎に角、詳しい話を聞かない事には始まらない。
三年B組の教室前で、佐伯君と合流する。佐伯君は顔を真っ青にして、申し訳無さそうに私を見た。
「……すまねえ。前に楯山にちょっかい出していたヤロウがいてさ、顔を合わすなり絡みやがったんだ。それでいたたまれなくなったんだか、授業始まる前に飛び出しちまいやがった」
その時に佐伯君は何をやっていたのか、と追及したかったけど、それが事実なら既に一時間も経過している。
こんな事になるのだったら、アンテナを設置して『心眼』で静ちゃんを常に把握しておくべきだった。いくら5kmの索敵範囲を持っていても、人の多い所でアンテナを使わずに、特定の人物をずっとマークし続けるのは難しい。
私は憮然とした顔を隠そうともせず、淡々と応じる。
「……兎に角、ここでじっとしていてもしょうがないでしょ。私は今から静ちゃんを探しに行くから、佐伯君はとりあえず授業を受けてて」
それだけを告げて、私はその場から駆け出した。
本来なら佐伯君にも探しに行って貰いたいところだけど、佐伯君と静ちゃんの関係は最悪だ。もし佐伯君が静ちゃんを発見したところで、すんなりと連れて帰って来れるとは思えない。
一旦自分の教室に戻り、リカーブボウの入ったソフトケースだけを肩に担ぐ。
「悪い沙由里。私、早退するわ」
近くにいた児島沙由里にそれだけを言って、教室を飛び出す。
「え? ちょっと御空〜!?」
背後から沙由里の間延びした声が聞こえた。
私は走りながら、ケータイで蓮見にメールを入れる。現時点で一番当てになるのは、常に監視カメラで校内中を把握している蓮見だ。どうせ授業なんて出ないで部室に引き篭もっていたのだろうから、もしかしたら既に静ちゃんを追跡しているかも知れない。
昇降口から飛び出した時、メールを送信してからきっかり一分で返信メールが届いた。
『尾行中。山の手霊園に来い』
やはり蓮見はこちらの期待通り、すぐに追跡してくれていたらしい。
山の手霊園とはこの近辺の小高い丘に位置する、鎌鍬でも歴史の古い霊園墓地だ。半ば公園化しており、沢山の花が植わっていて観光名所となっている。ちなみにバロールと戦った戦場である教会へと行く途中で通り過ぎたのが、山の手霊園だった。
さらにメールが届く。
『叶さんを呼び出したらしい。二人でお話中』
なんで叶さん?
どういう事なのかまるで判らないけど、以前から叶さんは楯山神社に入り浸っていたみたいだから、もしかしたら二人は結構仲がいいのかも知れない。
蓮見に加えて叶さんまで一緒にいるのだから、そんなに急がなくてもいいかも知れない。でもこんな時に昨日のケツアルコアトル並の敵と遭遇したら、あの二人では手に負えない。
やはり急いで合流した方がいい。
校門を抜け、通りを一気に駆ける。山の手霊園まではおよそ8km程、私の足で20分以上掛かる。『心眼』で周辺の状況を精査、ここから300m先の私鉄の駅前に、バスが停留している。
あまり意味の無い情報なので駅前を素通りすると、丁度タイミング良くバスが発着したところだった。立ち止まって後ろを振り返り、バスの行き先を確認する。
「う〜ん、なんてタイミング。山の手霊園行きゲット」
とは言っても今の私のお財布には、一円も入っていない。
なんでこんなに貧乏なのかと言うと、単に私に計画性が無いから。月々のお小遣いが五千円というのはちょっと少ないと思うけど、ウチの場合は欲しい物があったらその都度申請する形を取っている。無一文だからジュースすら買えないけど、教室に置いてきたスポーツバッグの中には、ちゃんとお茶の入った水筒が入ってるから問題は無い。
詰まる話、お金が無いのでバスに乗れない。だけど、なるべく早く目的地に到着しなければならない。バスは停留所で止まる事もあるし、スピードも早いとは言えないけど、それでも人の足よりはマシだろう。
私は近くの電柱に飛び上がり、蹴りの反動でとんぼ返りをして、擦違うバスの屋根に飛び移った。
「タダ乗りゴメンね」
こんな事はするべきじゃないけど、蓮見流に言えば『モラルと実利』ってヤツだ。やっぱり人間、その時々で臨機応変かつ弾力的に対応するべきだろう。
後ろの車の運転手が目を丸くしてこちらを見ているけど、なるべく気にしない方向で。もしかしたら、パンツ見えちゃったのかも知れないけど。
何度か停留所で停車して客の乗り降りがあったけど、10分程度で山の手霊園前に到着した。山の手霊園の手前には大きな駐車場があって、平日にも関わらず駐車率は多めだった。
バスの屋根から飛び降りた私を、近くにいたお年寄り達が変な目で見る。見渡してみると駐車しているのは観光バスやマイクロバスが殆どで、お客さんも殆どがお年寄り。
ケータイを取り出し、蓮見に到着した旨をメールする。
『展望台まで来い』
蓮見から受けたメールにある展望台とは、この霊園の中でも一番の高台に設けられている。本来は墓地の筈が、とことん観光名所としての設備を追及しているのだから変な話だ。
「……墓地って無税だっけ? 観光でお客が落とすお金は丸もうけ?」
無一文だからって訳じゃ無いけど、露骨な拝金主義には何だかムカムカする。ちゃんと税金を取らないから、宗教が政治に口出ししたりするんじゃないの?税金を取る一方で、神社とかお寺とか日本文化として保護する形で助成金とか出せば、怪しい新興宗教との区別が出来るんじゃないだろうか。
今の私には関係の無い事を考えながら展望台まで走る。
沢山の花々が咲き乱れる遊歩道は次第に緩やかな上り坂に変化し、行き交うお年寄り達の姿もまばらになっていく。何か空気感みたいなものが微妙に変化しているのに気付き、『心眼』による探索に注意を傾ける。
「これかな」
『展望台まであと200メートル』
そう書かれた立て看板の裏側に、一枚のお札が貼られていた。多分、そこら中に同じようなお札がある筈だ。
「……叶さんが、結界を張ってる?」
こんな事が出来るのは思い浮かぶ中で、叶さんくらいしかいない。坂道を登りながら周りに誰も見当たらない事を考えると、どうやら結界で人払いをしてるらしいと思い至る。
周辺に充満する不快なノイズは、普通の人間に無意識下の拒絶感を誘発する。ノイズと言っても可聴領域を超えているので、普通の人には認識出来ない。それでも展望台の近くに蓮見が潜んでいるのだとすれば、余程意志が強いのか、もしくは叶さんが結界を張る前から潜んでいるのかのどちらかだろう。
坂道を登って展望台へと通じる階段の手前で、脇の花壇に分け入っていく。階段をそのまま登ると、静ちゃんと叶さんの二人に気付かれてしまう。まずは、二人を密かに観察出来る場所に潜んでいる筈の蓮見と合流した方がいい。
花々の咲く斜面を登って行くと、斜面と展望台との境界に蓮見がいた。四つん這いの体勢で二人を観察している背後へ、私も四つん這いになって近寄る。気配を読んだのか、肩越しにこちらに振り返ってニヤリと笑みを浮かべる。
「随分と早く着いたじゃないか。それよりも、あれを見てみろよ」
「ちょっと待って。スカートが枝に引っ掛かっちゃった……よいしょ、っと」
斜面からひょこっと顔を出して、二人の姿を確認する。
街が一望出来る高台の広場は円形で、直径にしておよそ50メートル程もある。その広場のど真ん中、屋根付きの休憩所に二人はいた。
「……何やってんだろ」
御影石で造られたベンチに座り、制服のジャケットを半脱ぎにして、ワイシャツを肩からはだけた静ちゃん。その素肌を晒した背中に、お札を当てて何やらブツブツと呟いているのが叶さんだった。
「う〜む。俺とした事が、絶好のロケーションを確保出来なかったぜ。いや、潜伏するならここなんだけどよ」
角度が悪いのか、肌を晒した静ちゃんの背中しか判らない。相手に気付かれない様に潜んでいるのだから、自ずと背後に回るしか無かったのだろう。
「つまんない事言わない。それより、あれ何やってんのかな」
「俺にオカルト知識を期待するなよ」
あっさりと説明を放棄され、私はただ唸るしか出来ない。
人払いをしてまでやる事かどうか。
乙女の肌を人前で晒す訳にはいかないのだから、何となく判る気もしないでも無いけど、やはり何処か不自然だ。そもそも学校を逃げ出して叶さんを呼び出し、その揚げ句がこれでは説明が付かない。お札を使っている事から何かしら、呪術的な儀式みたいなものだろうけど、それが一体どんな効力を持ってるのか。
ここからだと静ちゃんの顔は伺えないし、叶さんにしても『心眼』で何事かを呟いているのが判るだけで、その表情は見えない。
「さっきからずっとやってるんだ。かれこれ三十分くらいか?」
「随分長いね。最初はどんなだったの?」
蓮見は少し考え込んでから首を捻る。
「何だか苦しそうな顔をしてたな。それからすぐに叶さんが現れて、そこら中に紙を貼ってた。叶さんは事情を理解しているみたいだな」
「どうしてそう思ったの?」
「楯山嬢に何も聞かないからさ。俺には読唇術の心得もあるんでね。そもそも口が動かない事には、読み取れる訳が無い。ハナっから何も喋ってないんだ」
読唇術とは確か、唇の動きから何を言っているのかを読み取るスキルだ。隠しカメラで動画撮影をし、無音でも何を喋っているのか判るのであれば、スパイ活動にも大いに役に立つだろう。
しかし叶さんが前もって事情を知っているとするならば、この行動には何か大きな意味があるかも知れない。考えてみれば、前から叶さんは楯山神社に入り浸っている。その事実に蓮見も気付いたのか、私達はお互いに顔を見合わせる格好になった。
「……叶さんはこれをやる為に神社に呼ばれていた、とかありそうじゃないか」
「……そうかも。どうも私達の知らない事情が、まだまだいっぱいありそう」
何の為に、という部分こそ判らないけど、とりあえず憶測ながらも、それなりに納得出来る答えにはなる。
どうやら意味のある結果が得られたらしく、叶さんはお札を静ちゃんの背中に貼り付けたまま、手を放した。静ちゃんはいそいそと服を着直し、ゆっくりと立ち上がってから見晴らしのいい鉄柵の側まで歩いて行った。
「ちょっと行ってくる」
ずっと潜伏していてもしょうがないので、思い切って接触してみようと思う。蓮見は何だか呆れ顔で私に付いてくる。
「別にいいけどよ。ちょっとは俺の努力も考えてくれ」
いきなり茂みの中から現れた私達の姿に、叶さんが驚いて素っ頓狂な声を上げる。
「うわっ、って何だ、御空ちゃんか〜」
遅れて静ちゃんがこちらへ振り向いた。
「……見てたの?」
何だか初めてまともな事を口にしたように思えて、私は少しだけ笑みを浮かべた。
「ゴメンね。心配だったからさ」
こちらから色々と追及するのは簡単だけど、それでは今までと変わらないから敢えて何も聞かない事にする。それで緊張感が薄れたのか、静ちゃんは溜め息と共に、僅かに肩から力が抜けたようだった。何を言おうか逡巡を見せた後、何か憑き物でも落ちたかの様に話し始める。
「……心配掛けちゃってご免なさい。私、護って貰ってばっかりだから、御空ちゃんイヤにならないかな」
どうやらまともに会話が成立しそうで安心したけど、一方では少し拍子抜けしてしまった。謝ってくれるのは嬉しいんだけど、事の真相と言うか、もっと突っ込んだ説明が欲しかった。だからと言って、無理矢理聞き出す訳にもいかない。
「全然。私ってほら、イヤだったらそもそも何にもしない性格だし。それに静ちゃんが頑張ってるのは判るよ。それでも後ろめたいならさ、今度一緒においしいモノでも食べに行こう。ね?」
人間、おいしいモノを食べてお話なんかしたら、それだけで幸せだったりする。余計な事なんて全部すっ飛ばして、一番大事な事を考えた。
にっこりと笑みを浮かべる私を見て、やっと静ちゃんの顔にぎこちない笑みが浮かんだ。そんな私達を遠巻きに眺めていた叶さんが、いつもの調子で明るい声を出す。
「若いっていいわね〜。そういう事で蓮見クン、貴方の奢りで甘いモノでも食べに行こう」
途端、蓮見が悲鳴を上げる。
「はあ!? 何で俺が?」
しかし叶さんは、何でも無いとでも言うようなあっさりとした口調で断じる。
「キミの得意な『モラルと実利』で考えてみなさい。ここで男の甲斐性を見せなくて、どうすんの」
叶さん良い事言うな〜って思って見ていると、蓮見は不貞腐れてブツブツと呟いていた。
「……自分の都合で人に甲斐性求めんなよ……アンタ絶対、自分がタダ飯喰いたいだけだろ」
蓮見の呟きは、見事全員にスルーされた。

そのまま学校へ行ったところで静ちゃんがプレッシャーを感じてしまうだろうから、いっそサボっちゃえって事になった。
叶さんがレンタカーを借りてくれたので、鎌鍬市のお隣の横幅市に移動。湾岸地区にある郊外型のショッピングモールの中に、口コミで評判のケーキ屋さんがある。
「やっぱ平日の真っ昼間だと、有閑マダムばっかりだねえ」
周りのお客さんを眺めて、叶さんが感想を漏らす。私はアップルティーの注がれたティーカップから口を離し、まったり気分を満喫しつつ蓮見を見る。
「……まだ不貞腐れてんの? ケーキバイキングにしなかっただけ、有り難いって思いなさい」
ぶすっとした顔を隠すつもりも無いのか、蓮見は手元のティーカップに口を付ける事も無くこちらを睨む。
「……前から言ってるけどな。機材を買うのに金がいるんだよ。それに『モラルと実利』だけどな、ここで奢って俺にどんなメリットがあるんだ?」
どうやら未だに納得していないらしく、口から出てくるのは恨み節ばかり。折角おいしいケーキを頂いているのに、そんな話ばかりでは台無しだ。
「人間関係って言うメリットがあるんじゃない? もしかしたらこの三人の中に、将来の彼女がいるかも知れない。そう考えたら悪い展開じゃないでしょ?」
本気でそう考えてる訳じゃ無いけど、男が女に奢るなら下心があるのは当然だ。だけど蓮見は三人の顔を見回して、深い溜め息を付いた。
「……はぁ〜っ。有り得ない話に喜ぶチェリーに見えるか? 俺がホイホイ付いて来たのは、敵とやらの情報収集の過程を報告しとこうと思ったからだ」
「む、本当はリラックスしたいんだけど、そっちも大事か。じゃあイヤな話は先に終わらせちゃおう」
敵に狙われている静ちゃんには酷な話になるかも知れないけど、身を守る上で必要なんだから我慢して貰うしか無い。既にケーキを平らげた叶さんが、口元を紙ナプキンで拭ってから口を開く。
「手掛かりなんて殆ど無かったんじゃない?」
しかし蓮見は、ニヤリと不敵な笑みを浮かべる。
「まあね。それでも考え方を変えるだけで、意外に多くの事が判ったりするもんさ。敵を探すって考え方じゃダメなのさ。探すのは、変化さ」
「何が違うの?」
私の問いに、蓮見は何故か周りを見回す。
「仮にあそこのマダムを敵じゃないかと疑ってみる。するとどうだ、そいつしか見えなくなる。これを仮想敵じゃないかと疑う余地のある行動やら事象やらに注意してみる。一人に限定せず、広い視野で観察しなくちゃならない。あくまで客観性で着眼点を探るのさ」
したり顔でそんな説明を並べ立てる蓮見の顔を、静ちゃんが初めてまじまじと見ているのが印象的だった。
「それで、どんな変化があったの?」
「色々さ。どれも小さな変化で、一つ一つは繋がらない事ばかりだ。しかし小さいながらも唐突な変化ってのは、必然性を悟られない様に偽装している可能性がある。例えば『光栄幸福教会』ってのはまさに、唐突な変化の典型例だよな。まさか教会の神父を、お前が殺したなんて誰も思わない」
そこで全員、動きがピタリと止まる。
私はぎこちない笑みを浮かべつつ、伺う様に蓮見に問う。
「……私はぶん殴っただけなんだけど?」
「そりゃ簡単に認める話じゃないよな。これはあくまで俺の推論だし。さらに空飛ぶ蛇の化け物なんてのが出現する始末だ。アレもお前がやったんだろ? そこから考えりゃ、神父も実は化け物でした、って話になる訳だ」
思わず絶句してしまう。
ケツアルコアトルを目撃しただけで、そこまで悟ってしまうとは。私が何かを言う前に、蓮見は先を続ける。
「敵は楯山静ちゃんを狙ってる。そしてアプローチの取り方は、それぞれ違う。ただ共通しているのは、そいつらはいきなり現れ、社会への存在の仕方が異質だって事だ。珍しいヤツがいたら、それだけで疑う余地がある」
蓮見の説明に、今までの事件を思い起こしてみる。『光栄幸福教会』はカルト教団だったけど、教会の建物は本物だった筈で、もしかしたらバロールは魔眼の力で本来居た筈の神父を支配し、教会を乗っ取ったのかも知れない。
対してケツアルコアトルはメキシコのマフィアのボスとして日本に来て、探偵ボクサーの鳴神を刺客として私にぶつけてきた。
確かにどちらも日本の社会に今までいなかった存在であり、神父やマフィアといった、一般的とは言い難い肩書きを持っていた。
「それで、アンタは何が言いたいの?」
理屈は判ったけど、肝心要となる敵の情報には行き着いていない。結局は何が言いたいのかよく判らないので、私の気分は何となく落ち着かない。
蓮見はまた例の、まるで目の前の何かを見詰める様な不思議な目付きで応じた。
「……珍しいヤツを見付けたのさ」

蓮見によるところの『珍しいヤツ』が敵なのかどうか、今から確かめてみる事になった。
ターゲットとなっている静ちゃんを連れて行くなんて危険過ぎると叶さんが反対をしたんだけど、蓮見は静ちゃんを対面させる事で何らかの情報が得られる筈だと主張し、珍しい事に静ちゃん自身が賛成した。
叶さんの運転するレンタカーで到着したのは、『八ヶ島ズーワールド』という巨大娯楽施設に隣接する、大型駐車場だった。
「いい加減、情報を小出しにするのはやめてくんない? そろそろ教えてよ」
車から降りてすぐに、私は蓮見を問い詰めた。『珍しいヤツ』がこのズーワールドにいると教えてくれたけど、それが何処の誰なのかまでは言わなかったのだ。
「そうよぉ。こうして静ちゃんまで矢面に立たせる以上、ちゃんと説明してくんなきゃ」
叶さんも不満をありありと顔に出して追及する。静ちゃんを見れば、何故かズーワールドのパンフを熱心に見ている。
「……イルカさん」
どうやら付属の水族館のイルカに興味があるみたいで、ポツリと漏らした一言に思わずズッコケそうになる。
「静ちゃんはイルカが見たいのか。ここのイルカショーは人気あるからな」
「あのねえ」
静ちゃんのイルカ発言に相槌を打つ蓮見を睨み付けてやる。するとやっと諦めたのか、溜め息交じりに説明を始める。
「はあ〜っ。別に言いたく無いってんじゃなく、あのケーキ屋じゃ人目があるだろ? 情報ってのは得るだけじゃなくて、漏れるのを防ぐ必要もあるんだ。誰が聴いているか判ったもんじゃないからな。車の中だって危ない。レンタカーなんて借り物じゃあ、盗聴器が仕掛けられててもおかしくない。そういう事だから、歩きながら話そう」
さっさと歩き出す蓮見の後を、三人一緒になって付いていく。駐車場脇から降りのスロープを歩きがてら、蓮見が先程の続きを口にする。
「ズーワールドってのは見た目、ただの複合娯楽施設だと思ってるだろ? だけど実は産官学の共同プロジェクトが根幹にあって、環境問題を軸とした研究施設が設けられているんだ。遊園地に動物園、それに水族館なんてものは、全てオマケに過ぎないのさ。研究施設には自然・環境・海洋・動物学者なんてのが招へいされてるんだぜ」
さすが情報通、一般人だったら全く興味の無い裏話なのに、ヤケに詳しい。
「要するに、娯楽施設で金を稼いで、その金使って環境問題を研究してるっつう訳。その副産物として、なるべく自然に近づけた動物達を見れる施設の作り方なんてのが出来る。北海道の動物園が人気って言うアレと同じだ」
そう言われてみれば、最近になって北海道のとある動物園が色々な工夫をしていて好評だって聞いた事がある。
「あ〜、あの動物園行ってみたいよね〜。雪の中でペンギン大行進とかさ」
私がそんな事を楽しそうに言うと、興味津々に静ちゃんが反応した。
「……ペンギンに囲まれて暮らしたい」
もしかして、静ちゃんって動物好きなのかな。
「ああいうのは、離れて眺めるのがいいんじゃないか? まあそんな事はどうでもよくて、『珍しいヤツ』ってのは最近になって研究施設に招かれた海洋学者ってヤツなんだけど」
「何が珍しいの?」
やっと本題に入ったと思ったら、これまた何が問題なのか判らない。いちいち説明するのは面倒臭い筈なのに、蓮見は辛抱強く先を続ける。
「アイルランド人と日本人のハーフの海洋学者で、名前は浦部美雪。日本国籍持ってるんで日本名を名乗ってる。まだ17歳なんだがアメリカで飛び級しまくって10歳で義務教育修了、15歳で大学院卒と桁外れの才媛だ。海洋学の博士号を修得し、日本で新設された八ヶ島海洋研究所にスカウトされた。たった二年の間に発表した論文は、国際海洋学会で高い評価を得ているんだと。それどころか、ノーベル平和賞さえ狙えるだとか言われ始めてる始末だ」
確かに珍しい種類の人間ではあるけど、それだけで敵対する『神』の一人であるとは到底言えない。
「珍しいのは判った。けど、それで敵だって疑う理由は何なの?」
「それは本人に会えば判るさ。差別だと思われるのも何だしな」
会えば判るとか差別とか、まるで判らない説明に私は首を傾げる。叶さんは違う疑問を持ったのか、難しそうな顔で蓮見に問う。
「その人と、どうやって会うつもり? 何のコネも無いのに、いきなりアポ無しで突撃しても門前払いされちゃうわよ」
だけど蓮見の顔には笑みが浮かぶ。
「手はあるさ。まあ任せてくれって。これで会えなきゃ外れ。会えれば疑惑はより深まるってな」

私達はズーワールドの入場ゲートで入場料を払って入場した。
平日であるにも関わらず、お客さんは多い。見れば子供連れのご夫婦や、カップルの姿もあって正直羨ましい。
受付嬢から貰ったパンフレットに載っている地図を見ながら、広大な人口島の中心部へと向かった。
ズーワールドは外周部に遊戯施設と水族館、内周部に動物園、中心部に研究施設があって、三つのエリアは水路が網の目の如く縦横に張り巡らされていて、お金さえ払えばボートに乗って移動する事も出来る。
蓮見に入場料も奢って貰い、さらにボート代までとなると、さすがにキレちゃうだろうから歩きで我慢する。
「俺達は学生服姿で、叶さんだけ浮いてるよな? これを利用しない手は無い」
歩きつつ事前に打ち合わせをして口裏を合わせようとの事で、蓮見が説明を始める。一人やり玉に挙げられ、叶さんは不満たらたらだ。
「え〜っ、私って浮いてる? まだまだ若いつもりなのに、ちょっとショックだわ〜。そりゃ、学生には見えないだろうけど、せめて引率で来てる新任の美人教師くらいには見えないかしら?」
何だか心配するところがズレてる気がしないでも無いけど、蓮見は顔を輝かせて指をパチンと鳴らした。
「そう、まさにソレだ! 引率で来てる美人教師。その設定でよろしく」
その言葉に、思わず叶さんをマジマジと見詰めてしまう。
「……叶さんが教師? う〜ん、敢えて例えるなら、現代の山師って感じだよ?」
「失礼しちゃうわね。根拠が無くて言ったんじゃないわよ。これでも、本当に教員免許持ってるんだから」
驚愕の新事実発覚。
ただのカバーストーリーのつもりが、資格だけとは言え真実になるなんて。
「……本当に?」
珍しく静ちゃんが目を丸くして叶さんに聞き返す。当の本人は、静ちゃんにまで信じて貰えなくてガックリと肩を落とす。
「ううっ、本当なのよう。これでも大学時代に社会科教師で教員免許取ってるんだから。二年前まで、三重で高校教師してたのよ」
そう言えば、叶さんは三重県の出身だって聞いた覚えがある。
「俺達は学校の社会見学の実行委員で、今回ズーワールドで社会見学をしたい。何でも捕鯨問題に詳しい世界的な海洋学者が勤務してるってんで、出来ればその有り難いお話を聞いてみたい。日本の神社にはクジラを祀っている所なんてのもあって、こちらの楯山静ちゃんは神社の巫女さんなので、捕鯨問題には感心を持ってるんですよ、と吹っ掛けてみる訳だ」
蓮見の立てた作戦に感心すると共に、いくらか心配事も浮かんでくる。
「成程、なかなか考えてるね。でも学園側に裏取られたらバレちゃうよね?」
普通の日本人ならあっさりと騙されるかも知れないけど、相手はアメリカ大統領をも輩出したアイルランド人とのハーフ。インテリジェンスの本家本元のイギリスのお隣の国でもあるし、確認はしっかりやってくると思った方がいい。
だけど蓮見も、インテリジェンス方面の人間。
インテリジェンスとは直訳すれば『知恵』だけど、諜報の世界ではスパイ活動全般を指す。
ニヤリと笑みを浮かべ、懐からケータイを取り出して素早い指使いでメールを打ち込む。
「――アイルランド人と日本人のハーフの海洋学者の調査開始。公安調査庁、対外防諜課の内部規定に添う第二種行動。外部特別情報調査官ロータスより、イチゴーイチマル時開始、っとな」
そのまま送信。
いきなりメール内容を口にしたので、呆気に取られてしまう。難しい単語の羅列に叶さんも静ちゃんも動揺に声が無く、その様子を見て頭が冷えてくる。
ウチの爺ちゃんがかつて防衛庁勤務だったので、蓮見とはそっちの方面で繋がっていたのかと理解が及ぶ。
やっと私は、単純な疑問を口にする事が出来た。
「……ろーたす?」
色々と聞きたい事はあったけど、一番感心を持ったのはその単語だった。蓮見は苦笑いで疑問に答える。
「別に口に出さなくても良かったんだが、一応説明しとこうと思ってな。ロータスってのは俺のコードネームな。蓮見の『蓮』がロータスって訳で、随分と安直なネーミングセンスだろ?」
「いや、まあそれは兎も角として。蓮見って政府のエージェントだったの?」
「誰にも漏らすなよ? スパイがスパイって知られたら、それだけで終わりだからな。それに政府直属って訳じゃあ無い。あくまで俺は外部のエージェント、要するに契約社員みたいな扱いだかんな。日本のスパイってのは外部に委託する事が多くてさ、オヤジが本職だからその関係でカウンター・インテリジェンス専門でやってんだよ」
カウンター・インテリジェンスとは、工作活動を防ぐ『防諜』の事を言う。
「今まで散々、自分はスパイだって言ってたじゃないの。バレたら終わりって、既にバレてるんじゃない」
私は今までに、蓮見の口から何度かスパイって言葉を聞いていた。何処までが本当で、何処からが真実なのかは判らないけど、本当のスパイにしては迂闊な発言が多い。だけど蓮見は、別段何でも無いのか涼しい顔で応える。
「本物のスパイが、自分はスパイですって公言する訳が無いって誰もが思うだろ。それを逆手に取ってるのさ。しかも、盗撮なんかで小銭稼いでるようなセコい学生だ。スパイに憧れてる狼少年、そういうカバーストーリーなんだ」
何に対するカバーストーリーなんだか。
でも確かに、今まで蓮見を本職のスパイだと疑った人間はいなかったような気がする。さすが悪党、悪党は悪党の心理をよく判っているって事かな。
「本日付けで叶さんは、桐琳学園の非常勤教師。教職の経験があるって調べは付いてたんだよ。ついでに三重県教育委員会の免許をこちらで即時発効。学園側への根回しも法務省から文科省、教育委員会と辿って完了。政府が主に中国の工作活動に危機感を抱いて安全保障を強化しつつあるからこそ、こういう強硬策が可能になったんだぜ?」
そういえば最近になって、防衛庁が防衛省に格上げになったり、日本版NSC(国家安全保障会議)を創設するとか聞いた覚えがある。普通の国家と同じく、国防を優先して連携を取れる体制に近付いたのかも知れない。
頭真っ白状態からやっと立ち直ったのか、叶さんが恐る恐る口を開く。
「……もしかして、本当に桐琳の教師やらなくちゃいけないの?」
「まあ非常勤とは言え、正規雇用だからな。ちゃんと給料が発生するし。いいじゃねーか、どうせ無職だったんだし」
なんだか酷い言い草だ。
途端に叶さんの頬がぷく〜っと膨れて、不満が爆発する。
「無職じゃないわよっ! 最近、五行リサーチってダミー会社作って、そこの社員扱いなんだからね!! 大体、教員って副業はダメなのよっ」
「おいおい、根回し済みだって言っただろ? そこら辺も、ちゃ〜んとカバーしてますよ。そもそも私立なんだから副業はオッケー。これからよろしくお願いしますよ、叶センセ」
蓮見の反撃に、叶さんの頭の中は再び真っ白へ。成り行きとは言え、本当に桐琳の教師になってしまうという展開には同情しちゃう。
「ううっ、ストレスから退職したのに……」
「それより本番だ。ここが研究施設らしいな」
蓮見の声に釣られて目の前に拡がる林を見上げると、木々の狭間から円筒形の大きな建物が覗いている。林の周囲はフェンスで囲まれていて、正門は開けっ放し。
警備は特に見当たらない。
正門から中に入り、林を抜けると研究棟の正面玄関に突き当たる。ずんずんと臆する事無く中に入る蓮見に導かれる様に、私も中に入った。
「はぁ〜い、お姉さん。そんな所にずっと座ってたら、お尻痛くなっちゃうでしょ? 良かったらボクと一緒に、ポージングの練習してみない?」
中に入ると受付の前で、変なポーズを取って受付の前に立つ蓮見の姿が飛び込んできた。右手で左頬を押さえ、左腕を横へと伸ばす奇妙な姿を見ると有り得ない擬音が聞こえてきそうだ。
「何をお馬鹿な事してんのよ。受付のお姉さんが困ってるでしょ?」
受付嬢は蓮見に釣られて立ち上がったまではいいものの、さすがに同じようなポーズを取るまでには到らなかったようで、引き攣った笑みを顔面に貼り付かせたまま固まっていた。遅れて中に入ってきた叶さんと静ちゃんは、何があったのか判らず訝しんでいる。
人が入ってきた事で我に返った受付嬢が、すぐに姿勢を正してにっこり笑みを浮かべた。
「……こちらは、八ヶ島海洋研究所です。アポイントメントがおありでしたら担当者の名前を申し上げて頂き、その他のご用件でしたら、こちらの用紙に必要事項をご記入の上、確認の後にご報告致します」
蓮見がポージングを解き、受付嬢の視線から隠すようにして背中の後ろに左手で合図を送る。それに気付いた叶さんが、蓮見の隣まで出て受付嬢の前に立つ。
「こんにちわ。実はわたくし、桐琳学園の社会科教師でして。こちらに有名な海洋学者の浦部美雪さんがいらっしゃるとの事で、是非お話を伺いたいと思いまして。生徒達の社会見学先として、このズーワールドをと考えておりまして、出来ましたら博士にご挨拶をさせて頂きたいのですが、お取り次ぎをお願い出来ますでしょうか」
事前に詳細を打ち合わせていた訳では無いのに、叶さんの口からスラスラと丁寧な説明が出てくる。だけど受付嬢はアポが無いと判り、一枚の紙を叶さんに提示する。
「ではこちらの用紙に必要事項をご記入の上、そちらのソファでお待ち下さい。担当の者に確認を取ります」
よくドラマとか漫画とかでは、アポが無いと即座に追い返されたりする描写があるけど、実際にはそんな横暴な対応はしないみたい。その場で用紙に書き込む叶さんの横で、蓮見が横槍を入れる。
「あ、備考欄には俺達全員の名前も記入しといて。まず社会見学実行委員って書いて、三年生の楯山静ちゃんから。用件は、日本のクジラ信仰と神社の係わり、それに現在の世界的な環境問題についての学習。午前中に地元の楯山神社を見学した後、ズーワールド水族館にて浦部博士の講演をお願いしたい、と」
浦部美雪を引っ張り出すには、楯山神社と楯山静ちゃんの名前を見せなくては話にならない。普通なら会うとしてもいきなり会える筈は無く、本人の仕事の都合次第となる。もしも浦部美雪が敵では無く、何も知らないのであれば今日会うのは難しい。
これが当たりだったら、神社の娘に興味を持つだろう。その場合は、自分の正体を悟られているのかどうか気になるだろうから、本当に社会見学の為に来ているのかを学園側に確認する筈だ。
用紙を提出し、私達はロビーの隅に置いてあるソファに腰を落ち着ける。
「さあて、薮を突いて蛇が出てくるのかどうか。蛇が出て来ても、みんないつも通りでいいからな。出来れば茶化してくれりゃありがたい。散々引っ掻き回してやれば、蛇はイライラして噛み付いてくるんだぜ」
蓮見の言葉から、どうやら自分が主軸となって話をするつもりだと判る。
インテリジェンスの分野にヒュミント(人的諜報)と言われるものがあり、今までの付き合いで、蓮見はその道に特に秀でているのを私は知っている。
ここは蓮見に預けるのが適当だろう。
5分位経って奥の通路から、一人の白衣姿の女性がこちらに向かって歩いてくるのが見えた。
「……どうやら当たりらしいな」
ニヤリと笑みを浮かべる蓮見の眼には、明らかに好奇心の色が伺える。女性が私達の側で立ち止まったのを見て、蓮見がソファから立ち上がる。
当然、私達もそれに倣う。
女性と言うか、外見的には随分と幼い印象で、17歳という実年齢よりも下に見える。それより驚いたのは、『全身の色素が薄い』と言う事だった。
「どうもお待たせしたみたいで、ご免なさい。私が浦部美雪です。こちらで主任研究員を努めています」
しっかりとした日本語で挨拶すると同時に、叶さんに手を差し出して握手を求めてくる。
「……会えば判るって、こういう事だったのか」
蓮見と叶さんの後ろで、浦部美雪に聞こえないように呟く。改めて彼女の全身を眺めて、蓮見の言いたかった事を理解した。
肩まで伸ばした比較的短めの髪は真っ白で、肌も雪の様に白い。それだけならそんなに驚かないんだけど、瞳が薄紅色に見える事で確信を抱く。
これは『アルビノ』と言われる先天的な遺伝体質に見られる特徴だ。日本では古来から『白子』などと呼ばれていたけど、現在では差別用語とされている。アルビノの人は皮膚のメラニン色素が殆ど無いので、直射日光を浴びると皮膚が火傷を負ってしまう上、瞳の色素も薄い為に眼球内で太陽光線が乱反射を起こし、視力も極度に低い場合が多いとされる。
彼女の幼さが残る外見はアルビノによく見られる事で、外で活発な運動が出来ない為に発育不全に陥りやすい。それでも普通に対応しているのを見ると、少なくとも視力は問題無さそうだった。
浦部美雪の特異な外見にいくらか戸惑った様だけど、叶さんも人懐っこい笑みを返しながら握手に応じる。
「わざわざお呼び立てして申し訳ありません。私立桐琳学園で社会科を教えています、桐内叶と申します。こちらはウチの生徒で、社会見学実行委員の者です。右から三年生の楯山静、二年生の崎守御空、男子生徒が蓮見卓郎です」
「これはご丁寧に。どうぞ座って下さい」
手で座る様に促され、皆がソファに腰を降ろす。浦部美雪女史はローテーブルを挟んで、対面側のソファに腰を落ち着ける。
見た目では実年齢よりさらに若く見えるけど、話振りや表情を見ていると精神年齢は高いと思う。デニムのマイクロミニに黒いニーソックス、さらにエンジニアブーツという格好の上から白衣を纏っていて、研究者らしからぬ印象だ。
今までの敵、バロールやケツアルコアトルは人間の姿をしていても、『心眼』でエネルギーの運用の違いを見る事によって『神』だと看破出来ていた。だけど彼女からはそういった特殊なエネルギーの流れは感じられず、現状では怪しむべき理由が見当たらない。
静ちゃんの名前を聞いても、特に怪しい素振りは見られなかった。叶さんが教師役なのだから、浦部美雪は当然の様に叶さんに顔を向ける。だけど話を切り出した者は、全く予想していない方向にいた。
「いやあ、まさか『未来の』ノーベル賞受賞者と、こんなレジャー施設のど真ん中で会えるなんて思ってもいなかったなあ」
軽い口調で横合いから茶々を入れる蓮見に、美雪は少しだけ眉根を寄せた。しかし相手はまだ学生、真面目に取り合わない方がいいと考えたのか、僅かに口元を綻ばせた。
「ふふ。確かに場違いかも知れないですね。『未来の』受賞候補者が『こんな』ところで、果たして有意義な研究が出来るのかと、そんな心配をして下さってます?」
皮肉には皮肉で応酬。
蓮見の仕掛けた心理戦に、敢えて乗っかってやろうとでも言うのか。そんな反撃を当然の如く想定している蓮見は、待ってましたとばかりに応戦する。
「まさか。若いながらも着実に実績を積み重ねてきた結果だと言うのに、それを蔑ろにする様な心配は、返って失礼ってもんだ。俺が興味を持っているのは、捕鯨反対派の急先鋒とも言える浦部女史が、日本で何を研究してるんだろうって一点さ」
建前上はあくまで社会見学のお願いだと言うのに、いきなり確信を突く。相変わらず蓮見は、相手どころか味方すら予想していない行動を取るヤツだと思った。美雪もさすがに論点がズレているのを感じたのか、困惑しつつも話を本来の方向へ戻そうとした。
「本日は確か、社会見学で私に講演をお願いしたいとのご訪問でしたよね? さすがに現在の研究内容を申し上げる訳には参りませんので、まずは社会見学と講演の内容をお聞かせ下さい」
「こりゃ失礼。叶センセ、後はお任せします」
両手を挙げて降参したかの様なポーズを取り、あっさりと引き下がる蓮見。いきなりバトンを渡され、叶さんは困ったような顔をして話を引き継ぐ。
「どうもすいません〜。好奇心旺盛な生徒でして、どうかご容赦下さい。それでは社会見学の趣旨と、予定している見学コースから説明させていただきますね」
さすが元教師、ぶっつけ本番でそれらしいアドリブがスラスラと出てくる。
「日本の歴史と食文化、近頃は捕鯨問題やマグロの世界的な需要など、環境に与える影響も大きいと聞きます。桐琳学園の所在地である鎌鍬は、古くから神社仏閣の多い地域でして。よその地域の話になりますが、クジラを祀っている神社もあるくらいなんですよ。日本の伝統文化を学びつつ、しかし世界の潮流も同時に学ぶという趣旨ですね」
叶さんは社会科教師としての経験と、修験者としての知識があるのでアドリブが効く。今回の交渉役には適任、それが蓮見の目論見にぴったりなんだろう。
浦部女史は頷きながらも、その表情は硬い。
「成程、とても素晴らしいお考えかと思います。ですが、捕鯨を容認する文化を学び、同時に捕鯨反対派である私の講演を開くのでは、少々矛盾しませんか? 私は研究者であって、教育者ではありません。あなた方のご期待に添えるかどうか」
しかし叶さんは、微笑みを絶やさずにやんわりと応じる。
「それが世界の潮流なのですから、現状をありのまま伝えるのが教育者としての考えです。只今おっしゃられた矛盾とは、同時に世界の矛盾であると認識しています。ですがどちらも否定せずにいれば、生徒達はバランスを取るでしょう。例えば、こちらの楯山静の家は神社です。ですが彼女は、生まれてから一度もクジラを食べた事がありません。判っていただきたいのは、生徒達にクジラを食べる事の是非を問いたいのでは無く、あくまで自然環境への配慮の重要性を認識して欲しいのです」
なんだか至極ごもっともな説明で、今までの叶さん像がぐるり百八十度変わってしまう程だった。
浦部女史は海洋学者だから、別に捕鯨問題のみに感心がある訳じゃ無い筈で、海洋生物の生態系全般に対する冷静な視点も持ち合わせている筈だ。それでも敢えて捕鯨反対派を標榜しているのだから、彼女には彼女なりの論拠があるのだろう。
「先生のおっしゃられる事には、概ね同意出来ます。私は何も、感情論で否定している訳ではありません。捕鯨反対派に担ぎ上げられているだけで、私の主張と完全に一致している訳では無いのです」
どうも私の考えていた人間像とは、少し違うみたいだ。過激な環境保護団体や動物愛護団体の与えるイメージの所為か、捕鯨反対派と聞くと一方的な主張をするものだとばかり思っていた。
「私の主張は、家畜とクジラを同レベルで扱えないと言うものです。肉牛の生産に問題があるのは判りますが、家畜は人の手で、ある程度コントロール出来ます。しかし、クジラやイルカは数のコントロールが難しい。そのような状態で食肉としての市場を形成しては、生態系のバランスに深刻な影響を与えます。海洋における食物連鎖の頂点であるクジラ、その影響は全体に拡がります。個体数の多い魚とは、次元が違うのです。満足のいく調査結果が得られるまでは、調査捕鯨すら控えて欲しいのです」
どうやら研究者として、まずは調査を優先してその結果如何で、結論を出したいと考えているようだ。
浦部女史の言い分には、納得出来る。
牛や豚は食物連鎖の頂点では無いけど、クジラは海洋生物の頂点にいる。その視点で考えるなら、もう少し慎重に調査をした方がいいのかも知れない。
それに日本だけが捕鯨推進派な訳じゃなく、アイスランドやノルウェーなんかは既に商業捕鯨を再開している。捕鯨反対派が日本を集中的に非難するのは、単に叩きやすいからだろう。叩かれたからと言ってこちらも感情的になっては議論が進まないので、あくまで客観的な立場を維持しなくちゃならない。
そこで一旦発言を引っ込めていた蓮見が、口火を切る。
「それでアンタは、日本の伝統文化にはどの程度理解があるんだい?」
蓮見の鋭い眼光に、浦部女史は鷹揚に頷く。
「それこそが、今の私の関心事です。クジラを神社に祀る。それは欧米には理解の難しい理屈です。日本と言う国は、死んだ人間の魂を信仰の対象としているのは判りますが、捕まえて食べたクジラを敬うと言うのは、とても不思議な感覚だと思います。実はそこに、感情論に終止符を打つ手立てがあるのではと思うのです」
もしかして、それが日本に来た理由なんだろうか。
だとするとちゃんとした理由があって、彼女は『敵』では無いのかも。私がそう思い始めている一方で、蓮見は未だに好奇の視線を崩してはいなかった。
「日本人は、自然に感謝するからな。最近はアレだが、伝統的に食事への感謝の気持ちが、自然信仰と結びついている。だから神社は存在するし、神もまた、そこら中にわんさかといるのさ。そこの神社の娘は、その文化を背負ってるから生きている。食事を単なる消費行動としか捉えていないから、理解出来ないのさ。自然の恵みによって生かされている、その感謝の気持ちがあるからこそ、有名な『もったいない』が生まれたのさ」
そこでようやく、浦部女史が静ちゃんの顔を見た。
神社の娘――まるでその場にいる事が象徴的な意味を持っているのか、静謐な印象が浦部女史の視線を釘付けにする。
「クジラを食べた伝統は、信仰ありきと言う訳ですね。だとすれば日本は、環境問題で世界の担い手となるべくグローバル・スタンダードを提唱していくべきでしょう。日本の環境技術が優れている事は、既に知られています。世界の信用を勝ち取る、それこそが求められている日本の役割だと思います。信仰とセットであるのだと、神社すら輸出するくらいの気概を見せて欲しいものです」
神社すら輸出しろとは、物凄い理屈だ。
信仰は自ら選ぶものであって、押し付けるものじゃ無いと思う。でもまあ、こういう考え方なんですよとアピールするのは必要なんだろう。そういう意味で、捕鯨反対国に神社を造り、神主を派遣してロビー活動してみたら面白いかも知れない。
「だとさ。神社の側の人間として、そこら辺、どう思った?」
いきなり蓮見に話の矛先を向けられ、ただでさえ口下手の静ちゃんは戸惑いを隠せない。そういう時は、私が助け船を出してあげる。
「いやいや、いきなり神様を輸出なんて、日本人の奥ゆかしさに反するってば。寧ろオタク文化として、巫女さんルックの美少女を輸出するところから始めたらいいんじゃない? メイド喫茶ならぬ、巫女喫茶とか。日本の神社は、もっと巫女さんを有効活用するべきだよね。いっそ静ちゃんがクジラ神社の巫女さんになって、アイルランドに乗り込めばいいんだよ」
全然、助け船になっていない。
「……何処が奥ゆかしいんだよ」
すかさず蓮見のツッコミが入るけど、私は奥ゆかしいので反論なんてしない。静ちゃんはモジモジしながら、辛うじて口を開く。
「……そんなの、恥ずかしいよ」
きっと私でも、やれと言われたらイヤだと答える。流鏑馬神事だったらやってもいいけど。そんな静ちゃんの様子を眺めながら、蓮見が何気無く口を開く。
「そういや、アイルランドだって大昔にケルトの信仰があったんだよなぁ。ドルイドだっけ? まさに自然信仰だったんじゃないか。確か、ケルトの水の女神の信仰が、イギリスのバースと、それからドイツにもあったんじゃなかったか?」
まるで話のすり替えだと言うのに、とても自然な話題に思えてしまう。茶化すだけ茶化し、話を掻き回してチャンスを作る。ここが勝負所だと、蓮見の『勘』が働いたのかも知れない。
浦部女史は何ら疑問を持たなかったのか、その話題に乗る。
「実はアイルランドでは、ケルト信仰を復活させようとする動きが小さいながらも存在します。海洋学者となって、カトリックである事の限界を感じました。人間愛は素晴らしいものですが、それを唯一不偏の摂理と説くだけでは、自然への視点に欠落があります。そういう意味で、日本の信仰にはとても興味を持っています。日本語も頑張って覚えましたし」
話を聞く分には、何処もおかしいところは無い。それでも蓮見の確信は、全く揺るがない。
「って事は当然、神社についても色々と調べているんだろうなぁ。知ってるかい?京都には、浦島太郎を祀っている神社があるんだぜ。横幅にもあったらしいが、大正時代に燃えて無くなっちまったんだ」
なんでいきなり、浦島太郎の話題が出てくるんだろう。
「……もしかして、海繋がりだから?」
ケルト信仰復興運動に絶賛協力中の海洋学者が、日本の神社についてお勉強中。だったら当然、海のお伽話である浦島太郎を祀っている神社の存在を、知らない筈が無いとの事なのか。
だけどその話題が、『敵』を見破る役に立つとは到底思えない。蓮見は例の、目前の何かを見詰める様な目付きで口を開く。
「日本で海の信仰と言えば、やはり浦島伝説だろ。丹後国の浦島の子が、浜辺で助けた亀に連れられて、竜宮城で乙姫と三年暮らす。しかし両親が心配になり、陸へと帰るが家は無く、両親の姿も見当たらない。実は陸では400年もの歳月が流れており、茫然自失となった浦島太郎は、乙姫から貰った玉手箱を開けてしまう。玉手箱からは煙が立ち上り、それを浴びた太郎は一気に老人となってしまった。鶴になったとか、そのまま死んだとか、諸説あるな」
日本人ならば、誰でも子供の頃に、一度は必ず聞いた事があるお伽話だ。相手はアイルランド人とのハーフだから、もしかしたら知らないかもと思って一応の解説をしただけかも知れない。
だけど小説『怪談』で有名な小泉八雲は、ギリシャ人とアイルランド人とのハーフだったそうだ。イギリスから来日し、日本人の女性と結ばれたラフカディオ・ハーン。
自身のルーツと、それに重なる日本のお伽話、そして怪談。きっと小泉八雲は、自身に流れるルーツを根拠として、日本の自然崇拝に共感してしまったのだろう。それと同じ事が、浦部女史にも起きているのかも知れない。
「有名なお伽話ですね。日本の神社が祖先を祀っている事を考えれば、浦島太郎が実在の人物だとしても、おかしくはありません。そういった信仰を今でも継承しているのは、とても羨ましく思います」
海洋学者なのに、宗教学者みたいな事を言う。
それでも、自身のライフワークに必要なテーマだと捉えているらしく、浦部女史は会話を楽しんでいる様に見える。
これが蓮見の誘導の結果なのだとすれば、狙い通りの会話に持ち込めていると考えていいのかな。だからこそ蓮見の切れ長の眼に、確信を得た者特有の瞳孔の拡がりが垣間見えたのだろう。
「たかがお伽話、真剣に研究してるヤツなんていやしない。だが、浦島太郎には単純だからこそ、不可解な謎が隠されているんだ」
蓮見が何を考え、何を言いたいのか、まるで判らない。それは蓮見以外の全員に当て嵌まり、沈黙を以て次の言葉を待ち受ける。
「誰もが陥る罠だ。浦島太郎の末路は、諸説あっても結末まで語られている。それはおそらく、陸の人間側の話だからなんだろう。だが、乙姫はどうなったんだ? そして乙姫という存在は、浦島伝説でしか伝わっていないんだ。俺にはまるで、唐突に日本に出現した様に感じてならない。乙姫伝説は、一体何処から来たんだ?」
そんな事は、今まで考えた事も無かった。どうしてこんな話をしてるんだか、だけど何かが引っ掛かる。何かを掴みかけているのに、何かが邪魔をしていて結論まで行き着かない。得体の知れない気持ち悪さを感じ、しかもそれが、浦部女史だけで無く、蓮見に対しても感じている。
蓮見は公安調査庁の外部委託スパイ、しかし私の『勘』が、それだけでは無いと告げている。
それを黙って聞いていた浦部女史が、蓮見の真意を探ろうとその眼をじっと見ていた。
「……私は専門家では無いので、それ以上のお話は理解が及びません。ですが、私にも別の疑問があります。神社は先祖を祀る。ならば浦島太郎の子孫がいても、おかしくは無いのでは? 竜宮城での時間の進みが遅いのであれば、実は乙姫がまだ生きていて、浦島太郎の事を思い続けている。そんな結末だったとしたら、乙姫を探してみると言うのも面白いかも知れませんよ」
浦部女史の論理の組み立てに、蓮見の顔から力が抜ける。途端に普段通りの、不真面目そうな蓮見に戻っていた。
「冗談じゃない。玉手箱で年寄りになりたくは無いね。もしも乙姫に出会ったら、こう伝えてくれよ。人の人生を、弄ぶなってな」


第九話・乙姫伝説