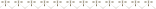Sick City
第三章・夢幻迷宮
暗闇に包まれた通路。
光源となるものが無い中、俺は『心眼』を頼りに周辺の状況を確認する。
――周りには、誰一人として人がいなかった。
通路の幅はおよそ5メートル程度、天井までの高さも同じくらいか。通路は石造りで全て同じ大きさ、重さの石が使われている。その石は極めて比重の重い物質らしく、石の組み合わせ方がピラミッドと同じような構造になっており、重力が効率良く増幅されている印象を受ける。
どちらにせよ、かなり高度な技術が用いられている事が判る。それにしても野次馬連中はともかくとしても、エリカとミノタウロスは何処へ行ったのか。
通常レベルの『心眼』では感知出来ない事から近くにはいない。この通路の前後はどちらも十字路になっており、この周辺は随分と入り組んだ構造になっているようだ。
それも含めて考えると、広範囲の感知をする必要がある。一体どんな場所に飛ばされてしまったのか、そしてこの構造物の出口、エリカやミノタウロスの現在位置などの情報は必要だ。
そう考えて『心眼』の認識を最大限まで高める。
「……やはり接近戦に引き込んでるな」
ミノタウロスは比較的大きな空間で、エリカと戦闘中らしかった。
半円状のドーム型の穹窿天井を持つ円形闘技場。
実際のところはどうなのか判らないが、印象としてはその言葉が適当に思える。大きな空間とは言っても、天井までの高さは10メートルあるかどうかと言うところなので、エリカが空中から一方的に攻撃しようとしても、ミノタウロスの脚力ならジャンプして届いてしまうだろう。
エリカもそれで接近戦に応じざるを得ない状況になり、苦しい戦いの最中だった。分の悪い戦いだが、それでもいきなり敗ける事は無いだろう。それよりも気になるのは、どうやら俺達がいるのはあの壺の中らしい、と言う事だ。
別に俺達が小さくなった訳じゃないし、壺自体が大きくなったと言う訳でも無い。どういう仕組みかは判らないが、壺の中は疑似的な異次元空間であり、二重構造のダンジョンになっているのだ。
瓢箪みたいな壺の形状が二重構造の表れであり、上下の迷路を中間に存在する螺旋階段が繋いでいる構造だ。下の迷路の最下層には巨大な空間が広がっており、そこには巨大な石造りの扉が存在する。対して上の迷路の最上階には壺の口があり、俺達はそこから入ってきたと思われる。
だがその口は現在は閉ざされており、ここから出るには最下層の扉を開けなくてはならないのかも知れない。巨大な石造りの扉を開けるのは俺には無理だろうし、エリカも通常の人間より力が強いのだが、それでも無理だろう。おそらくは、ミノタウロスだろうと開けるのは難しいだろう。
エリカとミノタウロスがいるのは螺旋階段を降りたところの踊り場の手前の部屋だったが、俺の現在位置からはかなり離れている。それからこの迷宮はトラップだらけで、この時にも野次馬連中がバタバタと死んでいる。
そういえばあの少女はどうしたんだろう。
そう思って探ってみたら、彼女だけは螺旋階段を降りる手前の部屋におり、どうやら無事のようだった。考えてみればミノタウロスの連れなのだから、安全を確保されているのは別段おかしくは無い。
どちらにしても俺がエリカと合流する為には、トラップをくぐり抜けて少女のいる部屋を通らなければならない。全体像が既に判っているので、安全かつ最短のルートを導き出す。この迷宮を造った者が、どういった設計思想を持っていたのかがなんとなく判る。
弱者はトラップで死ぬが、より強く、賢い者は部屋まで到達してしまう。
そして何の為に部屋が存在するのかと考えると、おそらくはミノタウロスの戦場となっているのだろう。部屋に到達しても、ミノタウロスと戦わなくてはならないのだ。
ただ全体で、三つの部屋があるので他にも門番らしき存在がいた可能性もあるし、ミノタウロス自体が最後の門番として最下層の部屋に配置されていたのでは無いか、とも考えられる。
そして最下層に先の判らない扉がある事を考えると、そこが守るべきモノである筈だ。
気になるのは扉の先に何があるのかと言う事になるのだが、『心眼』を以てしても、その先を感知する事が出来ない。この迷宮が単に敵を誘い込んで殺す為のものなら、そんなモノがあるのはおかしい。
だが実際に存在している以上、この迷宮の存在意義は全く別の方向性を示しているのだ。が、それが明らかになる事は無いだろう――今は一刻も早くエリカと合流する事を考えるべきだ。
俺は『心眼』を最大限に使い、ゆっくりと石造りの回廊を歩いていった。
本当ならば一気に駆け抜けたいのだが、いくら『心眼』があるとは言ってもトラップの知識に乏しいのでは、必要以上に慎重にならざるを得ない。
『心眼』は物質の構成を極小化、エネルギー運動を精彩に感知出来る。
しかしトラップを見抜けるかどうかは別問題だ。確かにトラップの起動をいち早く見抜く事は出来る。しかしそれはトラップを作動させてしまった、という事であり、事前にトラップの存在を的確に把握するのは専門知識が必要になるのだ。
例えるならば、箱を発見してもそれを箱だと判断出来る知識が無くては意味が無いのと同じ事。だから罠と思わしき、不自然な兆候を一瞬でも見逃してはならない。結局は慎重に行動しなくてはならないのだ。
だがそのおかげか、回廊の石壁にレリーフが描かれているのを発見した。
「――これは」
なかなか興味深いレリーフだった。
俺の様な極めて平凡な知識しか持たない者にとっては、的確な語彙で表現出来る類いのものでは無さそうだったが、敢えて言葉を選ぶならばヘレニズム文化と言うものだろうか、そういったギリシャの遺跡を想起させる技法によるもののように見えた。
そこに描かれている物語は、世間一般に知られているギリシャの伝承を真っ向から否定する様なものだった。
総じて語るならば、それはギリシャの歴史などでは無い。もっとそれ以前、ギリシャへ到る前文化が大西洋に存在した事を示す内容を含んでいた。
それは古代ギリシャの哲学者プラトンが『クリティアス』『ティマイオス』の二編の著書に記した、かつてジブラルタル海峡の遥か西に存在したと言われる、伝説上の都市の話なのだ。
――その名は、アトランティスとして知られている。
紀元前8世紀頃に成立したと言われる古代ギリシャ文明に先立つ事さらに五千年もの昔、大西洋に浮かぶ、肥沃な土壌を有した島があった。
同時期には遥か東の、今で言う東南アジア――ベトナムからカンボジア、タイ、マレーシア、インドネシアのスマトラ島にかけて、人類最初の文明が誕生した。それはレムリア大陸、もしくはムーとして伝わる、日本を含む、環太平洋の全ての文化の発祥でもあった。
遠く離れた二つの文明は、やがて自らに訪れる運命を悟る。
地殻変動によって引き起される、地震と大津波。しかしその直接の原因は、外宇宙より飛来した天地を貫く巨大な一本の軌跡であった。
それは巨大な剣として描かれている。
レリーフを描いた者が何を意図してその様な表現を用いたのかは定かでは無いが、おそらくは宇宙の彼方より飛来した隕石が地上へと落ちたのだと解釈すべきだろう。
彼らには取るべき道が二つあった。
一つは自ら築いた文明を放棄し、地震も津波も無い安住の地を目指して長い放浪の旅へと船出する事。
結果、東の王国は太平洋に散らばり、中国の黄河文明を経由して北上した者はアラスカ経由でアメリカ大陸のネイティヴ・アメリカンから中南米へと到り、日本列島においては沖縄、縄文、アイヌへと繋がり、南下した者はニューギニアやミクロネシアなどに散開し、外洋を船で渡り歩いた。
東へと向かう一団がいる一方、大陸を西へ移動した一団はインド・パキスタンにてインダス文明を築き、さらにイラクにてシュメールへと合流する。
西の王国から逃げ出した人々はギリシャ文明の基礎となり、南下した者たちはやがてエジプト文明を、東を目指した者たちはシュメール、インダスと合流した。
もう一つの選択は、さらなる高みへと到る試みであった。どういった道程を経たのかは描かれていない。それこそが『神』の誕生であった。
人間の肉体を捨て、死を選んだ彼らは遥か天空から地上の人々を守護する。
海中に没した両王国の最後の住人達は、『神』の住まう天上へと召された。
ここで一つの物語は終焉を迎え、次の物語へと移る。自らが率いる民を失った『神』は、移住先で定住した者達を援助した。やがて移住先の住民の中より選抜された者が、新たに神々の列へ加わった。
その中に、獣の姿をした『神』を見付けた。
人々の頭上に記された獣達。天空を舞う鳥達の下には、遠吠えをする犬と狼。
中心には一際巨大に描かれた、人間の身体を持った牡牛がいた。
彼ら獣の神はかつて人であったものの、死して神へと到った過程で獣と同化し、獣特有の本能を有する人間の理解を超える存在であった。彼ら獣の神を信奉したのは、自然崇拝の民族達が中心だった。
やがて三度目の『神』の誕生を迎える。
三度目に誕生した神々は獣の神を間違った存在であると考えて敵対し、追放し、捕え、殺した。
そんな中で鎖によって捕えられた姿で描かれているのは鳥の神や牡牛の神、それ以外にも蛇の神などもいた。
ギリシャのテッサリア、マケドニアに跨がる山の頂きから、オリンポスは打ち上げられた。オリンポスにて幽閉される獣神だったが、やがて役割を与える事で釈放された。その中で牡牛の神は、オリンポスの門番として配置された。
――そこで物語は終わっていた。
どうやらこれらのレリーフによって判るのは、ミノタウロスとは本当に『獣神』と呼ばれる種類の神なのだという事だ。
そういえばアイヌの伝承には熊の神なんてものがいるくらいだし、実はそれ程珍しい事では無いのかも知れない。ネイティブ・アメリカンに到っては、狼やコヨーテなどを神聖視する。
何やら感慨深いものがあるが、レリーフの描かれた回廊を脱けると足元の石床の厚みの下に、不自然な空洞がある事を感知した。どうやらトラップらしく、特定の石床を踏むと作動する落とし穴の様だ。
俺はその石床を跳躍して飛び越え、無事にトラップを回避した。このトラップさえ脱けてしまえば少女のいる部屋は目前だ。前方に仄かな光が漏れているのが見え、慎重に近寄ると部屋の入り口の開口部に到達した。
何の躊躇も無く部屋に入ると、天井にいくつか菱形の水晶体のような照明器具が取り付けられており、少なくとも部屋全体を見渡せるくらいの明るさが確保されている。
俺が入ってきた開口部とは反対側の、螺旋階段に通じている筈の出口前に、あの少女が突っ立ていた。俺の姿を見て一瞬驚いた顔を見せたものの、すぐに俺が普通で無い事を思い立ったのか、顔を引き締めてこちらを睨んだ。
「ちょっと驚いたネ――でも、この先にはいかせられないネ」
そう告げると、何やら奇妙な構えを取った。両手を後ろへ拡げ、両足を交差させつつ姿勢を低く保つ。丁度、鳥が飛び立つ間際とでも言おうか、そんな姿を連想させた。
「やめておきな。お前じゃ俺は止められない」
少女はおそらく、何か中国武術の使い手なのだろう。どうして俺達が戦わなくてはならないのかと訝っていたのだが、少女はそんな俺などお構い無しに突進してきた。
「チュオジェオメン! ユアンヤンジェオ!!」
どうやら中国語の様で何を言ってるのか判らなかったが、瞬間、脳内にアカシックレコードによる日本語訳が閃いた。
戳脚門・鴛鴦脚(たくきゃくもん・えんおうきゃく)。
中国武術においては、足技を得意とする戳脚拳の中でも歴史に残る、有名な絶招が鴛鴦脚だ。かの有名な『水滸伝』の主人公の一人、行者・武松(ぶしょう)が得意とした技だと伝わっている。
その技、華麗にして迅速――。
低姿勢になりつつ交差した左右の脚を中心に、背中を向けて反転、後ろ蹴りが足元から跳ね上がってきた。大地を蹴って俺の顎へと跳ね上がる、独特の蹴り技。それを反転して軽く躱すと、すぐさま次の後ろ蹴りが繰り出される。
躱し続ける俺と、連続で後ろ蹴りを繰り出し続ける少女。どうやら六種類程度の変化があるらしいが、それに加えて突きを連続で放ったり、或いは掌が下段から襲いかかってきたりと、実に多彩な武術だ。
だが相手の直線上に殆ど立たないように連続反転運動で回避する俺を捉え切れず、単純な格闘では敵わないと悟ったらしい。
「――把ッ!!」
玉環歩鴛鴦脚と呼ばれる接近しながらの後ろ蹴りを反転して躱した俺に対して、少女は軽くステップしながら足を入れ替えつつ着地し、屈みこみながら伸び上がるような貫き手を繰り出した。
その掌に、きらりと光を反射する尖端があった。後退して躱した俺の鼻先、紙一重のところに針のような鋭い隠し武器が見えた。
「まだネ!!」
少女はくるんと背中を見せて反転し、逆さ向きに跳躍して距離を開ける。
空中で拡げた両手から、何かが飛んでくる。おそらく中国の武器だろうが、日本で言えば、ちょうど苦無(くない)と呼ばれる手裏剣に酷似した投げナイフだった。合計六本の手裏剣を全て掌で叩き落とした俺を、少女は驚愕の表情で見た。
「暗器使いってヤツか?」
暗器とは、中国では暗殺用途に特化した隠し武器の事だ。殺し屋とか、清代の隊商護衛とかが好んで使ったと言われている。さすがにここまでやられては、俺としても黙ってはいられない。
瞬時に間合いを詰めてきた俺にぎょっと驚いた少女は、一気に後方へ跳び、壁を蹴って三角跳びで頭上を飛び越えた。
空中から繰り出される蹴り。
俺は蹴り脚を左手で巻き込んで、一気に後ろへ駆け抜けた。体重の軽い少女は空中にいた為に回避出来ず、バランスを崩して弾き飛ばされる。
「ッ!?」
くるんと回転して背中から床に叩き付けられる寸前、少女は驚異的な柔軟性で両手から床に着地し、逆立ちのまま開いた脚を回転させて蹴りを放つ。
俺は感心しつつもその蹴りを紙一重で躱した。
だが後ろからもう一方の脚が飛んできて、まるでヘリコプターのプロペラの様な蹴りがさらに襲ってきた。しかしそれでさえ俺は瞬時に見切り、頭を下へと潜らせて難なく躱した。
「あッ!?」
それと同時に、俺は脚を滑らせて少女の両手を払った。今度こそ少女はバランスを崩し、背中から床に転がる羽目になった。それでもすぐに体勢を建て直し、転がりつつも俺から距離を取って立ち上がる。俺との力の差がやっと判ったのか、警戒して手を出して来ない。
「――何故、お前は戦おうとするんだ?」
俺はずっと疑問に思っていた事を口にしてみた。少女は少し躊躇ったが、状況が不利な為か、呼吸を整えつつも口を開いた。
「お前、じゃナイネ――ワタシ、名前リャン言うヨ」
どうやらお前お前と言われるのが不快だったらしく、聞いてもいないのに自ら名前を名乗ってきた。リャンと名乗った少女は俺の動きを見切りたいらしく、俺の呼吸すら注意深く観察していた。
「ではリャン。俺と戦う理由なんて無いんじゃないか?あの牛野郎を説得してくれるなら、俺達はいつでも戦いを止める事が出来る」
だがリャンは頭を僅かに振って否定の意志を表す。
「無理ネ。ツァオシン戦い好き。ワタシ止められないネ」
それでもこうやって俺の話を聞いてくれるあたり、少しは態度が変わってきたようだ。取っ掛かりを得たと踏んで、さらに口を開く。
「戦う理由がある筈だ。戦いを辞めるなり、続けるなり、理由も聞かずに戦えと言われても、はいそうですか、とならないだろ」
無理と言われたので、こちらも言い方を変えてみた。それが功を奏したのか、リャンは少し顔をしかめてみたが、それでも応えてくれた。
「オマエ判らないネ――お金、困った事あるか?」
今度は俺が、対応に困って固まってしまった。まさか金に困って戦ってるという訳では無いだろう。それでも戦う理由の切っ掛けの一つ、程度の話で、半ば謎掛けみたいな色を感じた。俺が反応しないのを見て、リャンは話を続ける。
「日本人、お金持ってるネ。ワタシ達、貧しかったヨ。ツァオシン強い、お金稼げる。ワタシ、ツァオシン友達」
そこまで聞いても俺には戦う理由として弱いと感じた。
何か違和感を感じる。
金が欲しければ普通に働けばいいし、その方が命の危険が無いだけマシな筈だ。
「……誰かが何か言ったんじゃないか?」
俺はある仮定を立ててみた。
誰かが戦う理由を提示したのなら、金絡みだとしても理由として説明が付く。そして俺の見立てが間違っていない事が、リャンの口から出てきた。
「サングラスの男が言ったネ。宝持ってるヤツいる、持ってくればお金いっぱい出す。宝持ってる強いヤツ集まって戦ってる」
――サングラスの男。
俺はそれを聞いて、ビデオカメラを回していたあの黄色いサングラスの男を思い浮かべていた。そういえば――アイツはこの迷宮の中にいない。
野次馬連中はみんなこの迷宮に引きずり込まれたのに、あの男とメイド服の女達がここにはいないのだ。
それに宝と言うのも気になる。
俺はともかく、エリカは宝なんて持っているのか?
だがメフィストフェレスは、エリカが目覚めて意味がある、とか言っていた。もし、神と呼ばれる連中が何か価値のあるモノを持っていて、ゲームとやらが宝を取り合っているのだとすれば、この戦いにも意味がある。
どうやら真相が、少しずつ判ってきたようだ。
しかし今は目の前にいるリャンと、ミノタウロスをどうにかしないとならない。俺は機転を利かせる事で、この戦いを回避しようと考えた。
「俺達は、宝なんて持ってないぞ?」
俺の口から飛び出た言葉に、リャンが唖然としてしまった。それはそうだろう。ミノタウロスはともかく、金にならない戦いをする理由はリャンには無い筈。
「――ホントか?」
リャンは半信半疑と言った感じで聞いてくる。実は俺にもエリカが宝を持っているのか、それとも持っていないのかはよく判らないが、この場ではそう説明するのがベストだろう。
「信じるかどうかはリャン次第だけど、俺達だって宝があるなら戦ってるさ。でも持ってないから戦う理由が無い。宝を持ってるヤツは持ってないヤツと戦うか? 戦わないだろう」
まるで詭弁だが、理屈は通っている。果たしてリャンは納得するのか、正直なところ賭けだった。だが金に執着しているリャンに対しては、俺達も金が欲しいとアピールすれば理解出来る筈だ。
「……判ったネ。ツァオシン止めてみるネ」
リャンはそう言うと構えを解いた。やれやれ、内心疲れるが、そうも言ってられない。
「良かった。それじゃあ下へ行こう」
俺はリャンを促して螺旋階段へと歩く。リャンは多少の警戒感を滲ませつつも、素直に俺の後を付いてきた。螺旋階段を降りつつ、リャンは気になっていたのか質問をしてきた。
「オマエ、名前なんて言うネ」
そういえば俺自身は名乗っていなかったな、と思って俺も名乗る事にした。
「崎守零二だ。零二が名前」
「レイジか。レイジは不思議な男ネ。どうしてここまで来れた?」
質問の意味が判り兼ねるが、もしかしたら俺に何か特別な力があるのでは、と聞きたいのかも知れない。
「心眼のおかげかな」
だがリャンは日本語が不自由な為か、心眼の意味が判らないらしい。
「シンガン?」
そこで俺は、リャンに判りやすい表現を使う事にした。
「中国武術に『聴勁』ってのがあるらしいじゃないか。そういった類いのもんだと思ってくれていい」
『聴勁』とは、相手の筋肉の動きとかを察知して、行動を予測する技術の事だと何かの漫画で読んだ記憶がある。拡大解釈すれば心眼も似たような結果を得る事が出来るので、こういう言い方なら判って貰えると考えた。リャンはやっと理解が及んだのか、眼を丸くして俺を見た。
「……ソレはマスタークラスのスキルネ。レイジ、ワタシより若いネ。とても信じられないヨ」
そんな事を言われても出来るんだからしょうがない。俺はそれ以上の説明をしても納得させられるか判らないし、納得させる必要も感じなかったのでその話題はスルーする事にした。
それよりも。
「……若いって、リャンの年齢は?」
「二十二歳ネ」
――嘘だろ?
どう見ても、中学生くらいにしか見えない。身長は152〜3センチといったところだろうし、何より顔立ちが幼く見える。
何か言おうかとも思ったが、女性に年齢の話はタブーだと世間では言われているらしい。
だから黙っておく事にした。
俺は階段を降りながら、縦穴状のこの空間を改めて見回した。螺旋階段と表現したものの、この階段は一般的に螺旋階段と呼んでいるものとは少々違う。
円筒状の外壁に沿って螺旋状に造られており、その規模は大きい。そして円筒状の中心、広大な空間には巨大な鉄柱が何十本も縦に突き立っており、それぞれの柱をいくつもの歯車が動かしている。一体何の仕掛けなのか、規模が大き過ぎて想像するのは難しい。
螺旋階段を降り、下層へと辿り着く。
エントランスホールのような広場を抜けて先の部屋に入ると、エリカとミノタウロスの戦いが目の前で繰り広げられていた。ミノタウロスの繰り出したショートアッパーの様な技を、エリカが楯で防いだところだった。だが、凄まじい衝撃力によってエリカの身体は容易く宙へ浮き、天井の石壁に背中から叩き付けられる。
「はぐッ!!」
上方向への強烈な慣性力によって、天井に縫い付けられたエリカの胴体目掛け、跳躍したミノタウロスの頭突きが炸裂する。
ドゴン!!
「がッ!?」
天井と頭突きのサンドイッチによって、エリカは口から血を吐き出した。おそらく、衝撃で内蔵が破壊された筈だった。床に着地したミノタウロスの頭上に、エリカの身体が落ちてくる。
「――奮ッ!!」
背中からぐるりと回す形で、右の拳を叩き付けるミノタウロス。
ガスン!!
まともに拳の一撃を喰らったエリカが床に叩き付けられ、大きくバウンドして俺の近くまで勢いよく転がってくる。
「エリカ!!」
俺の声を聞き、床に這い蹲ったエリカが何とか立ち上がった。
「……げほッ、れ、レイジさん」
酷い状態だった。
すぐに敗けるような事は無いと思っていたが、俺の見立ては甘かったらしい。――肉体の回復力が遅いのだ。だが俺の姿を認識したエリカが、安心した表情を浮かべた。
「良かった……これで回復能力が元通りになります」
そう言って目を瞑ると、肉体に受けた深刻なダメージはすぐに完全回復を果たした。
「どういう事なんだ?」
どうも俺が到着するまでの間、エリカの回復力が著しく低下していたようだ。完全に回復したエリカを見据え、ミノタウロスが手を休めて口を開く。
「……そうか貴様――完全な状態じゃないな?」
それでも俺には、何の事なのか判らなかった。完全じゃない、と言うミノタウロスの言葉を信じるならば、エリカは不完全な状態だと言う事は判る。
しかし何を以て不完全と言うのか。俺の疑問を察知して、エリカが立ち上がりつつこちらを見る。
「バックアップシステムが置かれているワルハラが、完全な状態では無いのです。現状では、契約者として登録を完了したレイジさんの存在は常にサーチするように変更されてますが、私自身はシステムへの登録が不完全な状態なんです」
なんだか、コンピュータ関係の話でもしてるのかと錯覚してしまう。
「それで?」
「ワルハラに登録された私自身のオリジナルデータは大昔のものなので、今の私だと最適化された状態とは程遠い為に、ネットワークに遅延が生じます。具体的にはエネルギー供給の遅延という形になって表れますが、レイジさんが側にいる場合は、時空間追跡プログラムがレイジさんを挟んで私を正常認識する事で改善されます」
技術的な事は判らないが、要するに俺がいる時といない時でエリカの力に差が出ると言う事なんだろうか。ミノタウロスは俺を見て口を開く。
「よく無事に、ここまで来れたな」
そこへリャンが前へと躍り出て、ミノタウロスを説得に掛かった。
「レイジ、宝無い言った。戦い辞めるヨ、ツァオシン」
それを聞いたミノタウロスは、顔を横に振って否定の意志を示した。
「それは違う。確かにその男は宝など持ってないが、女の方はどうだろうな?」
話題を振られ、エリカが顔を強張らせる。その反応が不自然だった為、俺もリャンもエリカに注目した。何も言おうとしないエリカに対し、リャンが懐疑的な視線を向けたまま返答を促す。
「……お前、宝持ってるのか? レイジ持ってない言った」
だがエリカはそれでも何も言おうとはしない為、ミノタウロスが代弁するかの様に説明する。
「言える訳が無い。この女は一番世代の若い神族。古代文明の遺産について詳しくはないのだ」
「古代文明の遺産……それが、貴方達の戦う理由ですか?」
エリカの反応を聞き、ミノタウロスが首を振る。
「別に俺自身は、そんな物には興味は無い。だが俺自身が遺産を持っている為に、戦いは避けられん。この迷宮こそ、古代文明の遺産の一つだ。そして、貴様の持つ遺産も見当は付いている」
俺は成程、と思った。
確かにこの迷宮の造りや機構などを考えると、現代のテクノロジーとは全く別系統の進化を感じる。宝の見当が付いていると言われ、エリカは難しい顔をする。やはり本人には判らないのだろう。
「ふん――グングニルと言ったか。あの槍こそ、古代文明の遺産の一つだ」
それを聞いたエリカは一瞬だけ驚いたものの、すぐに反論をする。
「まさか。グングニルは小人から、主神オーディーンに託されたものだと聞いています」
「その小人とやらが古代文明人の末裔なのだ。小人と揶揄されたのもそいつらがアジア人だったからだが、今では神としても滅んで久しい」
正直、俺には付いて行けない話だった。
年代別の文明の勃興と、神の関係の一端が知れる内容だとは思うが、現代においてはそれらの事実は殆ど伝わっていない。
その理由としては、東洋において栄えたとされる環太平洋文明圏が海中へと没した為、現在に遺された遺物が限定的である為だし、西洋においてはキリスト教によって古代文明の遺産は発見次第、その都度封印されてきた為だ。
「貴様は戦いを避けようという姿勢のようだが、その槍を持つ限り戦いは避けられんのだ。今はまだ、貴様の存在が知られていないのが救いになってると知れ」
何も言い返す事の出来ないエリカに代わり、俺が反論する。
「そうだとしても、アンタと戦う理由にはならないだろ」
だがミノタウロスは、呆れたかのような口調で返す。
「いずれ倒れる運命ならば、先に俺が喰わせて貰う」
ミノタウロスには何を言っても無駄なのかも知れないと思った俺は、リャンに向かって再度聞いた。
「リャンはどうなんだ?」
リャンとは少しだけ判り合えたかと思っていたが、エリカが宝を持っているとすればそれもご破算だ。困ったような表情をして、リャンは首を振った。
「……レイジ戦いたくない思ってる判るヨ。だからワタシ、レイジと戦わないネ。でもツァオシン、その女と戦うのは止めないネ」
リャンの答えは妥当な線だろうと思う。だがミノタウロスは、リャンに対しても反論を返す。
「馬鹿を言うな。そいつも後でやらせてもらうぞ」
だがリャンは、強い口調でミノタウロスを叱りつけた。
「駄目ネ! 宝、手に入る、レイジ死ぬ必要、ナイ。ツァオシンたまには我慢するネ!!」
おそらく、リャンには頭が上がらないのだろう。ミノタウロスはバツの悪そうに呻いた。
「……むぅ、ならばワルキューレの方で我慢するか」
リャンとの話が付いたミノタウロスが、改めてエリカを見る。
「話が付いたところで早速、再開といきたいところだが、その前に貴様の神としての本当の名を聞かせて貰おうか」
何の意図があるのか、ミノタウロスの質問にエリカは難色を示す。
「神として君臨するつもりが無い以上、神名を明かすつもりはありません」
そんな事を言いつつ、一瞬だけエリカが俺を見た。
何だ?
僅かばかり、俺に対する遠慮が垣間見えた気がしたが、ミノタウロスにエネルギーが集中するのを感知して有耶無耶になってしまった。
「ふん、まあいい――行くぞワルキューレ!!」
戦いが再開される。爆発的な脚力でミノタウロスが突進する。先程までの戦いで遠距離での戦いを諦めたのか、エリカも軸をずらしつつ突撃する。
「奮ッ!!」
ミノタウロスの剛腕から、突きが繰り出される。
「はあッ!!」
エリカの右手に握られた光を伴った剣先が、その腕を弾き飛ばす。そんな事はお構いなしに、ミノタウロスはさらに右肩から体当たりへと移行する。だがエリカは一気に宙へと飛び上がり、とんぼ返りでミノタウロスの背後を取る。
反応の遅れたミノタウロスの背中に、左腕の楯を押し付ける。
「シュネレ・エントヴィックルング!!」
「何ッ!?」
まさか楯から生じる防御壁を、攻撃に使うとは予想も付かなかったのだろう。
バツン!!
強烈な光が迸り、ミノタウロスの巨体が背中から弾き飛ばされる。蹌踉めくミノタウロス目掛け、エリカが渾身の突きを繰り出す。
ガンガンガンガン!!
連続で繰り出される突きを背面に受け、ミノタウロスが壁際まで吹き飛ばされる。
「――舐めるなあッ!!」
怒りを露にして反転したミノタウロスの腕が、エリカの突きを弾き飛ばす。
さらにもう一方の腕から突きが放たれ、エリカは弾き飛ばされた剣をそのまま背中から反転する事によって再度、攻撃に転じて応戦した。互いの拳と剣が何度も交じり合い、火花が散る。
俺が近くにいる事でエリカのエネルギー出力が元に戻った為か、ミノタウロスとのパワーバランスはほぼ互角。体重に勝るミノタウロスが本来なら力においても上だが、どうやらエネルギー出力ではエリカの方が勝っており、結果的には互いの力の差は殆ど無くなっている。
俺はエリカの剣技の程を初めて目の当たりにし、これが古代西洋式の技かと興味深く観察していた。あまり知られていない事だが、西洋でも相応の剣技は存在する。
例えば古代ローマにおけるコロセウム、そこで日々戦いを繰り広げていたとされる剣闘士。有名な逸話としてパンクラチオンと呼ばれる総合格闘技からボクシング、レスリングなどが生まれたと言われている。
剣による戦いが銃に取って代わられた為に現代には伝わっていないが、そういった戦闘スキルの一つとして剣による技も存在していた。エリカの使う技は古代バイキングより遥か昔までに遡る、神代の古式剣術だろう。
足場の悪い船上から浜辺といった足場の悪い地形、そして揚陸から村々を強襲するスタイルによって生み出された古式剣術は、見た目の印象では小さくジャンプして繰り出す剣撃や、反転しつつ打ち降ろす技が多く、ダイナミックな動きが主体となっている。
日本の剣術が摺り足主体で地に足を付けて、歩行の安定性を重視するのとは大きく違い、エリカの使うそれは時折片足を持ち上げてステップを踏む軽快な動きが主体である。身体全体を使って打ち降ろされる剣撃は、日本刀の様な『斬る』動きとは異なり、西洋の『叩き付ける』動きに合ったものだと判る。
まさにパワー対パワーの対決。
エリカのスキルは決して低いものでは無く、古式剣術がもし今でも健在で、中国や日本の様に極限まで練り上げられていたのなら、おそらくはこのエリカのようになっていた筈だと思える程に高い技術を感じさせるものだ。力強さの中にも、しっかりとした技術が根底にはあるのだ。
でなければミノタウロスの使う『心意六合拳(しんいろくごうけん)』と五分に渡り合える筈が無い。対するミノタウロスの技も半ば伝説の武術であり、ギリシャ神話の伝説の化け物が使っているのが不思議な気もしないでもない。
『心意六合拳』とは、中国内陸部においてイスラム教を信奉する、回族と呼ばれる民に伝わる武術だと聞く。勇猛かつ苛烈、強力な突進力を利した、破壊力に富む拳の一撃。そして人間が扱えるレベルにおいて、最大の威力を持つ体当たりの衝撃。
体当たりなどと聞くと、アメフト選手やレスリングの選手の用いるタックルを思い浮かべてしまうが、こと『心意六合拳』においては、相手を押し倒す為に使うものでは無い。一撃必殺、一撃必中を信条とし、肩や頭部を相手に叩き付ける。それによって得られる一撃は、拳に比べて衝撃の乗る接触面積が大きく、威力もそれに応じて増大するのだ。
だが、ミノタウロスの3メートルを超える巨体で扱う『心意六合拳』はそんなものでは無い。人間のレベルを大きく超えた神域の発勁の威力は、もしかしたら高層ビルでも一撃で粉砕してしまいそうな程だ。
本来は内功と言われる発勁は、そういった外面の破壊には不向きな筈なのだが、ここまでの威力となってしまうと内部に蓄積された衝撃は内部に留まらず、結果的に物質の外面すら破壊するだけの威力がある。
エリカは容易く打ち合っているように見えるが、実際は打ち合うたびに剣を持つ手が痺れて麻痺している筈だ。普通の人間ならば腕の骨が複雑骨折をし、さらに筋組織すら破壊されてしまう。
エリカは驚異的な回復力で、瞬時に腕の破損を回復させつつ打ち合っているのでまともに渡り合えるのだ。
「……レイジの女、凄いネ。ツァオシン本気ネ」
人知を超えた戦いに、リャンが溜め息をついた。
リャンも達人級とまではいかないまでも、普通の人間としてはかなり出来る。エリカとミノタウロスの戦いは人間を超えたスピード同士、目で追うのは難しいのだが、リャンは何とか目で追っている。
エリカの剣に対抗する為にミノタウロスは腕を硬気功で防御しており、その為か発勁の威力は半減している。それでもまともに当たれば、エリカと言えども一撃で死を迎える。
エリカの剣は光のエネルギーを纏っている為、打ち合う度にミノタウロスの腕に火傷の跡が残る。ミノタウロスもエリカと同様、打ち合う毎にダメージを受けているのだ。
そういった面でも、両者は五分の条件。
打ち合い、回復しつつまた打ち合う。
これは何かの話で聞いた、千日戦争の様相を呈してきた。
決定的な差が無い両者の戦いはエネルギーの浪費によって、長期の戦いの末にどちらかが先に動けなくなるまで続く。尤も、神同士の戦いとはこうなる事が多いとエリカに聞かされている。
その為に、『滅殺兵器』と呼ばれる強力な切り札を所有しているのだ。それがエリカにとってはグングニルだが、もしミノタウロスにも『滅殺兵器』があるとしたらどうなのか。その答えが今、目前にて披露されようとしていた。
「――ラビュリントス起動!!」
突然の宣言に、エリカの動きが止まる。
「な!?」
轟く轟音。
俺は『心眼』によって、膨大なエネルギーがこの迷宮全体を動かしているのを感じていた。
「気をつけろ、エリカ!」
空間が歪み、辺りの景色が一変する。
「え!?」
驚きに目を見開くエリカ。
それもその筈。
エリカを中心とした部屋にいくつもの通路が四方八方に伸びている。それどころかエリカは部屋の中央に浮いており、部屋から伸びる通路は上下関係無しに存在したのだ。部屋と形容した空間は、エリカを重力の中心として機能していた。


第二話・獣神咆哮